「交渉というのは、勝ち負けを競うものではなく、問題解決への近道なのです。」
仕事の取引先と、製品の価格について・・・・リードテキストリードテキストリードテキストリードテキストリードテキストリードテキストリードテキストリードテキストリードテキストリードテキスト
−− |
多くの方が、自分なりの交渉術を編み出しているものの、そこに確信のある方は多くないようです。 |
野沢 |
「交渉」と言うと、ちょっと固く感じるかもしれませんが、夫婦間、友達同士、あるいはビジネスや国際社会の場で、当事者同士が話し合って問題を解決するという場面は日常茶飯事です。ただ、日本人の多くは、交渉する事に苦手意識を持っているようです。アメリカなどでは小学校の頃から、教育の中に交渉というテーマが取り入れられていますが、日本では、交渉を体系的に学ぶ場面がありませんし、言葉で伝えるというよりも、あうんの呼吸で互いに通じ合うことを良しとするような文化的な背景もありますからね。 |
−− |
和を重んじる日本人にとっては、自分の主張をはっきりと伝えることを、わがままと感じて嫌う人も多いのではないでしょうか。 |
野沢 |
ええ。特に、皆さんの中で交渉とは自分の意見を通すこと、つまりは勝ち負けを争うものだと思っているところがあると思うのです。確かに、それが今までの欧米流の交渉においても重要視されていましたが、最近、「協調的交渉」という新たな考え方が広がりつつあります。 |
−− |
アメリカで生まれた考え方ですね。 |
野沢 |
|
−− |
先のミカンの例では、よく話してみると、実はミカンを食べたいと思っているAさんと、香り付けに皮が欲しいと思っていたBさん、という結末だってあるじゃないか、というわけですね。 |
野沢 |
そうなのです。全員が同じゴールを目指しているわけではないというのが、協調的交渉の大前提です。だからこそ、その人にとって一番大事なゴールをお互いに尊重し合っていくために話し合う。もし目指すゴールが同じだったら、その他に大事なものは何かを互いに探していく。つまり協調的交渉というのは、コラボレーションなんです。二人が協力し合う事によって、素晴らしい発想が生まれるかもしれないし、第三の道が作れるかもしれない。今までは対立してせめぎ合ってきたけれど、それよりも協力して知恵を出し合って、もう一つゴールを作りましょうという考え方なのです。二人のコミュニケーションの中で、十二分に情報化して話し合って、いろいろな方法を探っていった方が、一人より良く出来るよという感覚ですね。 |
−− |
相手に負けまいという競合的交渉では発展性がないとして生まれたのが、協調的交渉でもあるとか? |
野沢 |
利害の不一致や意見の食い違いによって起こる対立や紛争、衝突を、英語で「コンフリクト(Conflict)」と言います。対立や紛争と聞くと、ネガティブなイメージを抱くでしょうし、誰もがそれを避けたいと思うでしょう。アメリカでは、そうした対立があまりにも多いが故に、それに関する研究が進んだのです。コロンビア大学の名誉教授であるモートン・ドイッチ博士は、対立には、確かにネガティブな面もあるけれど、対立によって相手への理解が深まったり、個人が成長したりというポジティブな面もあると報告しています。 |
−− |
正に伺いたいと思っていたところです(笑)。実際、どんな風に協調的交渉に臨めば良いのでしょうか。 |
野沢 |
お互いの問題を「我々の問題」と捕える事です。「窓を開けたい」「私は嫌」だけでは、対立した感情がくすぶったままで終わってしまいます。そこで対立が起きたら何とかして互いに話し合って、「私はこの問題を解決したいのだ」というメッセージを伝えることです。そして「私とあなたは同じ仲間(あるいは同僚や家族)なのだから」という共有できるメッセージも伝えるといいですね。 |
−− |
窓を開けたいという気持ちを一つとっても、いろいろな思いが裏にはあるわけですね。 |
野沢 |
そうです。発達心理学でもよく言うのですが、相手の本音に触れた時、心へのインパクトが与えられ、その度に、人は成長するのだそうです。私たちが歩み寄れない時は、その下に隠れている本音が分からない時なのです。 |
−− |
では、協調的交渉術を身につけるには、どんなことが必要でしょうか。 |
野沢 |
まず問題が起きた時、その状況、原因、結果について考える事が大切です。私は、大学やセミナーなどで、新聞の人生相談の欄に掲載されていた記事を元に、実践的な授業をしています。 |
−− |
自分でも意識していない本音かもしれませんね。 |
野沢 |
そうなんです。特に日本人は、自分の本音を分かっていない人が多いと思います。日本の社会では、自分が何を欲しているかを問われる場面というのが少ないからかもしれません。例えばアメリカでは子供が小さい時から「何を食べたい?」と聞く。「ジャムは付ける?」「付けるとしたら、マーマレードとイチゴジャム、どちら?」「ミルクとジュースがあるけれど、どっち?」等々。ところが日本のお母さんは、全部用意して「おいしかった?次はこれを食べましょう」と言う。つまりアメリカでは、小さい時から自分の欲求は何かを表現するトレーニングを、無意識の内にお母さんがしているんですね。 |
−− |
分析表における「問題の見直し」という部分ですね。 |
野沢 |
そうです。本音を知れば、やはりお母さんが自分を本当に愛しているのだと息子は知る。お母さんの方もコントロールし過ぎたのかもしれないと気付く。そうすれば、相手に歩み寄って、問題を解決しようという姿勢になるんです。 |
−− |
もし対立点で止まっていたら、決裂したまま、関係が終わってしまっていたかもしれませんが、互いの本音が分かって相手に配慮できるようになると、新しい良い関係が生まれる可能性がありますね。 |
野沢 |
|
−− |
家族間だけでなく、あらゆる交渉、コミュニケーションにおいても影響のある方法ですね。 |
野沢 |
ビジネスの現場だと、往々にして、それぞれが主張だけをする傾向にあります。日本では「落としどころ」と言いますが、日本人が交渉下手だと言われるのは、相手の主張を聞いた途端に、すぐアイデアを出すからです。もちろん「相手は、これで満足するはずだ」と、思ってアイデアを出すわけですが、本当に相手が満足するかどうか…。そこで、次に必要になるのが、十分な情報交換です。 |
−− |
相手の本音を知るために、ということですか。 |
野沢 |
そうです。相手の主張は分かっても、その時点では、本音は推測するだけで、正しいかどうか、確かめていないということが多いのです。先にお話した分析表にしても、あくまでも推測です。交渉の場というのは、原則的に相手の主張はすでに分かっていて、それに対して先の分析表のようなものを使って自分なりの考察を加えて準備をした上で、相手の本音と欲求に迫ろうという場です。「あなたが、こうおっしゃっている下には、こういう事を考えているのではないか。それで間違いありませんか?」と。 |
−− |
なるほど、日本人には、自分の本音を分かっていない人が多いとありましたが、そうでなくとも、なかなか簡単に本音を言わないという人も多いのではありませんか。 |
野沢 |
おっしゃるように、人は相手をよほど信頼していないと「あなたの欲求は何ですか」と、聞かれても言わないものです。ですから、協調的交渉をする上では、相手との信頼関係を作る事も大切です。「あなたの話を聞いていますよ」というメッセージを伝えるために、目を見て、うなづいて、相づちを打って、という聞く姿勢も求められます。 |
−− |
そうやって、相手の本音に迫り、問題解決に結びつけていくわけですね。 |
野沢 |
情報収集のスキルをアップさせるために、学生には、日常の中で、誰かが言った事を、もう一度言い換える練習をどんどんやりなさいと言っています。それに、言い換えられると「私の事を理解しようとしているのだ」というメッセージが伝わりますし、質問すれば「この人は私に関心があるのだ」と、思うものです。そうしたコミュニケーションのスキルを、交渉の中で、上手く駆使していく事が大事ですね。 |
−− |
こうした「交渉術」が競争社会の最たるものと思われているアメリカで生まれたというのは、興味深いですね。 |
野沢 |
以前は、競合的交渉一辺倒でしたが、今は、もう少し個を大事にしようという考え方にシフトしていると思います。交渉と言っても結局は人と人の営みですから、対立するよりも、二人で問題を解決すべく力を合わせた方が、新しい発想が出てくるというのが基本じゃないかと思うのです。 |
−− |
では最後に、こちらが協調的交渉を進めようとしても相手が競合的だった場合、どのように交渉を進めれば良いのでしょう? |
野沢 |
その質問は、とてもよく受けるのですが(笑)、相手が競合的だと、多くの人が反発するでしょう。でも、それは絶対してはいけません。あくまでも協調的態度を崩さないことです。そうすることで、こちらの協調的態度が相手の協調的態度を招くようになるのです。相手が競合的な姿勢でも、とにかく聞く。つまりひたすら情報収集する事によって、相手の競合的態度がトーンダウンしていくのです。トーンダウンしない限り、質問は出来ませんから、ある程度の時間はかかりますし、相手が何か言うと我慢出来なくなって、思わず自分の事を言ってしまう場合も多いでしょう。なかなか、簡単にできないかもしれませんが、問題を解決するという目的を見失わないようにすればいいんです。 |
野沢聡子(のざわ・さとこ)
(有)教育総合企画代表。慶応大学卒業後、読売新聞社英字新聞部(The Daily Yomiuri)記者を経て、1996年コロンビア大学教育学大学院(Teachers College)に留学。International Education & Transcultural Studies修士。1999年5月に(有)教育総合企画(TCS)を設立。現在は、主に「協調的交渉術」トレーニングの普及に取り組む。地方自治体での職員研修、法政大学エクステンション・カレッジの公開講座講師、2003年4月からは昭和女子大学総合教育センター講師。著書に『"交渉美人"は生き方上手』(郵研社)、『問題解決の交渉学』(PHP新書)、監修・訳書に『協調的交渉術のすすめ―国際紛争から家庭問題まで』(アルク)など。
●取材後記
野沢さん曰く「日本のビジネスの現場では、メンタリティは割と和を重んじる集団主義だけれど、ビジネス自体はグローバル化してアメリカ流の競争社会。今は、集団主義と個人主義とが混在した状態で、その中で私たちは非常に葛藤しているのだと思う」とのこと。だから、相手の本音を探るのが重要なのと同時に、対外交渉では、はっきりした態度で自分の意思を伝える事が大切だとか。「『言わなくても分かる』というのは、あり得ませんよ」。当たり前のことなのだが、ついつい過剰に期待していたかも、と思い当たる節がなくもない。
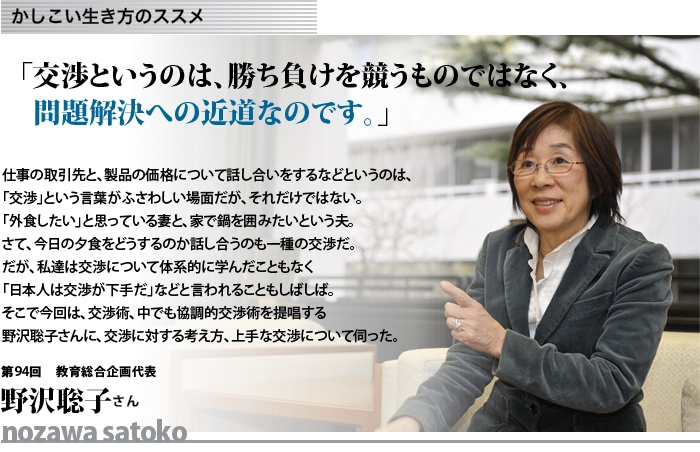
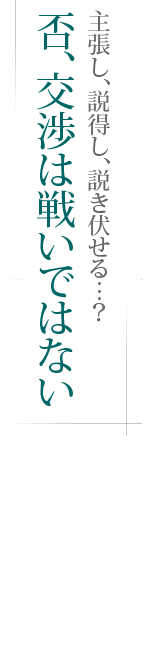
 ええ。今までは限られたパイを、なるべく多く取ろうとしてきた――つまり強者のための交渉と言えます。従来の問題解決では、自分の取り分を縦軸、相手の取り分を横軸としたグラフで考えた場合、相手が100取ると譲歩、自分が100取ると競合、50対50なら妥協といった区分があります。それ以前に、争うのは嫌だからと、問題を最初から見て見ぬ振りをする、諦めてしまうというケースもあり、回避と呼ばれています。つまり私たちが、何らかの形で問題解決しようとした時、これら4つのやり方――競合、譲歩、妥協、回避しかなかったのです。
ええ。今までは限られたパイを、なるべく多く取ろうとしてきた――つまり強者のための交渉と言えます。従来の問題解決では、自分の取り分を縦軸、相手の取り分を横軸としたグラフで考えた場合、相手が100取ると譲歩、自分が100取ると競合、50対50なら妥協といった区分があります。それ以前に、争うのは嫌だからと、問題を最初から見て見ぬ振りをする、諦めてしまうというケースもあり、回避と呼ばれています。つまり私たちが、何らかの形で問題解決しようとした時、これら4つのやり方――競合、譲歩、妥協、回避しかなかったのです。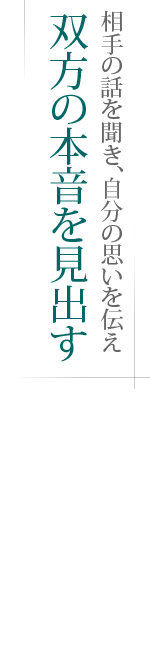
 相手の本音が分からない時に不信感が生まれるというのは、心理学の実験などでも明らかなのです。そして自分の本音を相手が分かっていないとしたら、しっかりと言わなければいけません。これも「言わぬが花」の日本の文化にあっては不得意な人もいるでしょう。ですが、言わないと、不安が膨らんで「あいつは敵に違いない」と、想像ばかりが広がってしまう。もちろん聞きたくない本音もあるはずですし、きれいごとでは済まないかもしれないけれど、言わないと相手には伝わらない。もし言うことでコンフリクトが起きても、それを受け止めた時に、人は成長するし互いの関係も強くなります。
相手の本音が分からない時に不信感が生まれるというのは、心理学の実験などでも明らかなのです。そして自分の本音を相手が分かっていないとしたら、しっかりと言わなければいけません。これも「言わぬが花」の日本の文化にあっては不得意な人もいるでしょう。ですが、言わないと、不安が膨らんで「あいつは敵に違いない」と、想像ばかりが広がってしまう。もちろん聞きたくない本音もあるはずですし、きれいごとでは済まないかもしれないけれど、言わないと相手には伝わらない。もし言うことでコンフリクトが起きても、それを受け止めた時に、人は成長するし互いの関係も強くなります。