「今の幸せがあるのは、自分を裏切らないという生き方ができたからです。」
ドキュメンタリー映画の監督、関口祐加さんが インターネットにアップしている映像が話題を呼んでいる。 認知症を発症した自身の母親の日常を自分で撮影し、 それを公開しているものだ。その映像には、 症状が進むお母様とそれを朗らかに見守りつつ、冷静に映像化する 関口さんの姿が見て取れる。自分の前に現れるさまざまな現実の問題に どう向き合うのか、真摯に対象にぶつかる関口さんに聞いた。
−− |
元々、映画やドキュメンタリーに興味があったのですか。 |
関口 |
大学を出てすぐにオーストラリアに渡り、2010年の1月末に日本に帰って来るまで、丸29年間向こうにいました。最初は、オセアニアの国際関係論を研究する学者になろうと、両親には「2年で日本に帰って来る」と約束して、オーストラリアの大学院に入ったんです。けれども、向こうに行って1年もしないうちに「これが本当にやりたい勉強なのか?」と思い始めて(笑)。そんな時、著名なアメリカ人の文化人類学者であるマーガレット・ミードの記録映像を観たんです。この映像が、私の人生を…。 |
−− |
狂わせた? |
関口 |
そうそう(笑)。「変えた」と言いたいけれど、狂わせたんです(笑)。白黒の16mmの映像で、時代は1930年代。ニューギニアの葬儀の様子を撮った映像です。顔に石灰を塗って悲しみを表す現地の人たち。ミードはその傍らで、自分の論文のために無遠慮にパチパチとタイプを打っている。それを見た瞬間に「何だ、この女!!」と。有名な人類学者かもしれないけれど、自分の論文のために葬儀を「観察」しているという本音が露骨に現れたショットを観て、すごく頭に来たんです。でも同時に「そういう感情を一瞬にして引き出す映像ってすごい! 私がやりたいのはこれだ!」と、天の声を聞いてしまったわけです(笑)。 |
−− |
いきなりの展開ですね。 |
関口 |
私の性格は亡くなった父に似ていて、猪突猛進。やりたいと思ったら、どんな事があっても絶対にやる。思い立ったら吉日。それまで、全く映画の勉強もしていないのに「私は、これをやるために生まれてきたんだ!」と確信しました(笑)。 |
−− |
前作の『THE ダイエット!』は、ご自身が出演して、いろいろなダイエットの手法を試しつつ、最後は自分でも気づかなかったご自身の内面まで浮き彫りにするという内容です。 |
関口 |
『THE ダイエット!』は、自分を受け入れられるかどうか、つまり自己受容がテーマなんです。映画の中では、精神科医の先生とセラピーをやりましたが、オーストラリアでは肥満というのは国が抱える切実な健康問題であって、栄養管理やカロリーコントロールではとても間に合わない。だから自分自身を見つめるところまで下りていかないと改善するのは難しい、つまり肥満は、心の問題なんです。 |
−− |
日本でも、多くの女性がダイエットをしなくてはと言いますが? |
関口 |
日本に帰って来て、皆、どうして自己肯定感が低いんだろうと思いました。言い変えれば、今の自分に満足出来ないという人がたくさんいるのかなって。だから「体が変われば、何かが変わるかもしれない」と考えて、その手法としてダイエットを試みる方が多いのでしょうか。でも、体型を変えても問題は解決しません。自分の生き方を変えなくては。 |
−− |
関口さんご自身も自己肯定感が低かったわけですか。 |
関口 |
|
−− |
セラピーの様子やご両親との関係など、あそこまで自身をオープンに出来るというか、さらけ出して怖くないですか。 |
関口 |
ドキュメンタリーの監督は「被写体を裸にしたい」と思っているのですよ(笑)。これは、私が師匠と呼んでいる原一男監督の言葉です。では、どうして自分が被写体になったのかというと、一つはドキュメンタリーを撮る上では、いつも被写体とのモラルの問題がつきまといますが、自分が被写体になってしまえば、何でもありじゃないですか。「さらけ出す」というのは、心を裸にするという意味で、それは自分だから出来るーーそういう覚悟で撮りました。また、ドキュメンタリーの被写体は、生身の人間なので、その人に対して責任を取らなければいけないし、映画の撮影が終わっても、関係性は切れません。そういう意味では、自分を裸にした方が楽と言えるかもしれません。 |
−− |
そうは言っても、自分が知らなかった自分に出会う場面を公にするというのは、勇気がいるのではと思います。 |
関口 |
もちろん、個人としてショックなことはありましたが、頭のどこかで監督の自分が「いい映像が撮れたな」とほくそ笑んでいるんです(笑)。今、アルツハイマーを患っている母を撮っていますが、娘としてはショックを受けていても、監督としては非常に冷静な視線で「この発言なら、こんな映像がいるな」と計算しているんです。 |
−− |
映画の中で、関口さんご自身の中で、父系の自分と母系の自分、その両者の葛藤と融合も描かれています。関口さんご自身は、お父様の性格に近いそうですが。 |
関口 |
うちの母は、自分にも他人にもすごく厳しい人でした。一方、父はとても能天気で、米穀商を営んでいたから、働く時間も自分の好きなように決めていました。仕事に対しての姿勢は、父に影響されているのでしょうね。それに、父の死に方も特筆に値するんです。もう10年程前ですが、ある時突然「俺は何て良い人生を送れたのだろう。何も後悔はない」と言って、貯金通帳を出してきて「俺はもういらない。おまえには苦労かけたな」と母に渡したんです。そしてその5分後に、トイレの中で突然死しました。父にそういう予感があったのかどうか分かりませんが、最後に「悔いはない」と言い切って逝くことができるのは、すごく幸せだなと思いましたし、父が亡くなったのは悲しかったけれど、今のこのままの生活だったら父のようには死ねないなと思ったんです。当時は結婚していて、母にもなったけれど、父のように死ねるのか、と。私は、とにかく映画を作りたかったから、それで離婚を決意したんです。 |
−− |
今、認知症のお母様を被写体に新作『此岸、彼岸』という映画を撮影されていますね。 |
関口 |
2009年9月22日、母の誕生日に初めてカメラを回したのですけれど、それ以前にすでに「大丈夫?」と思うことが何度かありました。ちょうど『THE ダイエット!』のプロモーションで、日本とオーストラリアを行き来し始めたころですね。実家に帰ったら、あれだけきれい好きだった母なのに、冷蔵庫の中がぐちゃぐちゃで。実は、母の母が認知症だったこともあり「これは変だな」と、確信的に思いました。そして、母の話なのだから自分でカメラを回すことにしたのです。 |
−− |
お母様を撮られた映像はYouTubeにアップされています。そこのお母様とのやりとりは、辛いとか悲しいとかではなく、楽しそうです。 |
関口 |
やはり母に対する贖罪なのだと思います。2年で帰って来ますと言っておきながら、29年帰って来なかったんですから(笑)。好きな事をさせてもらえた恩返しです。いえ、自分が、好きな事をしてきたから、どんなに母にわがままを言われても、すごく愛おしい、と受け入れられるのでしょうね。何か出来なくなったって、そうなっていくのは全て想定内。むしろ、ついに母が自分自身に正直に「嫌なものは嫌」と言えているなと、嬉しくなります。 |
−− |
お母様が、粗相した時、お母様ご自身「恥ずかしい」と思われることはないですか。 |
関口 |
母はもちろん恥ずかしいでしょう。そういう時は、周囲の対応が重要だと思います。そういう部分では、今回の映画のテーマは「人間の尊厳とは何か」ということだと思います。母だけでなく、母に関わってくれる介護関係の人たちも含めて、いろいろな意味で、人間の尊厳を問う作品になると思います。 |
−− |
介護の方というのは? |
関口 |
|
−− |
今のお母様を見ていると、失礼ですが全くそういう風には見えません。今のお母様は、柔らかくて、ユーモアがあって「ま、いいか」と、しなやかに流せる、そういう方に見えます。 |
関口 |
以前はまったく逆です、逆。すごく厳しかったですよ。「家が汚れるから」といって、友達も家に連れて来られませんでしたから。 |
−− |
ええ!?お母様と関口さんは、以前からああいった関係ではないのですか。 |
関口 |
ないです、ないです(笑)。母は、私達にも厳しかったけれど、自分にも厳しかった人です。その真面目できちんとした母の生き方とは真反対の生き方を選んだ娘二人ですから、それは推して知るべしですよ。それもあって、今の母を見ると、いろいろなことから解放されて、ふわーんと適当になって良かったと心底思うんです。人生の最終章で、やっと言いたい事を言って、やりたい事をやれているねって思うんです。以前の母のような性格で、最後まで行ったらきっと苦しかったと思うんです。 |
−− |
自分の母親を撮影するのは、どんなお気持ちですか。 |
関口 |
今回、初めて自分でカメラを回していますけれど、こういう風に母が言ったから、ああいう絵が必要だなと思いますし、レンズを通すと明らかに客観的になっている自分を認識しています。娘としてはためらうけれど、監督として「これを聞かなければ」と思う時もあります。決して、ホームムービーを作っているわけじゃないですし、本人に「ぼけていると思うか」と聞くのは、娘としては痛ましいけれど、世に問う作品として、監督としては聞かなければいけないという意識が、強くあります。 |
−− |
お母様の世代という側面もあるのでしょうか。 |
関口 |
今回、一緒に制作会社を立ち上げた渋谷昶子(のぶこ)監督は79歳、うちの母と同世代です。渋谷監督は大連からの引き揚げ者でいらっしゃるのですが、自立する道を選び、しかも私なんかより、はるかに早い時代に女性監督としての道を切り開いて来られました。そして、今も輝いていらっしゃる。すごい苦労がありながら、自分で道を切り開こうと思えば、母と同世代でもそれが出来たといういい例ですよね。一方、母は、チャンスはあっても踏み込んでいけなかったのだと思うんです。だから娘を見ていると「本当は自分だって」という可能性を感じて余計に頭にくるのではないでしょうか(笑)。きっと何かやりたい事があったし、能力もあって、自分が出来なかったのを時代のせいにしてきたかもしれませんが、認知症になって、それは嘘だと気付いたのだと思うんです。 |
−− |
公開する映画の素材をインターネットにアップするというのも、大胆な試みですね。 |
関口 |
馬鹿なことをしたと思わなくはないですが(笑)、格好良く言えば、自分にプレッシャーをかけているという側面があります。長く同じことをしていると、絶対に慣れが出てきます。ドキュメンタリーを撮ってきて、やり方や自分の領域に慣れてしまうから、自分でいさめよう、という気持ちです。自己受容についてお話しましたが、一方では、自分が自信を持っている時ほど自分を疑う、自己懐疑の姿勢も必要ですよね。 |
関口祐加(せきぐち・ゆか)
映画監督。1957年5月、神奈川県横浜市生まれ。1981年にオーストラリアに渡り、2010年1月末に帰国。第1回監督作品は、第二次世界大戦中に従軍慰安婦にさせられたパプアニューギニアの女性たちを撮ったドキュメンタリー映画『戦場の女たち』。東京国際映画祭・女性映画週間出品 / 日本カトリック映画賞最優秀映画賞受賞、メルボルン国際映画祭ドキュメンタリー部門グランプリ受賞、サンフランシスコ国際映画祭ベスト・ドキュメンタリー歴史部門受賞。1992年『When Mrs. Hegarty Comes to Japan』は、 オーストラリアの「お母さん」、ヘガティー夫人を横浜の実家に招待し、 家族で歓待するという家族間の異文化交流を撮った映画。シドニー国際映画祭デンディー賞ベスト・ドキュメンタリー部門ノミネート、オーストラリア・メディア賞審査員賞受賞、アムステルダム国際ドキュメンタリー映画祭観客賞受賞。2007年『THE ダイエット! (原題FAT CHANCE)』は自身を被写体とした第3作目で、オーストラリア・メディア賞ベスト・ドキュメンタリー部門ノミネート、東京国際女性映画祭クロージング作品、全米ライブラリー協会賞受賞。現在、自身の母を題材にした『此岸(しがん)、彼岸』を編集中。2011年3月、渋谷昶子監督と一緒に制作会社NY GALS FILMSを起ち上げた。
●取材後記
関口さんは、この記事のまま、いやそれ以上に温かく、深く、力強いという印象だった。そして、自分の弱さを見せられるというのは、本当に強くなくてはできないことだな、とつくづく実感した。そんな生きるパワーをもらったような取材。記事にそれが表れていれば幸いだ。
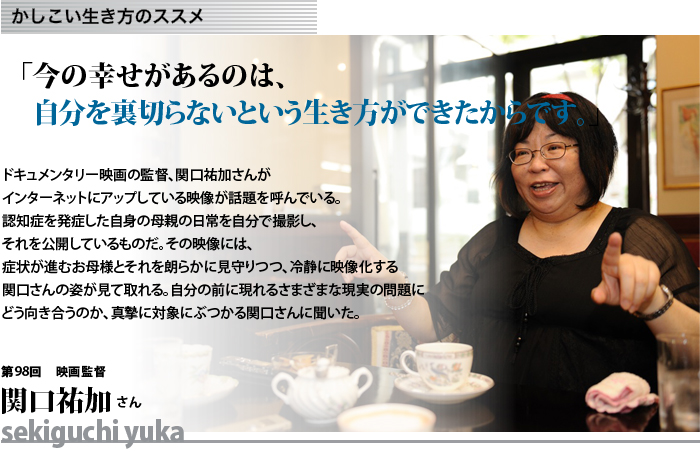
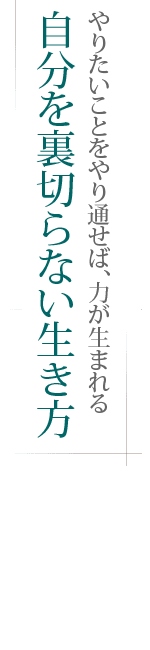
 オーストラリアという他民族国家の中では、アジア人である私は常にマイノリティですから、仲間に入れてほしい、オーストラリア人みたいになりたいという思いが、ずっとあったのだと思います。でも、蓋を開けてみると主流の白人たちは「変わってほしくない」と思っていたんです。マイノリティである私たちが持って来る「違うもの」が良いのであって、その違いを否定する必要などまったくなかった。だから自分が日本人であるということを再受容するということになったのです。
オーストラリアという他民族国家の中では、アジア人である私は常にマイノリティですから、仲間に入れてほしい、オーストラリア人みたいになりたいという思いが、ずっとあったのだと思います。でも、蓋を開けてみると主流の白人たちは「変わってほしくない」と思っていたんです。マイノリティである私たちが持って来る「違うもの」が良いのであって、その違いを否定する必要などまったくなかった。だから自分が日本人であるということを再受容するということになったのです。
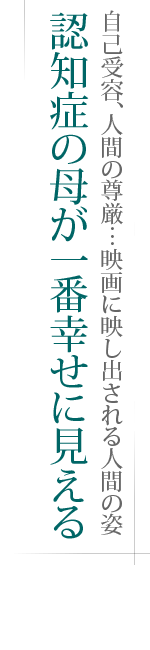
 うちの母が、なぜ医者を嫌いかという理由でもあるのですが、認知症、あるいはアルツハイマーと言うと、社会的にそういうレッテルが貼られてしまいますよね。医者から見れば、母は「せきぐち・ひろこ」という一人の人間ではなく「アルツハイマー病の患者」であって、話し方も赤ちゃんに向かうみたいになってしまう。そういう部分への、母の反発みたいなものが本能的にあるんです。それに対して母の反応が一番良いのは孫たちです。アルツハイマーになろうがなるまいが、おばあちゃんはおばあちゃん。社会的に、要介護がついているとか関係なく、平等に見てくれるからです。
うちの母が、なぜ医者を嫌いかという理由でもあるのですが、認知症、あるいはアルツハイマーと言うと、社会的にそういうレッテルが貼られてしまいますよね。医者から見れば、母は「せきぐち・ひろこ」という一人の人間ではなく「アルツハイマー病の患者」であって、話し方も赤ちゃんに向かうみたいになってしまう。そういう部分への、母の反発みたいなものが本能的にあるんです。それに対して母の反応が一番良いのは孫たちです。アルツハイマーになろうがなるまいが、おばあちゃんはおばあちゃん。社会的に、要介護がついているとか関係なく、平等に見てくれるからです。