「自分の食べるものを自分で作るなんて、なによりのぜいたくです。」
食に対してよりおいしいものを、より安全なものを求める 私達の気持ちは、ますます強くなっている。一方で、 食卓に並ぶ食材がどんな風に作られているのか、見たこともないし、 想像したこともないという人も少なくない。いつの間にか、 農と食の現場が離れてしまい、それが農業という場を厳しくしている…。 そんな現状を深く憂えて、何とかそれを打破しようと、 農園を運営し、消費者と農家をつなぐ活動を続ける えと菜園の小島希世子さんにお話を伺った。
−− |
小島さんの会社「えと菜園」では、今どのような事をなさっているのですか。 |
小島 |
事業には3本の柱があります。一つは「作る」。これは野菜の生産です。二つ目が「食べる」。生産物を多くのお客様に食べていただくための卸や直販。そして、消費者に農業の現場を知ってもらう、野菜の作り方を学んでもらう「学ぶ」。2011年の3月1日から始めた体験農園が、これに当たります。その3本柱を通して、生産して、加工も出来て、売れる農業というものを形作ろうと取り組んでいます。 |
−− |
そもそも農園を始められたきっかけというのは? |
小島 |
農家の奥さん達と一緒に立ち上げた、ネットショップが始まりでした。農家の方と生産者の距離、農業の現場と食卓の距離を縮めたいという思いからです。今、私達は毎日ご飯を食べているのに、目の前の食卓に並ぶ野菜や穀類が自然の中でどう育って、どう収穫されているかを知るすべもないですし、なかなかそれを意識しない、想像しにくい流通になっているのです。それをどうにかしたくて、農家直送のネットショップを立ち上げました。更に遡れば、農業系の仕事に就いたのは、もともと農家になりたかったからですね。 |
−− |
それには何か理由があったのですか。 |
小島 |
私は熊本の農村地域の出身です。隣り近所は皆農家で、格好いいトラクターもあるし、コンバインもある。なのに、うちは両親が高校教師だったので普通の乗用車しかない。「どうしてうちだけ普通の車なの!」と思いました(笑)。私の両親は週末も含めて帰りが遅いのですが、農家の友達の家は、昼ご飯まで一緒に食べていることもあります。それがとてもうらやましかったですね。 |
−− |
さすが高校の先生ですね(笑)。 |
小島 |
それでのせられたんですね(笑)。大学では、心理学を勉強したりと、寄り道もしましたが、農業を生業にしたいという思いは変わらずにありました。農家さんを見ていると「労働」ではくて「生業」というか、仕事が生活の一部なんだなという感じがします。「職」と「食」が密接につながっている場なんですね。 |
−− |
それは、いつ頃のことでしょう? |
小島 |
2004年ごろです。「自分のこだわりで農薬を使わず手間ひまかけて作っても、生産性を上げるために農薬と肥料を使って作っても、キロいくらという販売形式は変わらない」。つまりいくら味が違っても安全でも、品種が同じなら同じ値段でしか売れない、それが現状だというのです。それならと一念発起して「そのこだわりが伝わるように、作り方を知ってもらい、お客さんと距離が近づくような売り方をしましょう」と、農家直送のネットショップを立ち上げたというわけです。 |
−− |
消費者との距離が俄然、近くなりましたね。 |
小島 |
|
−− |
そういう農を体験すると皆さんの反応はいかがですか。 |
小島 |
例えば農薬を使わないと虫も来ます。実際に土に触れていると、そういうことを実感できて「有機の農家さんは大変なんだね」という声も聞けるようになります。もちろん農家さんが消費者に近づく努力はしなければいけないけれど、まずは消費者が、自分の食べるものが作られる現場を知るための場やサービスを提供したいですね。 |
−− |
その先には、こだわって生産する農業が成り立つような仕組みを作りたいということですね。 |
小島 |
ええ。これまでの農業は、残念ながら真面目に作ったら損をするというような形になってしまっていると思います。それでは産業として衰退するなという感じはありました。 |
−− |
例えるなら、職人さんが絹生地を使って手仕事で服を作っても、化繊を使って大量に作っても同じ値段だというようなものでしょうか。 |
小島 |
そうですね。今の大量生産、大量消費型の市場だったらそうならざるを得ないでしょう。それなら別の流通を考えましょうということです。現状は、不特定多数の生産者から集めて消費者に分配される市場の仕組みになっていますが、それとは別のところで農家さんと消費者を直接に線と線でつないでいきたいんです。そのうち、消費者にも生産の現場に足を運んでいただき「いつの間にか野菜作り、やっちゃっていました」というような状況を作れたらとも思います。そうやって農という舞台で、野菜などを作ったりすることで、生活に奥行きが出て、充実した暮らしにつながればいいなと考えています。今、自分が作ったものを食べるということは、なによりもぜいたくなことです。友達とご飯を食べに行くとしても、家で一人でご飯を食べるとしても、「食」は毎日繰り返される行為。そう考えれば、食、つまり暮らしと農は切り離せないことです。 |
−− |
どんなふうに商品を販売されているのですか。 |
小島 |
はい、うちでは生産物の価格は、農家さん自身に決めてもらっています。一般の流通システムでは、昨年は米一俵1万2000円だったものが今年は9000円になりました、と突然言われてしまいますが、それでは計画的な農業を続ける仕組みとして難しいのではないでしょうか? そのため国の保障などもあるわけですが、そういう状態では、産業として強くはなれません。だからうちで販売するものは、農家さんが価格を決め、注文を受け、発送してもらうのです。そこで、農の現場と消費者の距離が縮まって、この商品はこんなふうに作られているのか、とか消費者はこんなものを求めているのか、といった意思の疎通が図れるのです。農家さんと一緒に商品企画をしたりしますが、結局は農家さんがいつも良い物を作ってくれているから、私達の会社もやっていかれるわけで、農家さんには本当に頭が上がらないんです。 |
−− |
3銘柄ということですか!? |
小島 |
まず作っている人が少ないですし、小麦「粉」で出す場合は、製粉所もすべて有機認証を取らなければいけないんです。つまり小麦を有機認定ではない工場に持ち込んだ時点で「有機小麦粉」ではなくなってしまいます。だから大々的に作るのは、とても大変なことなんです。 |
−− |
それでは、非常に貴重な商品を扱っているということですね。 |
小島 |
まだ学生のころに、とある農家さんに「将来、熊本で農業をするために、熊本の農家直送のネットショップから始めます」と頭を下げてお願いしたら、「月に10個なら出してあげよう」と言っていただいて(笑)。それが始まりでした。その後、信頼関係が出来て扱える量も増えたのですが。 |
−− |
きっと小島さんの熱意やパワーを感じてくれたからなのでしょうね。 |
小島 |
そうかもしれません(笑)。この前お会いした農家さんからは「絶対、5年持たないと思っていた」と言われました。そうしたら、5年経っても今の仕事を続けているので「ちゃんとがんばってるね」と(笑)。やっと農家さんとの信頼関係が築けたように感じます。 |
−− |
熊本にある農場で作っているものも販売されていますね。ここではご自身が生産に深く携わっていると思いますが、この畑作りのこだわりはどんなところにありますか。 |
小島 |
|
−− |
販売されている商品の中には、有機に認証されているものもありますが、取得は簡単ではないと伺っています。 |
小島 |
大変ですね。熊本の私達の農場では認証を取っていませんが、農薬、化学肥料は使っていません。本来は有機認証って不要な制度だと思うんです。けれども今は、農家さんと消費者の距離があまりにも遠いから、それが信頼の代わりになっているのだと思います。 |
−− |
食の安全が注目されてきていて、小島さんがやっている事に対していろいろな事が追い風になっていると思うのですが、何か感じられますか? |
小島 |
ぜいたくの形が、高価なものを買うといったことから、自分で作ったものを自分で食べる、もっと言えば衣食住を自分の手元に取り戻すというような流れにシフトしてきているのかなと思います。今回、震災を経験したこともあって、皆さん、生活の基盤というものを考え直しているのかもしれません。今、市民農園の需要が非常に高くて供給不足になっているという事実は、皆さんのそういう気持ちの表れかもしれません。食の安全に対する関心も非常に高まっていますが、私は、農家さんと消費者の距離が縮まれば、大量生産という形ではなく、こだわりの農業が職業として成り立つ仕組みが出来ると信じています。そうすることで、農業を生業として、100年後も200後も300年後も、持続出来る仕組みを作りたいと思っています。 |
小島希世子(おじま・きよこ)
熊本県生まれ。えと菜園代表。農家に囲まれた家で育った原体験から農業を志す。慶應義塾大学卒業。野菜の産地直送の会社に勤務後、2009年、農薬を極力利用しない農家のネットワーク、新しく農業に従事したい人々のための参入支援・促進、そして独自販路の開拓を主な業務内容とする株式会社えと菜園を設立。横浜ビジネスグランプリ2011ソーシャル部門 最優秀賞受賞。趣味は、畑作業。3歳児の母。
●取材後記
体験農園のお客様が見えて、小島さんは細かいアドバイスをされていた。いわく、苗をしばるヒモは麻の方が切れなくて良いとか、きゅうりが曲がるのは有機栽培をしているから、というのは大きな誤解、などなど。農業をすることが楽しくて仕方がないという小島さんは、こだわって作った農作物を販売し農家も消費者も満足の行く仕組みを完成させたら、ご自身は、熊本に戻って農業に専念したいのだとか。食を自分の手の中に取り戻すことが、暮らしを豊かにすることという小島さんの言葉が印象的だ。
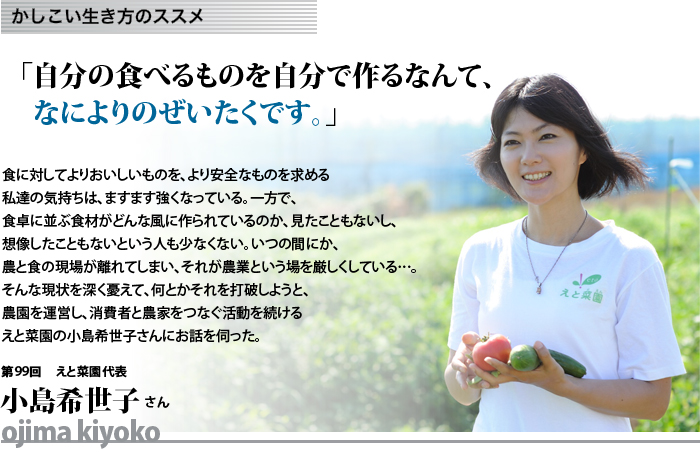
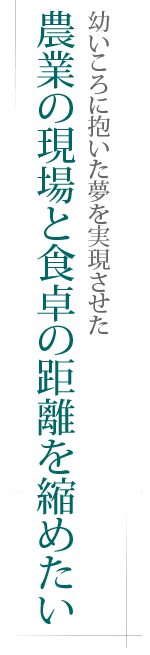
 確かにそうなのですが、まだ充分ではありません。どうも距離感があるのです。そこでもっとお客さんに農のことを伝えるために近づいてきてもらおうと始めたのが、家庭菜園塾なんです。農地を借りて家庭菜園をやりたいと思っている方がいる一方、農家の方は本業で手一杯ですから、間に立っていろいろな技術を提供するサービスを始めました。
確かにそうなのですが、まだ充分ではありません。どうも距離感があるのです。そこでもっとお客さんに農のことを伝えるために近づいてきてもらおうと始めたのが、家庭菜園塾なんです。農地を借りて家庭菜園をやりたいと思っている方がいる一方、農家の方は本業で手一杯ですから、間に立っていろいろな技術を提供するサービスを始めました。
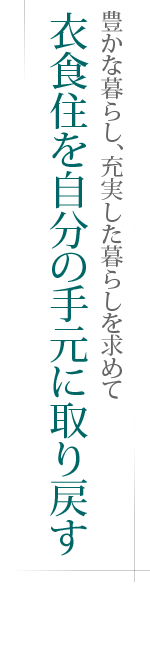
 農薬や化学肥料は使わないのはもちろん、有機肥料も極力使わず栽培しています。その他、雑草は抜かずに、「刈って、畑に敷く」というやり方で栽培しています。森や田舎の土手には、雑草が生い茂っているにもかかわらず、抜群に美味しい山菜や木イチゴがなったりしますよね。それなら畑でも「一反あたり○○kg採ってやろう!」という欲を出さず、森や田舎の土手の土の状態に畑をもっていけば、自然や雑草と共存する形で、野菜を育てる事が出来るのじゃないかなと考えていました。そんな時に『新ぐうたら農法のすすめー省エネ有機農業実践論』という本に出会って、農法も勉強しました。その本によれば、草を刈らずに「刈って敷く」、つまり雑草は土に還してあげる。すると雑草の根の周りに住む土壌微生物の活動が活発になり、更に微生物などの死骸や排泄物が栄養となって土の状態が良くなり、森の状態に近づくのだというのです。そこで、今はそのやり方を実践しています。健康な土には、一つまみあたり、1億個の土壌微生物が生息しているとも言います。私達も「土の中の生き物達」と「野菜の味の向上」の関係性に着目した農業に取り組んでいます。
農薬や化学肥料は使わないのはもちろん、有機肥料も極力使わず栽培しています。その他、雑草は抜かずに、「刈って、畑に敷く」というやり方で栽培しています。森や田舎の土手には、雑草が生い茂っているにもかかわらず、抜群に美味しい山菜や木イチゴがなったりしますよね。それなら畑でも「一反あたり○○kg採ってやろう!」という欲を出さず、森や田舎の土手の土の状態に畑をもっていけば、自然や雑草と共存する形で、野菜を育てる事が出来るのじゃないかなと考えていました。そんな時に『新ぐうたら農法のすすめー省エネ有機農業実践論』という本に出会って、農法も勉強しました。その本によれば、草を刈らずに「刈って敷く」、つまり雑草は土に還してあげる。すると雑草の根の周りに住む土壌微生物の活動が活発になり、更に微生物などの死骸や排泄物が栄養となって土の状態が良くなり、森の状態に近づくのだというのです。そこで、今はそのやり方を実践しています。健康な土には、一つまみあたり、1億個の土壌微生物が生息しているとも言います。私達も「土の中の生き物達」と「野菜の味の向上」の関係性に着目した農業に取り組んでいます。