「オフィス空間を考えることは、ビジネスを最適化することなんです。」
「オフィスワーカーである」という読者は多いと思う。
「忙しくて今日も残業だった」という読者も。さらには
「もっと効率良く仕事をしたいなぁ」と考えている読者も。
では、そのためにどんなことができるだろうか。時間の管理?
情報の流れを良くする? それらがオフィスという空間の
あり方によって変わるとしたら?
長くオフィスの設計に携わり、働く場所=ワークプレイスの研究を
続ける岸本章弘さんに、オフィスという空間の可能性について伺った。
−− |
オフィスというと島型にデスクを並べて向かい合って座るといった空間を思い浮かべます。 |
岸本 |
「対向島型」と呼ばれる形で日本では主流ですね。これと窓際の役職者の「ひな壇」席の組合せは、ピラミッド型の組織図をそのまま空間に変換したようなレイアウトですが、オフィスワークというものが生まれた時には、そのスタイルにも意味があったでしょう。しかしコンピューターとネットワークが普及したことで働き方がすっかり変わった今、空間はまったく追いつかなくなっていると言えます。 |
−− |
働き方と空間が合っていないということですか。 |
岸本 |
ええ。「行動と空間のミスマッチ」が起きているんです。「オフィスの様子を想像してみて下さい」と言われて、まず思い浮かべるのは皆がデスクに向かって仕事をしている様子だと思います。では、実際に昼間のオフィスを見て下さい。営業以外の部署でも、空席がものすごく多いですよね。皆どこに行っているのかというと、打ち合わせコーナーや会議室にいるんです。オフィスを新しくするために社員にアンケートを取ると、不満項目の上位にはいつも「会議室が取りにくい」という声が挙がってくることからも分かるように、つまり、デスクワークは今、確実に減っているのです。 |
−− |
とすると、知的創造に必要なオフィスというのは? |
岸本 |
|
−− |
そして個人の机がなくなることで、会議や打ち合わせのスペースを確保することもできるようになるわけですね。 |
岸本 |
そうです。僕は、デスクワークからテーブルワークへという言い方をしていますが、自席じゃないところ、例えば会議室での討議など、デスクスペース以外のところで活動する比率がどんどん高まっているのに、空間の比率は以前のまま。とはいっても、オフィス全体のスペースは限られていますから、そう簡単に会議室を増やすわけにはいきません。だから、個人スペースと共有スペースの境界を少しずつずらしていったり、転換したりしようとするのですが、そうすると一人に一つ割り当てていたデスクスペースが足りなくなってしまいます。その解決法の一つがフリーアドレス化して共有することです。もちろん導入するには、ネットワークにどこからでも接続できるとか、固定電話や紙の資料といった、人をデスクに縛り付けていたものから解放する環境を整えなくてはなりませんが。 |
−− |
では、コミュニケーションの変化に対しては、空間作りによってどんなサポートがあるのでしょう? |
岸本 |
コミュニケーションと一口に言ってもいくつか種類がありますが、ITの普及によって、リアルな場を共有していることで自然と伝わっていた情報、いわゆる「暗黙知」的な情報のやり取りが減ってきました。例えば、昔は、部下が電話で謝っているのを聞いて「今、トラブってるな」と分かりましたよね。僕が若い時、まだトレーシングペーパーに手書きで図面を書いてオフィスの設計をしていた時代でしたが、ある日、出先から戻ってきたら、その図面の上に先輩の文字で「ドラマがない!」と書かれたメモが貼ってあったことがありました。 |
−− |
良い先輩ですね(笑) |
岸本 |
ええ(笑)。思考過程を提示することを、「ディスプレイド・シンキング」と言いますが、昔のオフィスでは、その人の机の上を見れば「今、こんな事をやっているんだ」と何気なく分かりましたし、その人自身の情報も伝わるので、そこからコミュニケーションが生まれやすかったのです。でも今はデジタル化によって、そういう情報が見えにくくなってきました。こんな風に相手の情報は入ってこない一方で、英知を集めてやるべき仕事は増えているわけです。だからこそ以前よりも、互いの能力や過去の経験を知ることに、時間を使わなければいけなくなっているのです。必然的に、ミーティングのための空間も必要になってくるのです。 |
−− |
そんな風にどんどん複雑になっている仕事の「効率を良くする」ために、空間によって何ができるか、ということでしょうか。 |
岸本 |
その前に「オフィスのような効率や機能一辺倒の空間は嫌だ」という声をよく耳にしますが、ということは多くの人が、オフィスとはそういうものだと思っているということですよね。では、オフィスの効率って何でしょうか? |
−− |
いつか自分もあそこに座るぞ、という(笑)。 |
岸本 |
でも対向島型から独立した、窓際の一番良い場所に役職者のデスクが置いてあって、本人はそこにいないことが多い。それはどう考えても機能的でも効率的でもありません。合理的というのは、この仕事にはこんなスペースが必要だと論理的に考えることでしょう。例えば在席時間が長い人は人間工学的にも疲れにくい良い椅子を与えるとか、先の部長のように在席率が短い人は出入り口に近い席にするとか。 |
−− |
出入り口に? |
岸本 |
そのほうがずっと効率的です。席にいる時間が短いからこそ、在席している時はいろいろな人と接触を持ったほうが良いし、部下が出入りするのも必ず見えます。部下が着席する前に声を掛ければ彼の邪魔をしなくて済みます。 |
−− |
――なるほど、一方ですべての席を統一して均質なレイアウトにするユニバーサルプランが機能的だと言われますが? |
岸本 |
組織変更があっても物理環境を変える必要が無く、効率が良いからです。でもそれはオフィスを管理する人にとっての機能や効率であって、そこで実際に仕事をする人にとっての機能や効率ではないわけです。しかも、全員が同じ仕事の仕方をしている時代ならともかく、やっている事が違えば、オフィス、つまり仕事場に求めるニーズが違うのは当然です。ですから、それに合わせて資源を有効配分するほうが、合理的ではありませんか? つまり最大公約数的に考えるのではなく、個々に最適化できる仕組みを考える。そもそも、オフィスに優先すべきなのは、仕事のための効率と機能であって、オフィスを管理するための効率や機能じゃありませんよね。 |
−− |
「部下を管理できない」という声も出そうですが。 |
岸本 |
よく聞きます。でも、それは、多分違うんでしょう。なぜってそう言っている上司の方が、会議だの何だのでいつもオフィスにいないじゃないですか(笑)。それにツールが発展した今、見えない部下を管理する方法というのは、いくらでもありますし、そもそもITがない時代から、外出の多い営業部問などでは、朝礼をやったり日報を書いたりするなどして、それなりの管理方法が実践されてきました。 |
−− |
でも「部下がさぼるのでは?」という懸念も分かる気がします…。 |
岸本 |
会社員時代に、社員を被験者にして在宅勤務の実験をしたことがあるのですが、その時、自分たちにも思い込みがあったなと実感しました。いくつかの項目に対して、実験前後でどう変化するかアンケートを取ったところ、大部分の人が、始める前は部下同士あるいは部下と上司のコミュニケーションはマイナスになると予測していたのに、結果はプラスに転じていたのです。あるマネージャーは「自分は同じフロアにいる部下が見えていると思っていたけれど、よく考えたら自分自身が席をはずしていることが多いのに気付いた」と言っていました。 |
−− |
オフィスのあり方を考えると、自分の仕事の仕方についても考えざるを得なくなりそうですね。 |
−− |
先ほどのお話にもありましたが「コミュニケーションを増やしたい」という相談を受けることは多いですか。 |
岸本 |
ええ。その時は「それはどんなコミュニケーションですか」と尋ねます。日常的なコミュニケーションなのか、仕事に必要な情報そのものが共有されていないのか――いろいろなレベルのコミュニケーションがありますが、行動の問題と課題を特定すれば、ちょっとした事で改善レベルがぐっと上がるものなのか、長く時間をかけるべきものなのかが分かりますよね。 |
−− |
え!オフィスにですか! |
岸本 |
|
−− |
空間の設計ばかりがオフィスのあり方ではないようですね。 |
岸本 |
オフィスの課題には、大別すると、行動、空間、ツール、サービスという4つがあります。今はツールの問題が多く取り上げられますが、だからといって、そこから課題に取り組むのは間違いです。そもそもオフィスの課題というのは行動の課題なのです。自分たちがどういう組織になりたいのか、どういう働き方をしたいのか、つまりどういう行動をしたいのかを考えた上で、それに見合った最適な空間を作るべきです。「これが良いオフィス」という一般解はありません。「あなたに最も合っている」のが、良いオフィスなんです。更に同じ会社でも、起業間もない時期か、成熟期かといったフェーズによって求められる行動のパターンは変わりますから、良いオフィスというのは、まさに百社百様であり、且つ変化するものです。 |
−− |
なるほど、理にかなっています。 |
岸本 |
次に移転した際にもまた、オフィスの作り方を変えました。会社の次の戦略としてグローバル化を掲げ、そこでは完全なフリーアドレスを変更して、グループごとに、マネージャーに部下の配置を決めさせたんです。世界に広がっていくには、マネジメント人材の育成は必須です。だから、自分のチームを自らの裁量で運営し部下を育成する権限と責任をマネージャーに与えたわけです。また全体を4、5人ほどの小さな単位に分けて、通路を縦横無尽に走らせるレイアウトを採用しました。全員のデスクの片側が通路に面している格好になるので、通路に立てば席の人とその場で打ち合わせができます。即、コミュニケーションがとれることを重要視した結果、そういうオフィス空間となったわけです。 |
−− |
つい誤解しがちですが、効率を良くして発展させるべきは、仕事の中味ですね。 |
岸本 |
ええ。こうしてでき上がったオフィス空間は、そこで働く人にとって非常に合理的なのものになりました。自分たちがどんな会社なのか、どんな戦略を持っているのか、これからどうなりたいのか、そのためにはどういう行動を身に付けなければいけないのかを想定して、その他のシステム同様に、オフィス作りにおいても、その実現に向けて会社が最大限に支援しているのです。だから「会議室が取れなくて、ミーティングが1週間先になり、意思決定が先延ばしになりました」なんていう言い訳は、一切成り立ちません。でもこれ、とても合理的な考え方だと思います。 |
−− |
外に出ることが増えたと言っても、オフィスワーカーにとって過ごす時間の長さは相当なものです。となると無頓着ではいられないような…。 |
岸本 |
家を建てることを考えてみて下さい。そこに住む家族やライフサイクル、ライフスタイルなど、いろいろなことを考えますよね。それに対して、オフィスに関しては、考えなさ過ぎだとは思いませんか?しかも、そこに居るのは、一人じゃないでしょう? |
−− |
逆に言えば、一人じゃないから最大公約数で考えてしまっていたという面があるかもしれません。 |
岸本 |
皆、それで仕方がないと思ってしまっていたわけです。車一台買う時だって、スペックをいろいろチェックするのに、オフィスに関しては、その何十倍ものコストをかけているのに、自分たちに合っているかどうか、チェックしていないのじゃないかと感じます。 |
−− |
ええ。まず、オフィスのコスト削減と言う言葉が出てきたり…。 |
岸本 |
これまでオフィスは「コストセンター」と呼ばれて、できるだけ経費を削減しなければいけないと思われてきました。でも、それは違います。オフィスは知的労働の場であり、そこで考え出したアイデアが企業のビジネスを左右するのです。つまりプロフィットセンターなんです。そしてそれを生み出すのは、空間ではなく人。その「人」からどれだけのものを引き出すか、その行動やメンタリティを支える仕組みを作っていかないといけないわけです。よく、オフィスが与える効果は「定量化できない、計れない」と言われますが、そうではなく「計り知れない」のです。まさにいい組み合わせにした瞬間、人のやる気を引き出したり、組織の文化を育てたりできる。直接的ではなく、間接的に――言ってみれば漢方薬的に、じわりじわりと、オフィス空間が影響を及ぼしている事は間違いありません。つまり、オフィス空間を考える事は、ビジネス支援でもあるんです。だからこそ、最高、最新、最大ではなくて、最適な空間を作ることが重要なんです。組織の条件やビジネスの戦略が違えば、あっちで通用したものが、こっちで通用するとは限らない。自分たちのビジネスに合ったオフィス作りが大切なんです。 |
岸本章弘(きしもと・あきひろ)
1958年兵庫県生まれ。京都工芸繊維大学大学院修士課程修了。コクヨ株式会社にてオフィス等のプランニングやインテリアデザイン、先進オフィスの動向調査、次世代ワークプレイスのコンセプト開発およびプロトタイプデザイン等に携わるかたわら、同社発行のオフィス研究情報誌『ECIFFO(エシーフォ)』編集長をつとめる。2007年独立し、ワークスケープ・ラボ設立。ワークプレイスの研究とデザインの分野でコンサルティング活動を行う。千葉工業大学、京都工芸繊維大学非常勤講師等を歴任。
●取材後記
対向島型のオフィスに慣れたオフィスワーカーにとって「明日からフリーアドレス!」と言われたら戸惑うかもしれない。それに対して「とりあえず新入社員に机を与えなければいいと冗談交じりに言っている」そうだ。新入社員は、ついこの間まで学生。その時は講義毎に移動する、正にフリーアドレスだったはずだからだ。なるほど、ということは多くの人がフリーアドレスを経験していることになりそうだ。どうしたいか、どうありたいか、それによって空間のあり方が決まるのは、確かに住宅でもオフィスでも同じこと。オフィスの空間にももっと関心を持つべきだ。
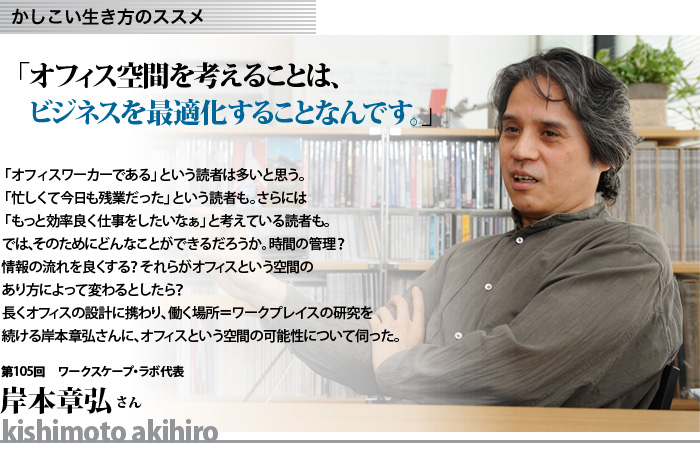
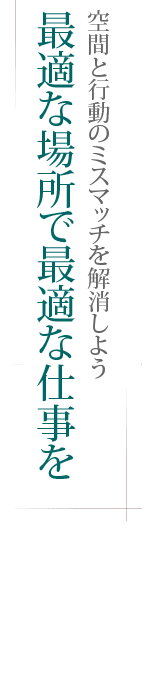
 例えば、個人の席を決めないで、その日の仕事の内容に応じて席を選ぶ「フリーアドレス」というオフィスのスタイルがあります。自席というものがなく、集中してアイデアをまとめるといった作業、会議やブレストといったミーティング、それにリフレッシュや情報交換といった、オフィスでの行動に応じてそれぞれクワイエットエリア、ライブエリア、コモンスペースと空間が分かれています。
例えば、個人の席を決めないで、その日の仕事の内容に応じて席を選ぶ「フリーアドレス」というオフィスのスタイルがあります。自席というものがなく、集中してアイデアをまとめるといった作業、会議やブレストといったミーティング、それにリフレッシュや情報交換といった、オフィスでの行動に応じてそれぞれクワイエットエリア、ライブエリア、コモンスペースと空間が分かれています。
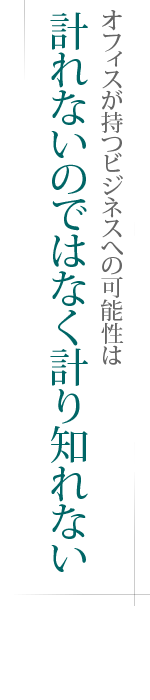
 ええ。さすがにオフィスの規模が大きい例ですが、一番手軽なのは飲食でしょうね。単にスナックコーナーを設けるだけでなく、ちょっとしたイベントにも工夫して、例えば、毎週木曜日の朝は食堂でベーグルを振る舞うという会社、アイスクリームデーを設けている会社もあったりもします。3時には長い列ができて、振り向いたら、後ろに社長が並んでいたりするそうですよ。
ええ。さすがにオフィスの規模が大きい例ですが、一番手軽なのは飲食でしょうね。単にスナックコーナーを設けるだけでなく、ちょっとしたイベントにも工夫して、例えば、毎週木曜日の朝は食堂でベーグルを振る舞うという会社、アイスクリームデーを設けている会社もあったりもします。3時には長い列ができて、振り向いたら、後ろに社長が並んでいたりするそうですよ。