「意識する、しないにかかわらず、自然に触れるとストレスが減るのです。」
新緑が美しい季節、木々の下を歩くと清々しい気持ちになる。
仕事の合間にふと窓の外を見るだけでも、心が和むものだ。
そんな経験から多くの人が自然に触れると安らぐという感覚を
持っているだろう。そうした感覚を科学的に解明し、健康に
役立てようと研究しているのが、今回、登場いただく
宮崎良文さんだ。身近にある自然に対して、私達の体は
どのように反応し、どのような影響を受けているのだろう?
―― |
自然に触れることで健康になると、簡単に言えば、そういうことでしょうか。 |
宮崎 |
「自然セラピー」と呼んでいるのですが、我々が提唱しているのは、病気にならない体を作るという予防医学です。「自然療法」という言い方と混同されることがあり、あたかも森に行けば病気が治るように思われる方もおられるかもしれませんが、そうではありません。人間はストレス状態に陥ると、免疫機能が落ちます。そうした時に、自然に触れることで人はリラックスし、同時に免疫機能が回復する――つまり病気になりにくくなる。それが自然セラピーの予防医学的効果です。 |
―― |
なるほど。病気にさせないと。 |
宮崎 |
そうです。私が中学や高校のころは、「保健休養機能」という言葉が使われていましたが、2004年に、森が持つ機能、今で言えば、癒し効果が注目されて、林野庁など産官学が連携した「森林セラピー(R)研究会」を発足させました。森林セラピー(R)では、森林浴を行うと免疫力が高まるなどの効用をうたっていますが、私はさらに、机の上の花といったごく小さなものでも効果があるという広い範囲の自然を含む「自然セラピー」を研究しています。 |
―― |
確かに新緑の季節は空気が清々しくて気持ちよいものです。 |
宮崎 |
|
―― |
今の私達の暮らしは、遺伝子から見ると、ちょっと都合が悪い、と。 |
宮崎 |
人の自律神経活動というのは、ストレス時に交感神経活動が高まり、リラックスした時は副交感神経活動が高まるようになっています。体温も血圧も、活動期に上がって、寝る前には下がるんです。そしてその振幅には上下とも限度があるのですが、現代社会では、交感神経活動が常に高すぎる状態にあると思うのです。ベースライン、つまり普段の状態が高すぎるので、上限までの幅が狭いわけです。ところが、そうした時に自然に触れると、一過性ではありますが、ベースラインが下がるという現象が見られます。 |
―― |
森の中を歩いている時と、街中を歩いている時の、人の生理的変化を記録した膨大な実験データがありますね。 |
宮崎 |
2005年からの7年間、48ヶ所で森林浴の実験を行い、576人のデータを集めました。人のリラックス状態を測る指標として血圧、心拍数、心拍の揺らぎ計測による交感・副交感神経活動、それに、ストレスに敏感に反応して分泌量が増える、俗にストレスホルモンと言われているコルチゾールの唾液中濃度について、森の中と街の中で、歩いている時、座って風景を見ている時それぞれの状態を計測しました。どの結果も自然に触れることによって、体がリラックスするという結果でした。近赤外光を使った脳前頭前野(額の部分)の計測においても、森の中では鎮静化していました。 |
―― |
それが、データにはっきりと表れるのですか。 |
宮崎 |
2005年度から2008年度にかけて全国35ヶ所で行った生理実験の結果では、コルチゾールが森の中では街の中に比べて平均12.4%下がりました。脈拍数は5.8%、最高血圧は1.4%下がるという結果が出ています。 |
―― |
森の中のようなところにいなくても、自然を感じるものがあればリラックスできると? |
宮崎 |
その検証です。室内実験は、温度や湿度、照度などをコントロールした人工気候室で行いました。被験者には、都市と森林の映像を見てもらったり、木の匂いをかいでもらったり、小川のせせらぎ音を聞いてもらうわけですが、室内実験の利点は、そうした要素を一つずつ検証できることです。更に屋外では使えない機器を使うこともできます。 |
―― |
そこでやはり、想定していた結果が出ましたか。 |
宮崎 |
ええ。机の上の花のような小さな自然であっても、匂いでも音でも、映像でも、一つの刺激で多くの人にリラックス反応が出ました。 |
―― |
失礼ですが、実験中の様子を見る限り、かなり殺風景で机も事務用。そこにあるこのバラだけで、そんなに気分が変わるものなのですね。 |
宮崎 |
そうです。先に言った木の匂い、自然の映像、小川のせせらぎ音、どれも同様の結果だったのですが、ただ面白いこともありました。小川のせせらぎ音を流した実験では、その音を聞いた時の脳の活動を調べたのですが、多くの人が前頭前野の活動が下がって脳が鎮静化して血圧も下がり、全体にリラックスした方向に向かうという傾向を示したのですが、一方、被験者の中に、数値が全く変化しない学生がいたんです。その学生に、実験後に何を思っていたのかと聞いたら、彼は、その音からトイレの流水音を思い出してしまったと言うんです。これには驚きましたが(笑)、同じ音でも、個人の嗜好や背景がリラックスに影響しているということです。匂いも、好きな香りと嫌いな香りは、個々人で大きな違いがありますよね? ここには、人によって差があることが見えてきます。 |
―― |
音や香りに好き嫌いがあることは、私達も経験的に知っていますが、データからも個人差があることが分かってきたのでしょうか。 |
宮崎 |
ええ。快適性には、消極的快適性と積極的快適性とがあって、温度や湿度などが適切で「不快ではない」というのが、消極的快適性です。以前は、快適であることを考える時に中心の課題となるのは、この消極的快適性でした。しかし今、少なくとも日本で求められている快適性は、積極的快適性です。つまるところ、+αの部分の快適性が求められているわけです。そしてこの+αの部分が、個人差につながる――私は、この個人差が、これから重要なテーマになっていくと考えています。極論すれば、好きか嫌いかですが、そもそも、自分の主観と体の反応は異なることもありますし、実は、私達は、自分の体を分かっているようで分かっていないし、分かっても正確に表現することも難しいのです。 |
―― |
「快適」という言葉ひとつにしても、その言葉の定義は人それぞれで、言葉で今の状態を説明しようとしても、そこで既にフィルターが入ってしまいますね。 |
宮崎 |
そうなんです。言葉では表現できない、感性なのです。これまで感性というものに科学的なアプローチはなされていませんが、それを言葉で表現できなくとも、測定機器の進歩によって生理的に測ることができるようになりました。感性と個人差、これもこれからの私の研究テーマですね。 |
―― |
個人差があるということになると、自然に触れた時に上手にリラックスする方法を、各々で見つけなくてはならないとか? |
宮崎 |
いやいや(笑)。無理をする必要はありません。その人が好きな自然があるはずです。人類学の根本の考え方ですが、人にはもともと遺伝子型というものがあります。それに対して、後天的に文化や環境によって修飾がなされます。その結果を表現型と呼びます。遺伝子型には、実は2種類あって、一つは両親から受け継いだ遺伝子。これは一卵性双生児以外、全員違います。それからもう一つ、私は、人として持っている自然対応遺伝子みたいなものがあると仮定しています。世界のどこにいようとも、人間が自然の中にいたことには変わりないのですから、人間が自然に触れて快適を感じるというのは世界共通だと考えていいでしょう。ですが、両親から受け継いだ遺伝子型に後天的な経験等が影響を与えて生み出された表現型が、人それぞれ違うからこそ、小川のせせらぎ音を聞いて、トイレの流水音を思い浮かべる人もあれば、リラックスする人もいるのです。 |
―― |
それは意外な結果ですね! イヤだと思っているのに、ですよね? |
宮崎 |
そうなんです(笑)。生理応答と主観評価が、必ずしも合致しないこともあります。いくつか実験をしていますが、結果は皆同じです。これまでの実験結果から言うと、快適だと感じて生理的な数値も比例して変化する場合が8割方ですが、2割位は、主観的には気付いていないけれども、生理的には変化している場合もあるのです。もっと言えば、主観的には差がないと思われることでも、生理的には有意差があることもあるのです。 |
―― |
こちらは、自分では感じていないつもりでも、体は反応しているというわけですか! |
宮崎 |
|
―― |
それによって、どのようなことが見えるのでしょう? |
宮崎 |
例えば森の中を歩く前と後でコルチゾール濃度を測定すると、通常、歩いた後は下がります。ところが中には、増える人がいる。確かに平均的に見れば下がっているし、私のように性格的に激しくて、いつもイライラしているような人間はいっそう、高かったコルチゾール濃度が下がるのです(笑)。では変化しないのはどういう人かというと、状態が良い人なのです。そういう人は、コルチゾール濃度が変化しないか、逆に上がることがあります。脈拍でも同じことがあります。それをこれまでは、単にばらつきと言ってきたわけですが、その人の絶対値が測れるようになったことで、ばらつきを説明できるようになったのです。 |
―― |
ばらつきそのものに意味があるわけですね。 |
宮崎 |
ええ。それにそういうばらつきに別の要素を加えることで、ばらつきではなくなるということもあります。
自然のものではありませんが、チョコレートの味覚実験では、脳前頭前野の活動が活発になる人と逆に鎮静化する人がいて、結論を導き出せなかったのですが、そこに個々人の性格というファクターを当ててみると、一定の規則性が見えたのです。 |
宮崎良文(みやざき・よしふみ)
1954年兵庫県生まれ。千葉大学環境健康フィールド科学センター教授。東京農工大学修士課程(環境保護学)修了。医学博士。東京医科歯科大学医学部助手、独立行政法人森林総合研究所生理活性チーム長を経て、現職。2000年「木材と森林浴の快適性増進効果の解明」に対して、農林水産大臣賞、2006年日本生理人類学会賞を受賞。著書に『森林浴はなぜ体にいいか』(文藝春秋)、『木と森の快適さを科学する』(林業改良普及双書)、『森林医学 II』(編集・朝倉書店)他。
●取材後記
確かに煮詰まった時に「外の空気を吸いに行こう」と思うことがある。それが迷信でも思い込みでもなく、体の中で本当に効果的な反応がありますよ、と言われると説得力も増そうというもの。加えて、自分が知らないうちに生理的に反応していることもあるというから、驚いてしまう。机に花を飾るのに実際的な意味があるとは、知らなかった。明日は花を買ってこよう。
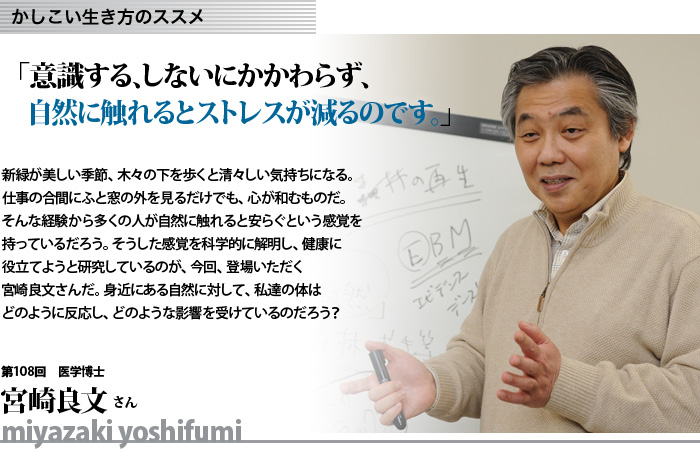
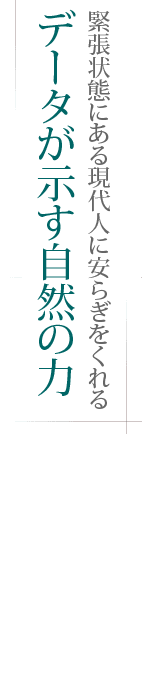
 ヒトが「人」になって500万年と言われています。これには諸説ありますが、紛れもない事実は、我々人間は長く自然の中にいた、ということです。では、現代のような人工的な生活がいつ始まったかといえば、ひとつの節目は産業革命でしょう。今から200〜300年前ですから、人間の500万年の時間の中ではほんのわずかな期間なのです。進化という過程において遺伝子も変化するのですが、わずか200〜300年の間では遺伝子は変化することはできません。つまり、我々の体は自然の中で暮らしていた時と変わらない、自然の中で暮らすことに対応した体であって、にもかかわらず、現在、我々は人工環境下に生きている、それ故に気が付かないけれど、実はストレス状態にある――というのが、私の仮説です。さらに言えば「テクノストレス」という言葉が出てきたのが1984年、「森林浴」という言葉は1982年。くしくも非常に近い時期に作られていることから考えると、そのころ急速に第二の人工化が起き始めた、だからこそ、今、皆が、反作用的に「自然」というものに注目しているのじゃないかと感じますね。
ヒトが「人」になって500万年と言われています。これには諸説ありますが、紛れもない事実は、我々人間は長く自然の中にいた、ということです。では、現代のような人工的な生活がいつ始まったかといえば、ひとつの節目は産業革命でしょう。今から200〜300年前ですから、人間の500万年の時間の中ではほんのわずかな期間なのです。進化という過程において遺伝子も変化するのですが、わずか200〜300年の間では遺伝子は変化することはできません。つまり、我々の体は自然の中で暮らしていた時と変わらない、自然の中で暮らすことに対応した体であって、にもかかわらず、現在、我々は人工環境下に生きている、それ故に気が付かないけれど、実はストレス状態にある――というのが、私の仮説です。さらに言えば「テクノストレス」という言葉が出てきたのが1984年、「森林浴」という言葉は1982年。くしくも非常に近い時期に作られていることから考えると、そのころ急速に第二の人工化が起き始めた、だからこそ、今、皆が、反作用的に「自然」というものに注目しているのじゃないかと感じますね。
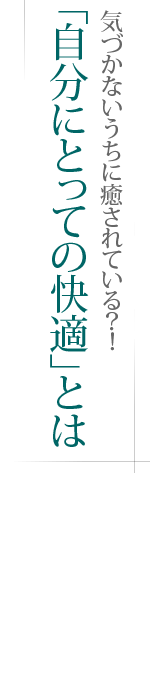
 普通の刺激――例えば視覚刺激などは、いくつかの経路を経て、大脳辺縁系や前頭前野に入力されるのですが、匂いは、いきなり大脳辺縁系に刺激が入力されます。だから匂いは、他の刺激に比べて、感情変化が大きいことが知られていますね。
普通の刺激――例えば視覚刺激などは、いくつかの経路を経て、大脳辺縁系や前頭前野に入力されるのですが、匂いは、いきなり大脳辺縁系に刺激が入力されます。だから匂いは、他の刺激に比べて、感情変化が大きいことが知られていますね。