「人がつながる仕組みを作って問題を解決する、それがコミュニティデザインです。」
コミュニティという言葉がいろいろな場面で使われている。
何かの興味で集まった人たちを指すこともあれば、
同じ場所に暮らす人たちを指すこともあるが、この言葉が
注目されているのは、むしろ「コミュニティ」に異変が起きて
以前とは違うものになっているからかもしれない。
では、今の時代により良く機能するコミュニティとはどのようなものか。
「作らない建築家」とも呼ばれ、「コミュニティデザイン」を生業とする
山崎亮さんにお話をうかがった。
―― |
お話をうかがうにあたって「コミュニティデザイン」とは何なのだろうと思いながら、ご著書を拝読しましたが…分からないな、と(苦笑)。 |
山崎 |
僕も、分からないですね(笑) |
―― |
(笑)。最初に注目されたプロジェクトは、島根県隠岐郡海士(あま)町ですね。町が今後10年間に実施する各種政策をまとめた総合計画の策定に関わられたとのことですが。 |
山崎 |
町長は、せっかく総合計画を作るのであれば、住民や行政職員も参加して、皆で作り上げたいという意向があって、お話をいただきました。海士町は人口2,400人の離島ですが、250人以上の移住者が住み着き、さらにUターンして島へ戻って来る人も多く、町として成功しているかに見えました。しかしそこには課題もあって、その一つが、Iターン者とUターン者、そして地元継続居住者との間で、あまりコミュニケーションがとれていないということでした。ですから、総合計画を作ることだけでなく、その後のまちづくりの担い手となるチームを生み出すことも課題だと考えました。そこで、Iターン、Uターン、それに地元継続居住者の混合チームを作るべきだと提案し、計画作りの過程から、三者間にある壁を少しでも低くすることを目指しました。 |
―― |
単純に集まるだけでは、確かにまとまるのは難しそうですね。 |
山崎 |
コミュニティというのは、住んでいる、働いているなど老人会や商店会など、地縁で結ばれているものと「ラーメンが好き」「鉄道が好き」というように同じ興味を持って集まっているものとがあるのですが、人口2,400人といった規模の場所では、NPOのような興味型コミュニティが顕在化しないんです。ですから、海士町では、地縁型のコミュニティの中から、子どもが好きな人たちの集まり、環境に対して意識が高いチームといったように新たな興味型コミュニティを作ることから始めました。そうすることで、一人が地域の自治会と新たに作ったコミュニティ、二つのコミュニティに属することになるわけです。そうやって、もう一層分コミュニティを作る取り組みをしました。 |
―― |
その各チームに、地元継続居住者と、Iターン者、Uターン者、ベテランも若手もいる。そのチームづくりの過程、さらにチームごとの役割分担や、具体的なプロジェクトに結び付けるための仕掛けも作られましたね。 |
山崎 |
ええ。コミュニティを作る時に重要なのは、「何を達成したいか」によってコミュニティの作り方を変えていく必要があるということです。大学の中にコミュニティを作る、行政組織の中にコミュニティを作る、あるいは企業の若手コミュニティを作るといったように、いずれの場合でも、ある課題を乗り越えていくために人と人とがつながって、つまりはコミュニティを作って力を発揮するという点は共通していると思います。言ってみれば、コミュニティデザインとは人のつながりで何かを乗り越えていこうとする行為というのでしょうか(笑)。 |
―― |
「デザイン」というと「=かっこいい物を作る」という捉え方があると思いますが、ここで言うデザインは、違いますね。 |
山崎 |
「デザイン」には、コマーシャルなデザインとソーシャルなそれとがあります。この50年は「こんなかっこいい形ができた」「それが売れた」という、コマーシャルなデザインが注目されがちだったと思いますが、産業革命後、アーツ・アンド・クラフツやバウハウスが目指していたようなデザインは、いずれも課題解決型のソーシャルデザインでしたし、思想家でもあり建築家でもあるバックミンスター・フラーのダイマクション地図や、建築家、ル・コルビュジエのドミノ・システムなども同じです。コルビュジエの著書『建築をめざして』の最終章は「建築か革命か」で結ばれています。「市民は掘っ立て小屋みたいな所に住まわされ、下水道もなく、ペストやコレラが流行すれば何十万人も死んでしまうような世の中でいいのか。政治家はそれに対してソリューションを与えていない。ならば、この平たく並んでいるものを、タテに積み上げて、ピロティを設けガラス張りにして、光と風が通るようにしよう。それによって社会が良くなっていくはずだ」。そうやってコルビュジエは、建築によって課題解決の形を美しく見せたわけです。しかし1960年ごろから、例えばマンションにしても同じ形を記号としてコピーしていくようになり、それによって、デザイナーは経済の仕組みの中に取り込まれ、本来コマーシャルとソーシャルとふたつの側面があったデザインという仕事のうち、コマーシャルの方に寄った仕事をしてきてしまったような気がするんです。だから、半年に1回リニューアルされるようなものを「デザイン」と呼んでいるし、僕らがイメージするデザインというものも、実はすごく限られたこの50年間の先進国だけのデザインであって、つまり地球上の人口の1割の人が使うデザインとも言えます。一方で、社会を見渡せば、至るところに課題があります。 |
―― |
だから悪路をものともしない車椅子をデザインする方もいれば…。 |
山崎 |
そうです、どんな汚れた水でも99.9%ろ過できるフィルターをデザインしている人たちもいるのです。僕は、そうしたソーシャルなデザインが本来のデザインだと 思うのです。 |
―― |
「形」として見えるデザインは、確かに分かりやすいものですからね。 |
山崎 |
|
―― |
数あるデザインの中でも「コミュニティ」にフォーカスされたのは、なぜでしょう? |
山崎 |
たぶん、ランドスケープデザインをやっていたことが大きいと思います。ランドスケープデザインというのは「オープンエア」「誰でも入れる」そして「未来永劫(えいごう)オープンである」という、いわゆるオープンスペース=公共的な空き地をデザインするものです。つまり、誰もが関係する場所であることが前提であるため、その設計を誰か一人の「作品」として作るのはダメなんじゃないかと、1960年代ごろから言われていました。ランドスケープ・アーキクテクトとして著名なローレンス・ハルプリンなども、作家の個性ではなく、将来そこを利用する人たちの意見を聞きながら設計を進めた方がいいと語っています。そのように、ランドスケープデザインの分野では、住民参加でデザインを考える、やらざるを得ないという状況が早くからありました。そして、僕もその端っこにいて(笑)、公園を設計するとなったら、いろいろな人たちに集まってもらってワークショップを開催したり、話し合いをしたりしていました。そういった中で、集った人たち同士は親しくなりますが、僕は設計業務、つまり図面を描くのが仕事ですから、5回程ワークショップをやったら「皆さんありがとうございました。良い図面ができました。これで終わります、さようなら」となってしまうんです。もったいないと思いませんか? 参加してくれた住民には「こんなこともやりたい」という発想があるのに、解散になってしまう。そうではなく、設計が終わった後の工事中も話し合いを続けて、公園がオープンした時には来園者を迎え入れ、さらに一緒に公園を運営していくような仕組みが作れたら、設計のプロセスで作ったコミュニティを、公園のオープン後に生かせるのじゃないかと考えたんです。 |
―― |
それは、具体的にはどんなプロジェクトでしょう? |
山崎 |
兵庫県の「あそびの王国」です。パークマネジメントに関わっていた有馬富士公園の開園後に、園内に子どもの遊び場を設計してほしいと依頼されたものです。 |
―― |
「町を楽しく使いこなす」という視点は新鮮です。ご著書でも、大阪の「公共空間をうまく使いこなしている人を探すワークショップ」はワクワクしました。ご本人は「使いこなしている」とは思っていないでしょうけれど、自然ですね。 |
山崎 |
ええ。3時に銀行が閉まると、その前に折り畳み椅子を持ってきてヤクルトを売り始めるおばちゃんがいます。おばちゃんがそこに座ると、どこからともなく地域の高齢者が集まって来るんです。といっても、ヤクルトを買うわけじゃなくて、おばちゃんとの会話を楽しんでいる。そうやって顔を合わせているから「あの人、今日は来ないな」と気付いたりする。単なる商行為を超えた地域の役割を感じました。その他にも、道端に空気で膨らませたプールを置いておく人がいて、そこに子どもたちがいっぱい遊びに来ていたり、道路の植栽帯を勝手に管理しながら、隙間にシソやネギを植える人もいて、公共空間を自分のもののように使いこなしながら、周囲にプラスの影響を与えている人たちをたくさん発見しましたよ。 |
―― |
あうんの呼吸というかバランスが巧みというか。 |
山崎 |
市民が持っている公共空間の使いこなし方や力というか、公共に貢献する気持ちをうまく引き出しながら、都市のマネジメントができたらなと思いますね。 |
―― |
というと? |
山崎 |
事故があったらいけないからと、手すりをつけたり、段差をなくしたり。それはそれで大切なことですが、そうした、至れり尽くせりの設計をするのではなく、そばに誰かいれば、いいのでは?と思うのです。 |
―― |
人と人の関わりが希薄だと言いつつ、ハードの面では、人同士の結び付きを排除しているということですね。山崎さんのデザインの方向性は、その逆に人と人とが関わり合うというものです。 |
山崎 |
|
―― |
最初は、溝の掃除だったとしても、何かの時には声をかけやすくなりますね。 |
山崎 |
「あの人は力が強いから、これを運ぶのを手伝ってもらえないだろうか」とか「あの人は細かいことが好きだから、これがお願いできるかも」と、互いを分かった上での関係を作っていくことができます。つまり身近な人と共同して、目の前の課題を解決できるということなのです。そうしたコミュニティがない状態では、これからの社会はもたないだろうと思います。 |
―― |
東日本大震災の避難所では、ボランティアが、自分のできることを書いて示す「できますゼッケン」を現地に送られましたね。 |
山崎 |
ゼッケンのプロジェクトは、ある企業との共同だったのですが、避難所にも「政府と個人とがダイレクトに契約しなければいけない社会」と同じ構図があったのです。 |
―― |
これまでで、特に印象が強いプロジェクトを挙げるとしたら? |
山崎 |
海士町でしょうか。海士町に住んでいる人たちの意識の高さにあると思うのですが、「こうなればいいな」と思ったことが、とてもうまく進みましたね。地域の中からチームを生み出し、その人たちが活動を進めていくモデルになった、マイルストーン的な仕事と言えると思います。僕らの仕事の方向性を大別するとしたら、海士町のように新しくコミュニティを生み出していくラインと、既存のNPOやサークルなどのコミュニティが元気にしていくライン、それと「できますゼッケン」のようなソーシャルデザインみたいなラインの3つがあると思います。それらの各要素、要素を組み合わせながら、毎回、課題に合わせてやり方を変えているということなのかなと。 |
―― |
その後、海士町のような例はありますか。 |
山崎 |
そうですね。例えば、立ち上げからちょうど2年になるのですが、東京都の墨田区の食育計画づくりを手伝っていて、ここでも海士町と同じように墨田区民24万人の中から100人位に参加してもらい、つまり興味型コミュニティを作って、その人たちが食育計画を作っていくという動きが始まっています。 |
―― |
24万人と2,300人ではずいぶん、規模が違うように感じます。 |
山崎 |
規模は意外に関係ないようです。今、大阪の天王寺に新しくできる百貨店でも住民参加型のコミュニティデザインを担当しています。百貨店としては、日本一売り場面積が広いビルの中に、和歌山や奈良から来たコミュニティが活動するスペースを作るため、今、50団体ずつワークショップをやっているところです。これは以前お手伝いした鹿児島の商業施設「マルヤガーデンズ」の10倍以上の規模にあたります。ただ、都市部よりも中山間離島地域の方が進歩しているんです。 |
―― |
東京を見ても、新しいものはない、と…。 |
山崎 |
ええ。だから、海士町での経験が墨田区の参考になるとか、鹿児島のマルヤガーデンズでの試みが大阪の天王寺につながるという方向です。我々が、中山間離島地域でやっていることばかり自慢気に話してしまうとすれば、もはや東京や大阪よりもそちらのほうが進んでいることを実感しているからだと思います。そうした地域だからこそ、人々には危機感もあって、柔軟性もあるんです。 |
―― |
都市のプロジェクトは二番煎じ、三番煎じのようですか。 |
山崎 |
そうかもしれません(笑)。ただ、誤解のないように伝えておかなければいけませんが、僕らが参加したから成功したということは、まずありません。僕らができることは、現地に月に1度か2度行って何かやる程度であって、課題の解決に向かうのは、他でもない、そこに住んでいるコミュニティの人たちがやる気になった、立ち上がったからですし、地域で何か面白いことが起きているとすれば、それは地域の人たちが本気になったから。僕らは、地域の人たちだけでは、なかなか話し合いがうまく進まなかったところに、ちょっときっかけを作っただけです。 |
―― |
でも「何だかよく分からない」コミュニティデザイン、仕事として面白いですね。 |
山崎 |
そうですね、やめられないですね(笑)。 |
山崎亮(やまざき・りょう)
1973年愛知県生まれ。92年大阪府立大学農学部入学。メルボルン工科大学環境デザイン学部留学(ランドスケープアーキテクチュア学科)を経て、97年大阪府立大学農学部卒業。99年同大学院農学生命科学研究科修士課程修了。99年株式会社エス・イー・エヌ環境計画室入社。2005年同社退社後、06年に株式会社studio-L設立。京都造形芸術大学芸術学部空間演出デザイン学科教授。主なコミュニティデザインに兵庫県飾磨郡家島町(しかまぐんいえしまちょう)(現姫路市)のまちづくり、兵庫県立有馬富士公園マネジメント、島根県隠岐郡海士町振興総合計画、鹿児島県鹿児島市マルヤガーデンズなど。著書に『コミュニティデザインー人がつながるしくみをつくるー』、共著に『藻谷浩介さん、経済成長がなければ僕たちは幸せになれないのでしょうか?』(共に学芸出版社)、『まちへのラブレター:参加のデザインをめぐる往復書簡』など多数。
●取材後記
「コミュニティを生む」という仕事が「仕事」になるというのも興味深い。しかもコミュニティを生み出す、解決の仕方は、その場に応じて違うし、さらに山崎さんがおっしゃる「コミュニティ」が表すものも、それぞれの場所によって違う。だから「コミュニティデザイン」を一言で説明するのはなかなか難しいけれど、うまくつながれない、気軽に声をかけられない今の私達にとって、とても大切な概念かもしれない。

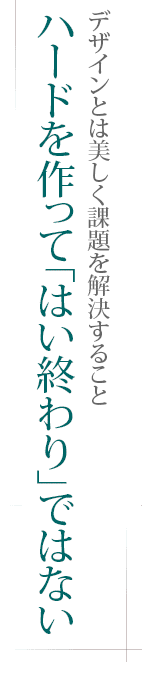
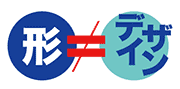 デザインとは、表面に出ている課題ではなくて、課題の本質をつかんで、それを美しく解決していくことだと思います。コンサルティングでも政治でも何でも、そこに美しさがないといけないと思うんです。「美しい」というのは、多くの人たちが「いいね」と共感するもの、というのでしょうか。そう考えれば、物の形でない、美しさ――演劇を観て感動したり、歌を聞いて「いいね」と思うことにも、美しさが入っている。そうやって皆が、ぞくっとするような「いいね」と思うような解決策を提示することができれば、それがデザイン作業なのだと思います。建築デザインも製品デザインも、グラフィックデザインも、美しく目の前の課題を解決していければ、それは「デザイン」ですし、一方で物の形は見えないけれどもファイナンシャルデザイン、キャリアデザインなど、美しくお金の配分や人生設計を作ることも、ある種の美しさを伴う「デザイン」。コミュニティデザインも同じです。人と人の結び付き方の妙であったり、彼ら自身のやる気や共感をぐっと高めていく。それがコミュニティの力を使ったデザインなのだろうと思います。
デザインとは、表面に出ている課題ではなくて、課題の本質をつかんで、それを美しく解決していくことだと思います。コンサルティングでも政治でも何でも、そこに美しさがないといけないと思うんです。「美しい」というのは、多くの人たちが「いいね」と共感するもの、というのでしょうか。そう考えれば、物の形でない、美しさ――演劇を観て感動したり、歌を聞いて「いいね」と思うことにも、美しさが入っている。そうやって皆が、ぞくっとするような「いいね」と思うような解決策を提示することができれば、それがデザイン作業なのだと思います。建築デザインも製品デザインも、グラフィックデザインも、美しく目の前の課題を解決していければ、それは「デザイン」ですし、一方で物の形は見えないけれどもファイナンシャルデザイン、キャリアデザインなど、美しくお金の配分や人生設計を作ることも、ある種の美しさを伴う「デザイン」。コミュニティデザインも同じです。人と人の結び付き方の妙であったり、彼ら自身のやる気や共感をぐっと高めていく。それがコミュニティの力を使ったデザインなのだろうと思います。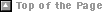
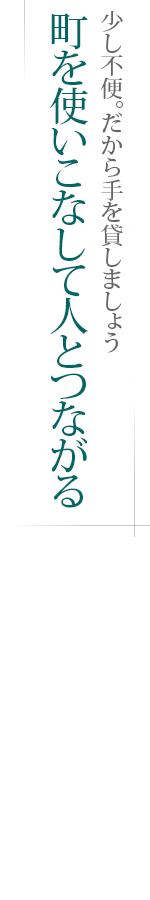
 ええ。誰かと共同する必要のない便利な町を作ってきてしまった結果、つながりが断たれて問題が出始めているのではないかと思うんです。関係性がないから、「あの人、どうしているだろう」と、気に掛けることもできなくなってしまったわけですが、それをハードで解決しようとしても難しいと思うんです。やはり日々、町の中で、誰かとつながるという行為を増やしていくことが、ある意味のセーフティーネットとなる。そうやって、民と民、個と個が相互につながる仕組みが必要だと思うのです。
ええ。誰かと共同する必要のない便利な町を作ってきてしまった結果、つながりが断たれて問題が出始めているのではないかと思うんです。関係性がないから、「あの人、どうしているだろう」と、気に掛けることもできなくなってしまったわけですが、それをハードで解決しようとしても難しいと思うんです。やはり日々、町の中で、誰かとつながるという行為を増やしていくことが、ある意味のセーフティーネットとなる。そうやって、民と民、個と個が相互につながる仕組みが必要だと思うのです。