「人間の体を計測することは新しいサービス、新しいマーケットを生み出すことになるのです。」
身長、体重、足のサイズ…。「体のサイズは?」と問われて
数値を答えられる部位は、数えるほど。しかし、本当ならきちんとした
自分のサイズを知らなくては、ぴったりの服を買うことも難しいし、
メタボリック症候群のように、ウエストサイズと健康も深い関連がある。
「人間のサイズ、形、動きは、体を介して表に現れた本質である」というのは
人体計測と、それによって得られたデータを活用するサービスを研究する
持丸正明さん。人体を測って何が分かるか、そしてそれを実生活で
どのように活用するのか、お話を伺った。
―― |
眉の長さ、膝の大きさなどなど、何十年も前から、私達の体のあらゆる部分について計測が行われていたというのは、一般の人はあまり知りません。 |
持丸 |
もともと、人体を測るというのは、例えば椅子を作るとか、家を建てるとかいう時に、何をどの程度の寸法にすべきか、使う人々の平均値を出すためのものです。ですから人の体を測るということ自体は、これまでも連綿と行われていますが、私が所属しているデジタルヒューマン工学研究センターでは、さらにそれによって「サービス」を作ることを目的にしています。 |
―― |
ありますね(苦笑)。 |
持丸 |
誰しもそういう経験はあると思います。でも一度も履いていなくても、POSデータで分析すると、その靴は「売れた」ことになり、どんどん生産されます。ですが、ほとんど使われない物というのは、本当の意味での「価値」は生産されていません。そう考えると、使って良かったからまた使いたい、それによって生活が変わったという価値をもっと訴求していくべきではないかというわけです。そのために人の体を測るということが役立つと考えているのです。 |
―― |
測ることで新しい価値を作ることができると? |
持丸 |
生活様式や物の使い方、さらに体つき、運動量、健康状態も、人それぞれですよね? そこでどんな体つきなのか、運動能力なのか、生活なのかを「測る」。測って、それに「合わせる」ことで、プラスの価値を生み出していくのです。ただ、個人に合わせるために、完全にオーダーメードにしていては、コストが掛かりすぎますし、そうした完全オーダーメードという業態はすでにあります。ですが、例えば靴。人の足の形は千差万別ですが、1,000人のために1,000足の靴を作るのではなく、10人に合う1足を作ることで、カスタマイズの程度はかなり高くなります。つまり、個別対応とマスの間―私たちはメゾと呼んでいますが、ある程度のグループに分けて、それらに対してカスタマイズしていこうというのです。そうすれば大量生産であっても価値が生まれます。そのために人を測るということが必要なのです。 |
―― |
セミオーダーのようなものでしょうか。 |
持丸 |
ええ。例えば我々の技術を靴のメーカーに提供しています。店舗で足の形を測り、量産品の中から、その人の足に最も合う商品を選び、さらに個別に中敷きをカスタマイズして提供するというサービスです。 |
―― |
足のサイズだけでなく、運動についても測られているとか。 |
持丸 |
ええ。以前から、歩くということにすごく関心があって、歩行のデータをラボで取っています。 |
―― |
歩行のデータと言うと具体的には何を測るのでしょう? |
持丸 |
|
―― |
しかも、今は実験室だけでなく簡易な装置を用いて、リアルタイムで自分の歩行の様子が分かるようになっているとか。 |
持丸 |
そうです。精緻なデータを基にして数式を得られたので、ウォーキングマシンのような簡易化した装置の上を歩いてもらうだけで、計測できるようになりました。 |
―― |
歩く時の何かが転倒リスクと関連があるというのでしょうか。 |
持丸 |
転ぶのは大きく二通りあって、一つは地面に着いた踵が滑る場合、もう一つは空中に上げている足が、何かに引っ掛かって転倒する場合です。後者は「つまずき」と言って、こちらはいろいろと研究があります。空中に上げた足を捉えたモーションキャプチャを見てみると、歩行時、人間は意外と足を高く上げていないこと、またそうして上げた足は、本人が意識せずとも、一歩一歩、ほとんど同じ高さに上がっているということが分かります。繰り返し、ほとんど同じ高さですから、人間って大したものだと思います(笑)。ところが高齢者になってくると、頭の中では同じ高さに上げているつもりですが、実際には高さにばらつきが出てくるのです。 |
―― |
本人はいつも同じように上げているつもりでも、足が1cmしか上がっていない時もあれば、3cm上がっている時もあると? |
持丸 |
そうです。そのばらつきが、つまずく原因だとする研究もあります。当然と言えば当然ですね。1cmしか上がっていないところに1cm以上の何かがあったら、つまずいて転倒してしまいます。 |
―― |
身体のサイズ同様、できると思っていた動作ができないなど、高齢者に限らず、認識とのずれはありますね。 |
持丸 |
そうですね。転倒リスクについて言えば、ほとんどの方が認識していらっしゃらない。気仙沼でも、やはり見ただけでは分からない転倒リスクのばらつきが明らかになりましたが、意識すると変わるようで、1ヶ月後の計測では結果が大きく変わっている方もいて、我々も驚きました。歩き方というのは、意識するだけで割とすぐに変えることができるようですね。 |
―― |
意識を持っていたら、リスクも変わるものでしょう? |
持丸 |
意識することによって、少なくとも歩行機能は向上するでしょう。そう考えると、まず測って、知って、というのは、大事なことだと思います。 |
―― |
これを測れば、こういうことが分かるというのではなく、いろいろな部分を測っていくことによって―例えば、歩行の際の膝の曲げ具合といった差が、何に影響を与えているか見えてくるわけですね。 |
持丸 |
さまざまな計測の結果は人それぞれに違いがありますが、測ることによって、そのグループみたいなものが見えてきますね。それは個々人の暮らしをより良いものにし、その個々人のデータが多数集まって、ものづくりへと生かされていく...その二重のループを回していこうというのが、私たちの目的ですが、私が人体計測を続けてきてこの10年で大きく変わったと思うことが二つあります。一つは、計測機器類が非常に安価になったということ、二つ目にそれらがネットワークにつながったということです。人体計測という分野においては、この二つが劇的な変化をもたらしました。 |
―― |
昔は、被験者に研究室まで足を運んでもらって測っていたわけですものね。 |
持丸 |
装置が非常に高価だったためです。自動車レースで言えば、F1マシンみたいなものですから、高い上に乗りこなすのがすごく難しい。だから、なかなか使えなかったのです。それがここ10年でコンパクトカーのように手ごろになって、操作もボタン一つで簡単にできるようになったわけです。例えば、足の計測器に限れば、価格は10年前と比較して10分の1。それによって民間に広く開放され、データも蓄積されるようになりました。もちろんそのために計測範囲が狭まったり、精度が落ちたりといったデメリットはありますが、それを実験室の「F1マシン」によって補うことができます。精緻なデータを集めて、しっかりとしたデジタルヒューマンモデルを作れれば、全体を復元できるからです。ですから、人体計測が進化したというよりも、人体計測を取り巻くICTと、ネットワーク環境が劇的に進化したと言えます。 |
―― |
集められるデータの数も変わりましたか。 |
持丸 |
全く違います。数百万、数千万のデータが集められるようになりました。条件を整えて完全にコントロールされた実験室でのデータでないから有意でないという声もありますが、母数が100の時の10のばらつきは問題ですが、1,000万や1億が母数となれば、問題にはなりません。むしろより現場に近い、さまざまな条件でデータを集めることができるのです。 |
―― |
しかも、地域も限られなくなるわけですね。 |
持丸 |
まさに日本の一部の企業が行っていることですが、計測のハードルが低くなったからこそ、例えば世界各地に店舗を持ってデータを集め、その国や地域の人に合わせた商品を製造することができます。さらに今は、携帯電話、それもスマートフォンの普及によって、様相が一変しました。10年前は、携帯電話に、加速度やコンパス、GPS、カメラ、ネットワークといった機能が備わるとは想像しませんでしたが、今やユーザー一人ひとりが人間計測の装置を常時身に着けていて、必要であればデータを送ることができる。こんな環境は、一昔前なら信じられないことです。 |
―― |
今までは到底集められなかったデータ量が手に入るようになっていると。 |
持丸 |
セキュリティには配慮しなくてはなりませんが、自分のライフスタイルや運動機能に合った製品やサービスを選んだり、提供を受けたり、かつその効果を自分で確認していくこともできるようになりましたし、あるいは、それを一緒に使っている人とのコミュニティーを共有していくというようなこともできるようになりました。そういう面でも、データの使い方は、今までと変わったのだと思います。 |
―― |
負債、ですか。 |
持丸 |
|
―― |
しかも、日本にはいろいろな製品がありますから、そこにデータがのれば...。 |
持丸 |
まさしく、その点はとても重要なことです。家電製品のメーカーを持っている先進国は、実は限られていて、アメリカにはもうほとんどありませんし、ヨーロッパでも大きなところは2社しか残っていません。ところが、日本にはたくさんあります。となれば、炊飯器や冷蔵庫、テレビ、洗濯機などセンサーになり、データを集め得る機器を各家庭に配っているのは、先進国では日本が随一です。であれば、そこから蓄積したデータをコンテンツ化して使用価値へと結び付けられるはずです。日本の家電メーカーが苦戦していますが、むしろこれは一つのチャンスだと思うのです。 |
持丸正明(もちまる・まさあき)
1964年生まれ。専門は人間工学、バイオメカニクス。1993年慶應義塾大学大学院理工学研究科後期博士課程修了。工業技術院生命工学工業技術研究所研究員から改組を経て、2001年産業技術総合研究所デジタルヒューマン研究ラボ副ラボ長、現在デジタルヒューマン工学研究センター長。IEEE Computer Society、SAE、日本人間工学などの会員。2002年、新技術開発財団・市村学術賞受賞。
●取材後記
高齢者の話題とともに、子どもの安全も「測る」ことによって一層、確保されてきている。子どもの事故は、大人には思いもよらない所で指や首を挟まれてしまうことが多く、体格データや暦年齢と行動範囲のデータが重要になるそうだ。完成度が高いと思っていた製品にも、まだまだ改善の余地がある。逆に、たくさんの計測データを集めることで、個人差の少ない部分と多い部分が見え、やみくもに個別対応するのではなく、何に注力し、何にはしないか、という生産過程の効率化にも一役買いそうだ。人間、まだまだ測りがいがある。
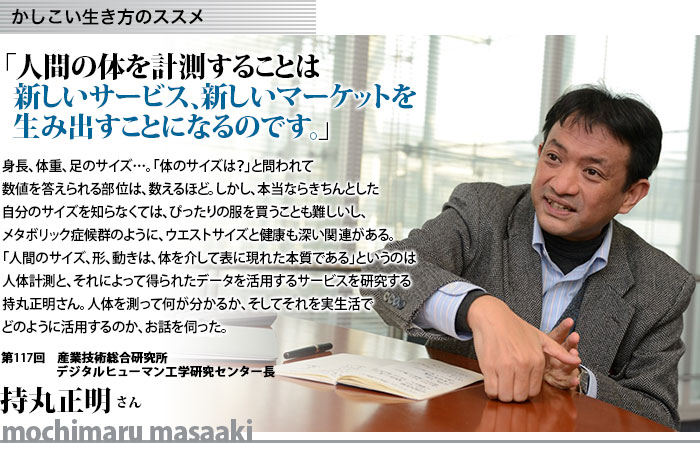
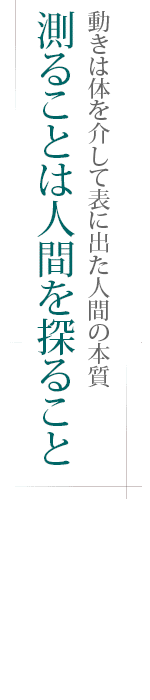
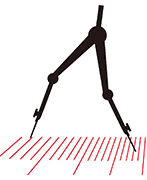 体に50個以上の反射マーカーをつけ、モーションキャプチャで歩く時の姿を記録すると同時に、足下に埋め込んだセンサーで、地面にかかる力を計測するのです。動きと力が分かれば、関節にかかる負担をコンピュータで計算することができます。そうやってデータが集まると、日本人の歩き方の個人差のパターンが分かるんです。
体に50個以上の反射マーカーをつけ、モーションキャプチャで歩く時の姿を記録すると同時に、足下に埋め込んだセンサーで、地面にかかる力を計測するのです。動きと力が分かれば、関節にかかる負担をコンピュータで計算することができます。そうやってデータが集まると、日本人の歩き方の個人差のパターンが分かるんです。
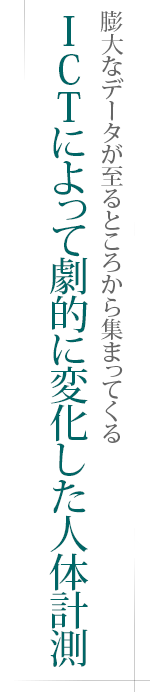
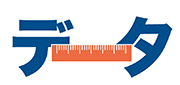 データを持っていたら、情報を保護したり、記録機器を用意したり、バックアップをとったりと維持管理にコストがかかります。つまり固定資産税を払い続けなければいけません。しかし、それを統計処理して、何かの設計につなげて活用することができたら、データは資産へと変わります。我々は、活用できる形をコンテンツと呼んでいますが、データをコンテンツ化する技術を持っていなければ、データをいくら集めても、負債が増えるだけなのです。
データを持っていたら、情報を保護したり、記録機器を用意したり、バックアップをとったりと維持管理にコストがかかります。つまり固定資産税を払い続けなければいけません。しかし、それを統計処理して、何かの設計につなげて活用することができたら、データは資産へと変わります。我々は、活用できる形をコンテンツと呼んでいますが、データをコンテンツ化する技術を持っていなければ、データをいくら集めても、負債が増えるだけなのです。