「調理の目的は食品をおいしい食物に変えること。調理科学はそのための条件設定を追究します。」
「さっと熱湯にくぐらせたら、すぐに冷水にさらして...」
「さっと」「すぐに」などなど、細かい手順を積み重ねる調理。
最近「科学的に考える調理法」が話題だが、そもそも加熱も撹拌も、
化学反応が関わっている。だからこそ昔から、言われてきた
料理の手順にもそれぞれ合理的な裏付けがある。
お茶の水女子大学で調理科学を担当する香西みどりさんに
調理における科学とは何か、お話を伺った。
―― |
まずは、調理科学とは、どういうものなのかというところから、お話を伺えますか。 |
香西 |
私の専門である調理科学は、英語で「cookery science(クッカリー・サイエンス)」と言います。「食品化学」と「調理科学」の違いは何かというと、食品化学は、食品そのものを扱うのに対して、調理科学は、その食品を、おいしい「食べ物」に変化させるのがテーマだという点です。調理のゴールは「おいしい食物を作る」こと。そのために、調理の過程を研究し、最終的にどういう状態になったものが嗜好的に好ましいか、そしてそのために必要な条件とは何か――そうした一連の流れを研究するのが、調理科学だと言えます。 |
―― |
例えば、どの位の時間、何度で加熱すると、その食材にどんな変化が起きるといったことを調べるのですか。 |
香西 |
ええ。何度で何分、どういう速度で加熱したら、どういう状態になるのか。さらには火を止めた後も余熱を利用する場合には、何分火にかけて、沸騰させて、いつ火を止めればいい、といった、そういう条件設定を考えます。 |
―― |
最近、野菜は50度で洗うといいと言われますが…。 |
香西 |
サラダは多くの場合、その歯触りを楽しみたい。であれば、買って冷蔵庫に保存していた野菜を一般には冷水につけてシャキッとさせます。50度で洗うと細胞膜への影響と熱ショックタンパク質の生成が考えられますが、実際にやっておりませんので……。野菜に限らず、植物性食品の場合には、60度付近で加熱すると、生の時よりも、ちょっと硬くなるという変化が起きます。 |
―― |
水に入れてゆでれば何でも軟らかくなるという単純なものでもないのですね。 |
香西 |
それは50度加熱とはまた違った現象です。50度というのは、植物性食品の細胞膜が壊れる温度なので、植物の中でさまざまな反応が起きる重要な温度と言えます。ただ、50℃で割と短時間で処理した上で観察される効果と、もうちょっと長い時間をかけた上で観察される硬化という現象の関係は現時点では何ともいえません。私が研究している野菜の硬化に関して言えば、植物は、60度位で加熱すると、生の時よりも硬くなります。 |
―― |
それが意外だったのです。生の時よりも加熱した方が硬くなることがあるとは。 |
香西 |
|
―― |
「試料」とは、この場合ジャガイモを指していますよね? |
香西 |
はい。食材ですね。調理だと食材ですが、実験だと試料と呼ぶもので(笑)。 |
―― |
まさに科学ですね。そうやって、ある「試料」は、こういう硬化の仕方をすると数値で表すことができれば、失敗なく調理ができるということですね。 |
香西 |
ええ。最適な調理状況の設定ができれば、誰が調理しても同じように再現できますし、あるいは大量に調理する時などは、一定の品質が確保できます。それをコツや経験に頼るのではなく、調理条件の設定を数量的な表現で行うことで、一定の状態で再現できる、再現性の高い調理方法が得られるのです。 |
―― |
調理条件に関して言えば、「こういう時には、人参はこう切って、こうゆでなさい」といったところまで、落とし込まれるのですか? |
香西 |
たとえば切り方ひとつにしても、直方体と立方体など、いろいろな形が考えられます。では、その形、大きさだったら、どういう風に温度が上がっていくのか、どういう風に味がしみ込んでいくのか、硬さはどう変化するのか、これらはシミュレーションによって分かります。試料の中でどういった変化が起きるのか、最終的に自分が望ましいと思う状態にするためには、何分加熱したらいいかなど、適切な調理条件の設定ができるのです。 |
―― |
硬化という現象を利用して煮崩れしにくく仕上げられるということは、逆にマッシュポテトを作るために煮崩れしやすいように調理することもできますね。 |
香西 |
ええ。温度変化がゆっくりだと硬化が起きやすいということは、煮崩れさせたいなら、なるべく速く温度を上げること、つまりたくさんの熱湯でゆでるとか、細切りや薄切りにすればいいということです。ただ、問題なのは、薄切りにして、速く温度を上げるということは、速く細胞膜が破れるということです。50度以上の加熱で細胞膜が破れると、細胞の中から成分の溶出が起きますが、薄く切ったり、細長く切るということは、熱が伝わりやすいと同時に、同じ重さに対して表面積が大きい形――つまり、細胞膜から成分が出やすい形でもあるのです。 |
―― |
煮崩れしやすい形と、成分の溶出は表裏一体、こちらを立てると、あちらが立たないというわけですね。 |
香西 |
溶出させたくないのなら、表面積の小さい、丸に近い形の方が、温度の上昇速度がゆっくりになります。ただ、別の問題も出てきて(苦笑)、温度の上昇が遅いと、長い時間加熱しなければいけません。それもまた、成分が溶出する機会を増すことになる――そういう現象を踏まえた上で、何を優先させて調理するかを考えることが大切なのです。 |
―― |
いろいろな条件が複雑に絡み合っていますね。 |
香西 |
兼ね合いが大切なのです。その食品、食材のおいしさを決めるのは糖だなど、単純に決められれば話は簡単ですが、そうではありません(笑)。ある食材がおいしい状態にある時には、成分や硬さ、それから水分の変化に、色なども関わって、そのおいしさが感じられるわけです。ですから、例えばテクスチャ−(歯ごたえ)が大事だというのであれば、そこに着目して、ちょうどいい状態になる条件を設定する。その上で成分の変化や溶出について調べる。そうやって、優先順位の高いものをゴールの指標として、条件設定をするのです。例えば、丸ごと蒸した状態がおいしいし、それが最終ゴールだというなら、調理もそのように丸ごとで蒸し加熱とし、マッシュポテトを作るのだったら、小さめに切って、速くゆでて、熱い内にマッシュするということになるのです。 |
―― |
そうやって最終的なゴールを決めると、その手前の過程が違ってきますよね。 |
香西 |
そうですね。例えばホウレン草に含まれるクロロフィルという色素は、ゆでると分子構造が壊れて、褐色の分解物へと変化するため、それを抑えるためにホウレン草をゆでた後は、冷たい水にさらしなさいと言われます。それはまた、あくの成分であるシュウ酸を除くためでもあります。だからといって、長時間、水に浸けると、ゆでているので細胞膜が壊れていますから、シュウ酸だけでなく糖やアミノ酸、あるいは味に関係する成分も出ていってしまいます。 |
―― |
だから「さっ」と、水にさらすと。 |
香西 |
そうです。「さっ」です。温度を下げるのが第一目的ですから「さっ」と浸ければいいのです。 |
―― |
その「さっ」が、手間に感じてつい省きたくなりますが、そこで差が出てくるわけですね。 |
香西 |
見た目はあまり変わらないと思いますが、食べた時には差が出ますね。ゆで時間が違えば、色、歯触りも違います。標準的なゆで時間は1分30秒くらいですけれど、そこから先は好みの問題もあります。 |
―― |
まずは、何をすればどうなるという、そこに至るまでの基礎を知っておかなければ、個別に対応することもできませんね。 |
香西 |
牛乳には、カルシウムイオンが含まれます。カルシウムイオンは、2価の陽イオンです。これに対して、牛乳のタンパク質は、普通は全体として陰イオンを帯びた状態です。2価の陽イオンを持っているカルシウムイオンは、ちょうど手が二本あるような感じで、それがタンパク質の陰イオン部分と結合してタンパク質同士をつなぐ、橋渡しをするような役割を果たすので、卵に牛乳を入れると凝固を促進するのです。固まりながらも、加えた牛乳の分だけ水分が増すので軟らかくもなる。その硬さの違いが、人間の嗜好から言うと、好ましいとなるわけですね。人間の好みの問題です(笑)。 |
―― |
先ほど、ジャガイモのゆで方についてお話が出た時、素早く裏ごしすることがポイントだとありましたが? |
香西 |
冷めてからだと、ジャガイモの細胞がバラバラにならずにくっ付いてしまうんです。また固まりが大きいと、つぶすのに時間がかかるので、その間にやはり温度が下がり、そうすると粘りが出て、いも団子みたいになってしまいます。 |
―― |
なぜ、粘りが出るのですか。 |
香西 |
|
―― |
細胞の中にでんぷんが収まる…料理をしている時に考えてもいませんでした。粘りといえば、天ぷらの衣は、さっと混ぜるだけと言われます。 |
香西 |
グルテンができるからです。天ぷらは、中に揚げ種があって、衣があって、油、という構成です。衣の水分が油の方に出ていき、油が衣の中に入ってくる――要するに、天ぷらとは、水と油の交替なんですね。そして衣の中に守られている揚げ種は、例えばサツマイモだったら軟化してホクホクになるし、魚介類だったらタンパク質が変性しておいしくなる。しかも周りに衣があるので、揚げ種の水分は保たれているので瑞々しさもあります。一方、衣の方は、水と油の交替が起きてカリッとした歯触りになるのです。 |
―― |
なるほど! |
香西 |
卵を入れると加える水分としては少なくなってグルテンの形成が抑えられたり、水の温度が高いとグルテンができやすくなるので氷などを使って10度前後まで水温を下げるといった工夫がされています。 |
―― |
化学反応ですね、本当に。 |
香西 |
わさびなどすり下ろして用いますが、包丁で切っただけではあまり辛みがないのをご存じですか。わさびの辛みはアリルイソチオシアナートという成分で、配糖体シニグリンがミロシナーゼという酵素によって辛みとなるのですが、シニグリンとミロシナーゼは、細胞の中の別々の場所にいるので、すりおろすことでわさびの細胞を壊して基質と酵素が出会い辛み成分を出すように反応させているのです。リンゴもただ切った時よりも、すりおろすと、すぐに茶色くなるでしょう? |
―― |
瞬時に茶色くなりますね。 |
香西 |
あれも酵素反応が激しく起きた結果の褐変です。 |
―― |
こうしていろいろな現象を解いていただくと、きりがないのですが、最近、一番面白かった実験はどんなものでしょう? |
香西 |
卵ですね。マヨネーズを電子レンジで温めたり、冷凍庫に入れたりすると、その後、油が分離するというのは理屈では分かっていたのですが、何とも言えない感じが本当に面白くて(笑)。マヨネーズは卵と酢と油で作られていますが、油分は75%です。その油を、卵黄の低密度リポタンパク質(LDL)という強力な乳化剤の役割を果たす成分が抱え込んでいるのですが、LDLはタンパク質だけあって、高い温度にも低い温度にも弱いんです。開封前のマヨネーズを室温で保存するのはそのためです。ではマヨネーズを加熱したらどうなるのか、凍らせたらどうなるのかと実験してみたところ、冷凍したものは溶けると油が出てきますし、電子レンジで温めたものはすぐに分離します。乳化剤の役割を果たしているLDLが変性してしまい、その役割を果たせなくなって油を抱きかかえることができなくなり、油と水が分離して、元に戻らなくなるのです。つまり、マヨネーズじゃなくなっちゃうわけですね。 |
―― |
(笑) |
香西 |
卵白は卵黄に比べるとそれほど冷凍に弱くはないので、卵白を凍らせて、室温に戻して泡立てると、凍らせる前よりも泡立ちは悪くなりますが、それでも泡立たないことはありません。けれども卵黄の場合はそのまま冷凍庫に入れると、ゴムボールみたいにまん丸になるんです(笑)。殻ごと冷凍庫に入れても、卵黄は変性してボールみたいになってしまいますが、ともかく卵黄の冷凍変性は、ゴムボールのような、弾力のある何とも言えない状態になり、解凍してももう液状には戻らなくて。 |
―― |
何かに使えるのでしょうか。 |
香西 |
そうですね…デザートに使えるかもしれませんね。まん丸くなって、もちもちしているというか(笑)。もう元に戻らない変性の仕方をしているので、室温に戻しても、ボール状のままコロコロっとしていて、弾力があって(笑)。 |
―― |
今日、家でやってみますが(笑)、それは何が起きているのですか。 |
香西 |
一口に「変性」と言っても、加熱による変性と、冷凍による変性とでは若干異なります。変性とは、タンパク質の立体構造が壊れることですから、変性した後のタンパク質の凝集、凝固の仕方が違うのだと思います。例えば、ゆで卵にした時は、卵黄にほくほく感がありますよね? ああいう卵黄の中に含まれている顆粒状のものが、冷凍すると状態が変わり、凝集、凝固の仕方にも影響をするのだと思います。 |
―― |
現象だけをとってみても面白いですね。今日のお話は、調理科学全体からみたら本当にごくわずかなエッセンスだと思いますが、こういう機会は、小学生など学校教育の場で行われてもいいのではと感じました。 |
香西 |
そうですね。食育という言葉は、100年以上前に小説家の村井弦斎から広まったものです。彼は、「小児には、徳育よりも、知育よりも、体育よりも、食育が先」と言っています。知識を教えるよりも食育が大切だと言っているわけです。その大切な食育が、なぜ学校の科目にならなかったか。良い方に考えれば、身近な場、つまり家で学ぶものだということで、授業の科目として取り上げられなかったのかもしれません。昔は炊飯器などなく、調理の作業が多いので、家の中で手伝いなどを通して親から伝わる機会がもっとあったのかなと思います。ですから、家で調理をしないと興味を持つ場面も少なくなり、食育の観点からも機会が少なくなるのではと思います。 |
―― |
家でもそうした時間を持とうという気持ちはありますが、それでも少ないように感じます。もっといろいろな場で、小麦粉をこねすぎたら、こうなったということを実体験する場が増えた方がいいですね。 |
香西 |
「やってみてこうなった」ということを踏まえれば、次はもっとよくなりますし、たぶん、やればやるほど、誰でもうまくなっていくと思いますので。 |
香西みどり(かさい・みどり)
1955年福島県生まれ。78年お茶の水女子大学家政学部食物学科卒業。同大学院家政学研究科食物学専攻修了後、同大生活科学部助手を経て2006年同教授。現在に至る。著書に『調理がわかる物理・化学の基礎知識』(光生館)、監訳書に『マギー キッチンサイエンス』(共立出版)。
●取材後記
「味噌汁は煮えばなをいただくのがいい」と言われる。大豆から作られる味噌のタンパク質はコロイド粒子という状態で安定しており、汁に入れたばかりの時は分散しているけれど、加熱し過ぎたり、時間が経ったりすると、粒子が集まってしまってうまみ成分も一緒に沈んでしまい、汁のうま味がなくなるのだという。調理の「なぜ?」を伺うと即座に、その仕組みを解きほぐして下さり、何だか魔法のよう。その仕組みを知るだけでも料理はますます楽しくなる。
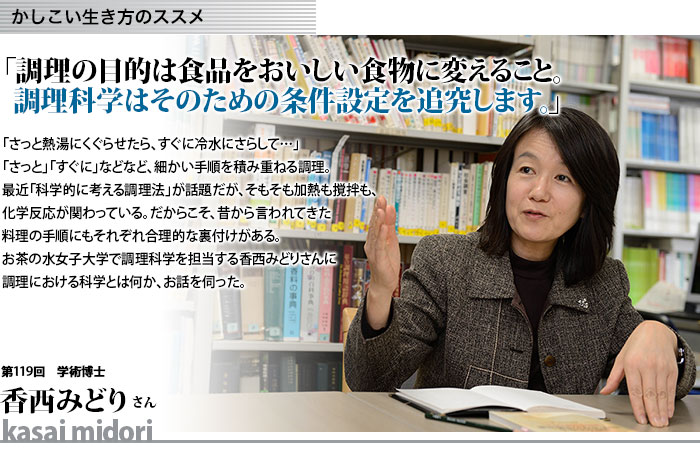
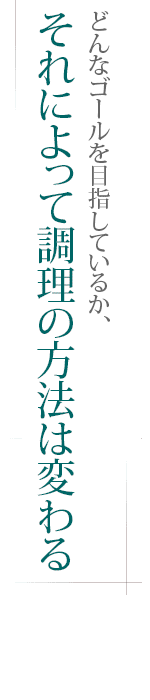
 一般にゆでた野菜は軟らかくなりますね? ところが実は、野菜は加熱すると一度硬くなるのです。水からゆでても熱湯に入れても、程度は異なりますが60度前後で硬化の現象が同様に起こります。その際、硬化の影響をしっかりと受けているものは、煮崩れしにくいのです。つまり、水から加熱すれば、硬化が起きる温度帯をゆっくり通過していくので、しっかりと硬化が起き、その後、沸騰して段々と軟らかくなっていきます。ですから、この硬化という現象を上手に利用すれば、煮崩れしにくいジャガイモに仕上げられるわけです。逆に、あまり硬化を起こしたくないのなら、速く温度を上げればいいということになります。ですが沸騰水に入れると、食物の中心部と外側の温度差が大きくなり、それによる硬さの差も大きくなって、不均一な仕上がりになってしまいます。ですから、根菜類を加熱する時は水からゆでるとよいと言われるのです。私たちは経験的に水からゆでていたわけですが、実際に試料の中の温度分布を調べても、確かに均一に仕上がり、外側が煮崩れしにくいことが分かります。調理の過程をシミュレーションし、試料の断面の中心と外との違いを見る、より細かく試料の断面を1mm刻みで調べるなど、数量的な把握も、私たちの研究テーマの一つです。
一般にゆでた野菜は軟らかくなりますね? ところが実は、野菜は加熱すると一度硬くなるのです。水からゆでても熱湯に入れても、程度は異なりますが60度前後で硬化の現象が同様に起こります。その際、硬化の影響をしっかりと受けているものは、煮崩れしにくいのです。つまり、水から加熱すれば、硬化が起きる温度帯をゆっくり通過していくので、しっかりと硬化が起き、その後、沸騰して段々と軟らかくなっていきます。ですから、この硬化という現象を上手に利用すれば、煮崩れしにくいジャガイモに仕上げられるわけです。逆に、あまり硬化を起こしたくないのなら、速く温度を上げればいいということになります。ですが沸騰水に入れると、食物の中心部と外側の温度差が大きくなり、それによる硬さの差も大きくなって、不均一な仕上がりになってしまいます。ですから、根菜類を加熱する時は水からゆでるとよいと言われるのです。私たちは経験的に水からゆでていたわけですが、実際に試料の中の温度分布を調べても、確かに均一に仕上がり、外側が煮崩れしにくいことが分かります。調理の過程をシミュレーションし、試料の断面の中心と外との違いを見る、より細かく試料の断面を1mm刻みで調べるなど、数量的な把握も、私たちの研究テーマの一つです。
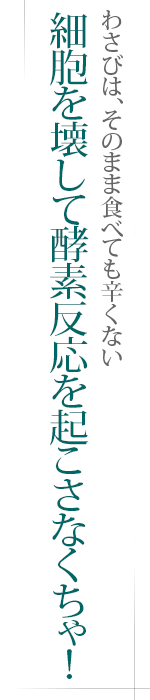
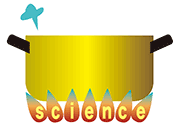 ジャガイモに限らず植物には、細胞と細胞の接着剤のような役割をしているペクチンという物質があって、ゆでることで水や湯に溶け出るのですが、それでも細胞の間に残ります。一般的に粘性は、温度とは逆の関係にあります。高温なら粘性は低く、低温なら高い。このペクチンも、温度が高いほどさらさらしていて流動性があり、細胞と細胞が離れやすいわけです。ですから温度が高い状態の方が、簡単に裏ごしできるのです。マッシュポテトは、ジャガイモの細胞と細胞をバラバラにする料理ですが、温度が下がってペクチンの流動性が低くなってから細胞同士を引き離そうと思っても、なかなかバラバラにはなりません。しかしペクチンの接着力より人間の方が力があるので(笑)、「えいや!」と力を入れて裏ごしすると、細胞が途中で分断されて、中からでんぷんが出てきてしまうのです。するとベタついてしまう。温度が高い内に裏ごししたマッシュポテトは、さらさらしているでしょう? あれは、でんぷんが細胞の中に収まっていて裏ごししても細胞単位で分離しているからなのです。
ジャガイモに限らず植物には、細胞と細胞の接着剤のような役割をしているペクチンという物質があって、ゆでることで水や湯に溶け出るのですが、それでも細胞の間に残ります。一般的に粘性は、温度とは逆の関係にあります。高温なら粘性は低く、低温なら高い。このペクチンも、温度が高いほどさらさらしていて流動性があり、細胞と細胞が離れやすいわけです。ですから温度が高い状態の方が、簡単に裏ごしできるのです。マッシュポテトは、ジャガイモの細胞と細胞をバラバラにする料理ですが、温度が下がってペクチンの流動性が低くなってから細胞同士を引き離そうと思っても、なかなかバラバラにはなりません。しかしペクチンの接着力より人間の方が力があるので(笑)、「えいや!」と力を入れて裏ごしすると、細胞が途中で分断されて、中からでんぷんが出てきてしまうのです。するとベタついてしまう。温度が高い内に裏ごししたマッシュポテトは、さらさらしているでしょう? あれは、でんぷんが細胞の中に収まっていて裏ごししても細胞単位で分離しているからなのです。