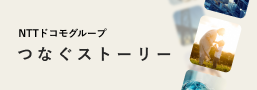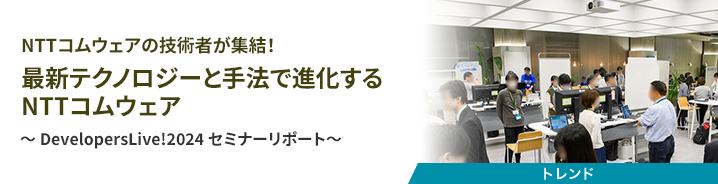
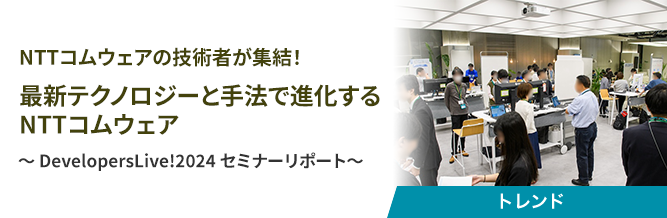
NTTコムウェアは11月14日、NTT品川TWINSアネックスビル(本社)で「DevelopersLive!2024」を開催した。本イベントは同社社員向けに最新のソフトウェア開発技術を体験する場として、2017年から毎年開催している。今年は「けしからん成長」をテーマに参加対象をドコモグループ全体に広げ、これまでの開発スタイルからは”けしからん”とされる方向性や技術施策を中心に10のセミナーと展示で紹介し、社員同士の活発な交流がおこなわれた。
最初に、コーポレート革新本部の常務執行役員 武田晴信、執行役員 渡邊浩誠より、今回のテーマである「けしからん成長」に関する意図や方針を説明。続いて、NTTコムウェアと複数の共同プロジェクトを進めているNTTドコモの三井氏が「BizDevOps」の実践について熱い想いを伝えた。そして、各プロジェクトメンバーが自身のプロジェクト解説を行った。なお、各プロジェクトメンバーには、現在携わるプロジェクトと社会の関わりや自身のやりがいについて聞いた。
コーポレート革新本部 常務執行役員 武田晴信

はじめに、テーマに使われた『けしからん』という言葉を解説。「これまでは、『最近の若い者はけしからん』のように、ネガティブな意味に使われてきた言葉だが、最近は『もっと見たい、知りたい、聞きたい』といったときに使う好意的な意味合いになっている。この場ではぜひもっと知りたい、もっと聞きたい情報、ツールに触れて、職場で活用して欲しい」と意図を語った。
コーポレート革新本部 執行役員 渡邊浩誠
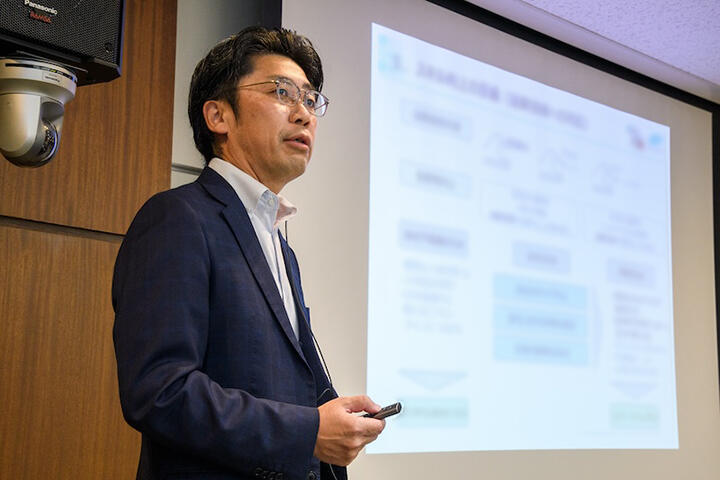
「エンジニアのけしからん提案」がテーマ。「正しいものを正しくつくれているか?を問い続けながら、最新技術に挑戦し、自由な発想で新しい価値を生み出す魅力的な会社でありたい。カスタマーエクスペリエンス向上のためには、お客さまがITへ求める価値をビジネス目線で考えられるビジネスアナリストの育成が必要である。これまでのロジカルシンキング、デザインシンキングを超えたアートシンキングで今までにない価値のあるものをつくっていきたい」と語った。
NTTドコモ 第一プロダクトデザイン部 部長 三井力

タイトルは「ドコモのスマートライフ事業を支えるBizDevOps ~あなたが主役だ!」。「パブリッククラウド、スマートフォン、ターゲティング広告を活用したマーケティングの普及により、現在では誰もがアプリケーションの開発や効果的なマーケティング活動を行える時代となった。コンペティターが増え続けるなかで、企業においては顧客視点とスピードが重要である。これまでの開発のように「プロジェクトマネジメント」に疲弊するのではなく、「プロダクトマネジメント」に注力していきたい。ビジネス部門(Biz)、開発部門(Dev)、運用部門(Ops)がコミュニケーションを密に一体となり、チーム全体が顧客価値向上を意識する「ONE TEAM開発」をしよう。NTTコムウェアとの共同開発においては、ONE TEAMでスピード感のある仕事ができている。失敗を恐れずにチャレンジする風土がある」と語った。
「ソフトウェアの価値を向上させるUI/UXデザイン」

<講演者>
NTT IT戦略事業本部 DigitalDesign&DevelopmentCenter 古川洋祐(写真なし)、佐藤ちひろ(写真左)
コーポレート革新本部 技術革新統括部 吉村優(写真中央)、伊藤あずさ(写真右)
UI/UXデザインとは「ユーザーにソフトウェアへ価値を見いだしてもらうための手段」である。その価値には「機能的価値」と「心理的価値」があり、「開発」が機能的価値を向上させるのに対し、「デザイン」は心理的価値を向上させる。心理的価値向上のプロセスは「共感 > 定義 > 発想 > 試作 > 検証 > 構造化」である。
まず、ソフトウェアを使用するユーザーの行動と心理を調査し、ユーザーに「共感」する。次に、調査したユーザーの行動と心理を【確率】を用いて分析し、より効果効率的に心理的価値を向上させるための課題を「定義」する。
NTTコムウェアはAIを活用したセキュリティ運用を実現するAI Advisorの開発に参画しており、実例を交えて「発想」、「試作」のプロセスを解説。「発想」ではカスタマージャーニーマップを用いサービス全体のユーザー体験を起点に複数の実効性ある課題解決策を立案、「試作」ではユーザーを直感的に誘導する機能性と使いやすさ、視覚的魅力が重要であり、デザイナーとエンジニアの連携がポイントとなる。
「検証」で用いるテスト手法として探索的テストを紹介。テスターの経験を活用し、テストの設計と実行を並行して行うことで高速なテストが可能である。実運用に近い環境でシステムに触りユーザーに共感することで、未知の課題に気づくことができるという。今後、ステークホルダーへの提案や開発チームでの議論を通じて、継続的な価値向上をめざす。
「構造化」では、情報を整理するためのフレームワークとしてデザインシステムを紹介。これは一貫性のある優れたデザインを提供するために体系化したものである。例として、機能の利用頻度等をもとにUIをデザインする「視覚的階層」、統一感のあるビジュアルや操作体験を提供する「一貫性」、全ての人がWebサイトを利用できるようにする「Webアクセシビリティ」の高いデザインを取り上げた。NTTコムウェアは2022年に社内向けのUI/UXデザインガイドを発行。また、Webアクセシビリティの技術調査にも注力しており、2024年にはWebアクセシビリティ診断サービスを社内向けに提供開始した。
社員インタビュー
古川: 国内最大規模の顧客基盤と大規模言語モデル(LLM)などのAI技術を活用しながら、顧客起点で新たな価値を創造できる仕事に大きなやりがいを感じています。
佐藤:私は経験者採用で入社し1年が経ちますが、UI/UXの意識を全社で向上させたいという思いがあり、この推進活動にやりがいを感じています。弊社の顧客提供価値向上、他社差別化のためには、開発・デザインの連携力強化が不可欠です。そのために、まず実案件を複数創出することでアセット蓄積に取り組んでいます。
吉村:サービスの使い勝手を向上させ、ユーザーに使いやすい体験を提供したいと思います。私たちのチームは、さまざまなシステムを横断して状況を把握できるため、その知見を別のプロジェクトにも展開できます。全社的に貢献できることにやりがいを感じます。
伊藤: Webアクセシビリティの向上は優先度が低くみられることがありますが、実際には老若男女、さまざまな障がいをもつ方々に使いやすさを提供する大切な取り組みであるため、啓発していきたいと考えています。UI/UXの仕事は、さまざまなシステムに関わり、プロダクトの改善に貢献できるという達成感があります。
開発プロセスの革新は、AIだけで良いのか?〜仕様や設計をどのように表現すべきか〜
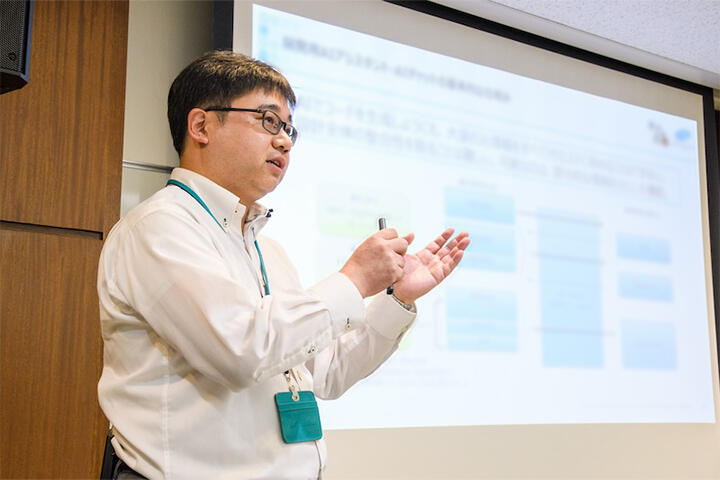
<講演者>
コーポレート革新本部 技術革新統括部
担当課長 高鶴哲也
開発用AIアシスタントによるコード生成では大量の元情報をすべてリクエストに収め、設計全体の整合性を取ることは難しい。現実的には、部分的な情報を元にした補助的な利用になると指摘。
AIをうまく活用するためには2つのアプローチがある。「AIへの入力データをS/N比※1が高く、かつ、LLM※2が学習済みの形式で表現することで、限られたトークンサイズに必要な情報を収めること」、そして「業務固有の部分に対するAI補助にこだわらず、より抽象度の高いプログラミング言語や、設計図を作図するための言語などの、今まで開発者に使ってもらうことが難しかった記法を使いやすくするためのラスト・ワン・マイルとしてAIを活用すること」であると述べた。
自社で提供するAI搭載の新標準統合開発環境は、前述のアプローチを取り入れており、テキスト形式の設計書や抽象度の高いプログラミング言語のコードからAIが既存情報を効率的に解釈できることで、AIコーディング補助の精度を高めることを狙っている。これは、プログラマの潜在能力をより効果的に引き出し、価値あるソフトウェアをお客さまに届けることにつながっている。
- ※1 S/N比:Sound(本質的な情報)/Noise(余計なデータ)の比率。本発表においては、Sound=設計文書内の抽象的な設計情報と捉え、Office文書の図形オブジェクトで書かれた文書は設計書としてのS/N比が低く、構造化テキストやテキスト作図言語で書かれたデータは設計書としてのS/N比が高いと考えている。
- ※2 LLM:Large Language Models(大規模言語モデル)。大量のテキストデータで学習された言語モデルであり、自然な文章生成や言語理解が可能である。
社員インタビュー
高鶴:最新のオープンソースなどを取り入れることで、全社的に技術力向上を推進する仕事にやりがいを感じています。ソフトウェア開発業界では、プログラマが付加価値の高い人材として活躍することが重要です。お客さまの近くでニーズをよく理解して素早く適切にソフトウェアとして具現化できる付加価値の高いプログラマを育成するとともに、プログラマをサポートする技術や手法の探究を進めていきたいと思います。
グリーンソフトウェア開発への挑戦:時代の先駆者になる『けしからん野望』

<講演者>
コーポレート革新本部 技術革新統括部
米原大樹
近年、GHGプロトコル※3のScope3を含むサプライチェーン全体のCO2排出量削減に向け、製品単位のCO2排出量の算定・開示が求められている。しかし、ソフトウェア製品に関しては、開発費用ベースの算定方法しか確立されておらず、開発者の削減努力が反映されにくいことが課題であった。
そこで、NTTコムウェアは同様の課題意識を持つ企業とともに、経済産業省が公募した「令和5年度GX促進に向けたカーボンフットプリントの製品別算定ルール策定支援事業」に参画し、国内初となるソフトウェア製品の算定ルールの検討に取り組んできた。その成果として、経済産業省の「カーボンフットプリントガイドライン」に整合したCO2排出量算定ルールを策定。ソフトウェア製品のグリーンな調達実現に一歩近づいた。
NTTコムウェアは、以前より自社で取り組んでいたCO2削減の知見を活かし、ソフトウェア開発の現場目線でルール策定に参画することで、より実践的で有用な算定ルールを策定することに貢献した。今後、環境性能をビジネス価値の中心に置いたソフトウェア開発・運用を推進し、NTTコムウェアがグリーンソフトウェアビジネスの先駆者として脱炭素社会を実現する”野望”があるという。
- ※3 GHGプロトコル:温室効果ガス(Greenhouse Gas:GHG)の排出量を算定・報告するための国際基準(https://ghgprotocol.org/)
- ※ 本取り組みの詳細はNTTコムウェア公式HPニュースリリース参照
社員インタビュー
米原:ソフトウェア開発の脱炭素化は、NTTグループならではのダイナミックな取り組みだと思います。そして、NTTグループのICTを担う事業会社であるNTTコムウェアがまさに取り組むべき仕事だと思います。私の担当している業務分野は社会課題に直結しているため、やりがいを感じており、楽しく仕事を続けています。ゼロからルールを作り価値を生み出すことに大きなモチベーションを感じています。
2024/12/25
- ※ 商品およびサービスの内容は、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ※ その他、記載されている社名、商品名などは、各社の商標または登録商標である場合があります。