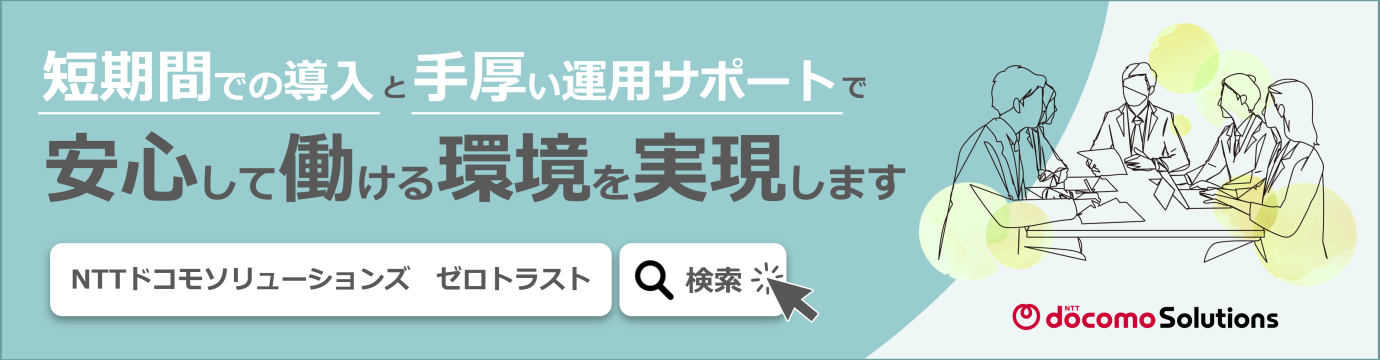「ゼロトラストが必要」と言われても、どこから手を付けるべきか迷っていませんか。
ゼロトラストの実装は、セキュリティリスクの軽減だけでなく、事業継続性や顧客からの信頼獲得にもつながる重要な取り組みです。
この記事では、ゼロトラストの基本概念から段階的な実装ステップ、導入時のポイントまでを分かりやすく解説します。ゼロトラスト導入の第一歩として、ぜひ参考にしてください。
01 ゼロトラストとは?「社内=安全」を信頼しない新たなセキュリティモデル

ゼロトラストは「全てのアクセスを常に信頼せず検証する」という原則に基づいた、現代の働き方に適したセキュリティモデルです。
従来の境界型セキュリティは「社内は安全、社外は危険」として内部ネットワークを信頼していましたが、ゼロトラストでは社内外を問わず、アクセスごとにユーザーやデバイス、そしてコンテキスト(アクセスの時間・場所・普段と違う振る舞いなど)をもとに検証を行います。
ゼロトラストの基本原則は、以下の3つです。
| 基本原則 | 実装のポイント | 具体的な対策例 |
|---|---|---|
| 常に検証 | ユーザー・デバイス・アクセス元を都度確認 | MFA(多要素認証)、デバイス認証、IP制限 |
| 最小権限の原則 | 業務に必要な範囲だけアクセスを許可 | RBAC(ロールベースアクセス制御)、Just-In-Timeアクセス |
| 侵害を前提とする | 侵入後の被害を最小限に抑える設計 | マイクロセグメンテーション、ログ監視、EDR導入 |
テレワークやクラウド活用が進む現代では、社内外の境界が曖昧になり、従来の境界型セキュリティだけでは十分な防御が困難です。そのため、ゼロトラストという新しいセキュリティモデルが注目されています。
ゼロトラストの基礎についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
ゼロトラストとは?セキュリティに詳しくなくてもわかる基本と導入ステップ
02 ゼロトラストの実装は5ステップで進めよう!

ゼロトラスト導入には複数のプロセスがありますが、一般的な進め方の一例は以下の通りです。
- 現状を把握して導入計画を策定する
- ID管理とアクセス制御を強化する
- デバイス(エンドポイント)を保護する
- ネットワークとデータを保護する
- 継続的な運用と改善を行う
まず、自社のIT環境やリスクの現状把握から始めましょう。ID管理やVPNの状態、過去のインシデントなどを確認し、従来の境界型セキュリティからゼロトラストネットワークへの移行を検討します。導入後の目標とロードマップを明確にすることが重要です。
次に、クラウド型のID管理サービスや多要素認証(複数の方法で本人確認を行う仕組み)を活用して、ID管理とアクセス制御を強化し、最小権限の原則を徹底します。
デバイス(エンドポイント)保護では、全端末の管理・可視化を行い、OSやパッチ、暗号化、EDRの導入基準を満たしているか確認します。モバイル端末やBYOD(個人所有端末)も含めて安全性を確保することがゼロトラスト実現の鍵です。
ネットワーク面では、ゼロトラスト型のネットワークアクセス制御やクラウド利用の可視化と制御を導入し、ユーザーごと、アプリケーションごとにアクセス制御を行い、データを保護します。
導入後は、セキュリティ情報の収集・分析や運用自動化の仕組みを活用し、運用体制を継続的に見直すことが不可欠です。 さらに、アクセス権限の定期的な棚卸しやセキュリティ教育を通じて、より堅牢な体制を維持しましょう。リソースが限られる場合は、外部ベンダーの支援を検討するのも効果的です。
03 ゼロトラストの実装に役立つ製品の種類と選び方

ゼロトラストの導入に役立つ製品をまとめると、下表のとおりです。
| カテゴリ | 説明 |
|---|---|
| EDR(Endpoint Detection and Response) | エンドポイントでの脅威検知と対応 |
| IAM(Identity and Access Management) | ID管理とアクセス制御の統合 |
| IDaaS(Identity as a Service) | クラウド型のIAM |
| ZTNA(Zero Trust Network Access) | ゼロトラスト型のネットワークアクセス制御 |
| MDM(Mobile Device Management) | モバイル端末の管理とセキュリティ制御 |
| CASB(Cloud Access Security Broker) | クラウド利用の可視化と制御 |
| DLP(Data Loss Prevention) | データ漏えい防止 |
| SIEM(Security Information and Event Management) | セキュリティイベントの収集・分析 |
| SOAR(Security Orchestration, Automation and Response) | セキュリティ運用の自動化と対応 |
| SWG(Secure Web Gateway) | Webアクセスのセキュリティ制御 |
| SASE(Secure Access Service Edge) | ネットワークとセキュリティの統合クラウドサービス |
| UEBA(User and Entity Behavior Analytics) | ユーザーやデバイスの行動分析・異常検知 |
製品やソリューションは、導入や運用のしやすさを重視し、直感的に操作できる管理コンソールや日本語サポートの有無なども確認しながら段階的に選びましょう。
無料トライアルやデモを活用することで、実際の運用をシミュレーションでき、導入後のギャップやトラブルを防げます。
04 ゼロトラストの実装・運用のメリットとデメリット

ゼロトラストを実装・運用するメリット
ゼロトラストの実装によるメリットは、主に以下の3つです。
セキュリティレベルが向上する
すべてのアクセスを常に検証し、最小権限で許可することで、侵入に成功した攻撃者が、ネットワーク内の他の端末やサーバーへと感染を広げていく動きを防止できます。
IT運用・管理を効率化できる
クラウド型ID管理やシングルサインオン(1回のログインで複数サービスを利用できる仕組み)で複数クラウドの管理を一元化し、セキュリティ情報の収集・分析や運用自動化を活用することで、少人数でも効率的な運用が可能です。
事業継続性と顧客からの信頼を高められる
サイバー攻撃による事業停止リスクを軽減し、顧客や取引先からの信頼向上につながります。また、インシデント発生時に影響範囲を特定しやすいため復旧期間が短縮できます。厳格なアクセス管理は個人情報保護法などへのコンプライアンス強化にも繋がり、ISMS認証(ISO27001)やプライバシーマーク取得の基盤整備としても有効です。
ゼロトラスト実装のデメリット
ゼロトラストを実装・運用する際のデメリットは、主に以下の3つです。
導入コストがかかる
複数のセキュリティ製品を導入・連携させるため、初期費用やライセンス費用が比較的高額になる傾向があります。
運用体制が複雑になる
複数の製品を統合管理する必要があり、各製品の管理に専門知識が求められます。
既存システムとの連携・移行が難しい
古いシステムやレガシーアプリとの互換性問題が発生し、ID管理やネットワーク制御の連携ができない場合があります。互換性調査を行い、中長期的な移行計画を立て、必要に応じてシステム改修やリプレイスを検討することが重要です。
05 ゼロトラストの実装・運用を成功に導く3つのポイント

ゼロトラストの実装を成功させるために、以下の3つを押さえておきましょう。
課題とリスクを正確に把握する
顧客情報や技術データの保存場所、アクセス権限、クラウドや従業員デバイスの利用状況を整理し、リスクを可視化します。
段階的に実装する
多要素認証やクラウド型ID管理の強化から始め、徐々に範囲を広げるのが鉄則です。
従業員へのセキュリティ教育を徹底する
多要素認証やシングルサインオンの仕組みを社内で共有し、セキュリティ意識の向上を図りましょう。また、セキュリティ担当者を配置することで、社内全体でゼロトラストへの理解が深まります。
ゼロトラストの実装が初めての場合は、外部の専門機関に相談するのも有効です。
06 ゼロトラストを実装する際の相談先の選び方

ゼロトラストを実装・運用する際は、以下の3つの相談先を検討しましょう。
ゼロトラスト専門ベンダー
クラウド型ID管理やエンドポイント保護などのソリューションを提供し、実装から運用までを一貫して支援します。
無料トライアルや小規模な検証を活用することで、実際の環境での動作確認が可能です。
セキュリティコンサルティング企業
中立的な立場から課題分析や実装計画、経営層向け資料の作成まで幅広く対応します。製品選定や段階的な実装計画の策定、運用体制の構築などもサポートします。
システムインテグレーター(SIer)
既存システムとの連携やデータ移行、実装後の24時間監視など、技術的なサポートを提供します。自社の環境に合わせた小規模な検証(PoC)から支援してくれるなど、柔軟な導入計画を提案できるSIerを選びましょう。
07 まとめ

ゼロトラストは「信頼せず、常に検証する」を原則とする新しいセキュリティモデルで、従来の境界型対策では防ぎきれないリスクに対応します。
まずはID管理や多要素認証などのアクセス制御から始め、段階的にデバイスやネットワークの保護へと広げるのが効果的です。運用コストや体制面の課題もありますが、計画的に進めることで着実な実装・運用が可能です。
ゼロトラスト型モデルのセキュリティを構築したい場合は、専門ベンダーやコンサルティング企業のサポートを活用するのも一つの方法です。
導入に手間や時間がかけられない場合や運用体制に不安がある場合は、NTTドコモソリューションズにぜひお気軽にご相談ください。