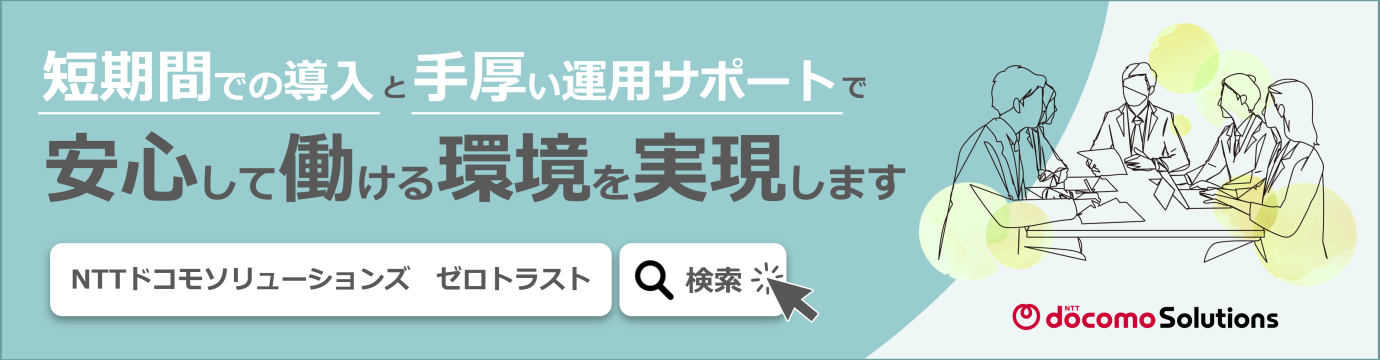VPNの通信速度やセキュリティ上の課題に悩み、ゼロトラストへの移行を検討している方も多いのではないでしょうか。従来のVPNに限界を感じつつも、ゼロトラストの具体的なメリットや導入方法が分からず、判断に迷っている方もいるかもしれません。
本記事では、ゼロトラストとVPNの根本的な違いから、導入ステップ、注意点までを分かりやすく解説します。自社に最適なセキュリティ戦略を明確にし、社内提案の準備を進めたい方は、ぜひ参考にしてください。
01 ゼロトラストとVPNの違いとは?
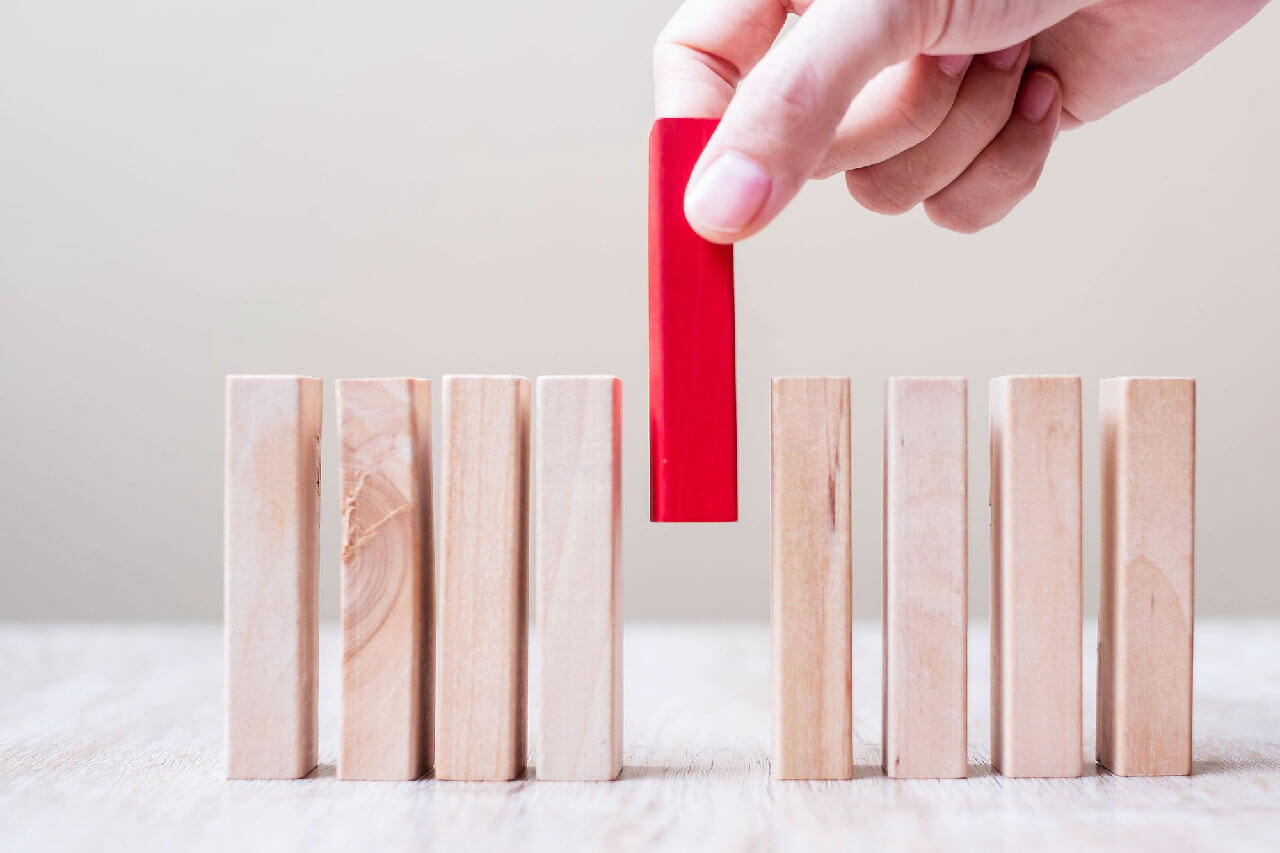
ゼロトラストとVPNは、以下の3つの観点で大きく異なります。
- セキュリティに対する考え方
- アクセス制御の範囲
- 認証方式と検証頻度
従来のVPNは「境界防御モデル」に基づき、一度認証されると、厳密なアクセス制御が設定されていない限り社内ネットワークの広い範囲にアクセスしやすくなる構成が一般的でした。一方、ゼロトラストは「常に検証する」ことを前提とし、ユーザーID、デバイスの状態、接続環境などを都度評価し、必要最小限のアクセス権のみを付与します。
加えて、多要素認証やリアルタイムのリスク検知を組み合わせることで、外部からの不正アクセスや内部不正のリスクを抑制します。クラウド活用やリモートワークが進む現代の業務環境に適したセキュリティモデルといえるでしょう。
02 VPNの課題と企業への影響

VPNは構成や運用が適切でない場合、外部からの攻撃対象となるリスクがあります。特に、脆弱性を突いた不正アクセスやマルウェア感染によって、社内ネットワーク全体が危険にさらされる可能性があります。
また、VPNの通信速度は、VPNゲートウェイの設計やネットワーク帯域の制限によって影響を受けることがあります。特に、同時接続数が多い場合や適切な負荷分散が行われていない場合、接続速度が低下する傾向にあります。これにより業務の処理速度が落ち、従業員の作業効率に悪影響を及ぼすことも少なくありません。
クラウドサービス利用時には、VPN経由の通信がボトルネックとなり、遅延が顕著に現れることで業務の生産性の低下や作業時間の増加につながる懸念もあります。
03 ゼロトラスト導入のメリット
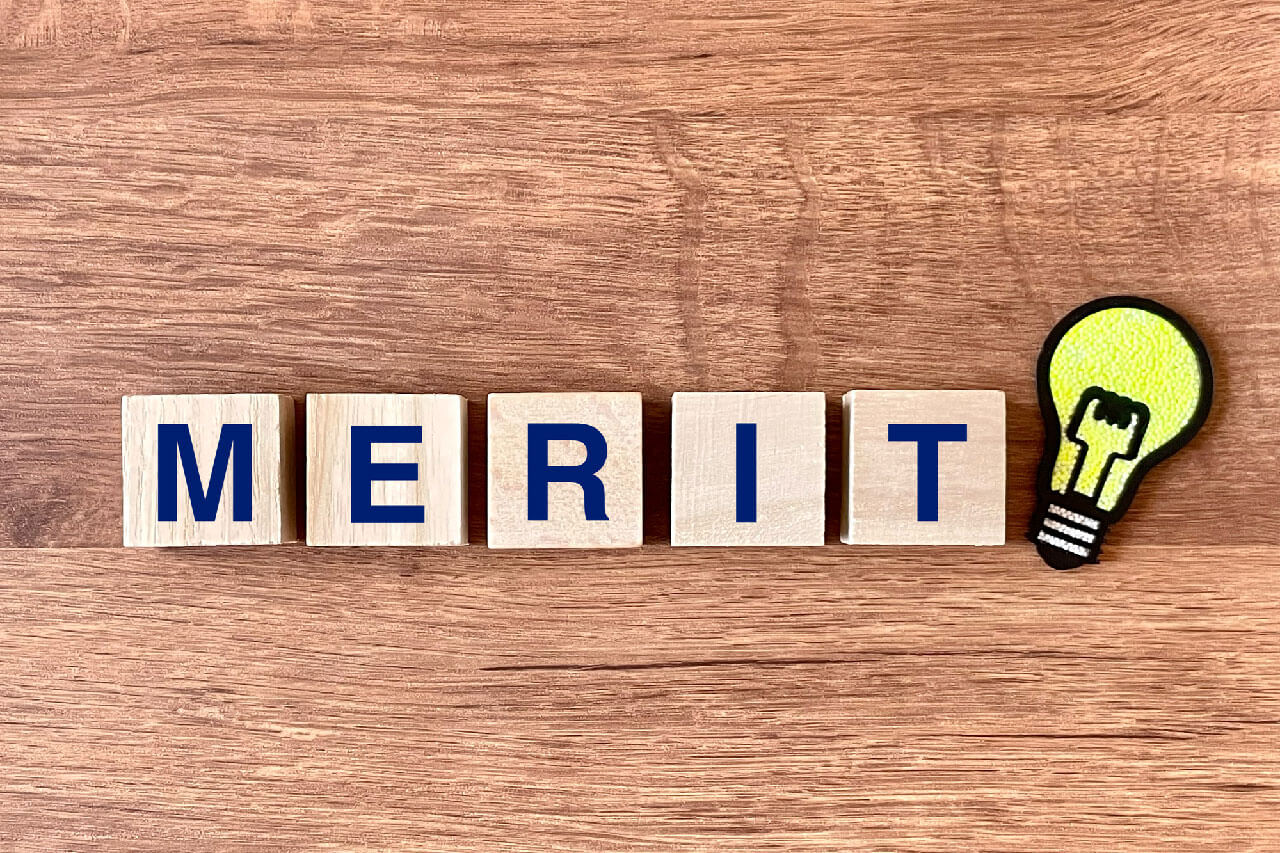
ゼロトラストセキュリティを導入することで、企業が得られる具体的なメリットは主に以下の4つです。
- セキュリティレベルの向上
- ラテラルムーブメント(横方向の不正移動)の抑制
- アクセスログの可視化による監査性の強化
- クラウド活用やDX推進の加速
ゼロトラストでは、ユーザーやデバイスの状態を都度確認し、多要素認証やAIによる異常検知を組み合わせることで、従来のVPNよりも高いセキュリティを実現します。
また、マイクロセグメンテーション(細かい単位でアクセス制御を行う手法)の導入により、万が一侵入された場合でも、ラテラルムーブメントによる他システムへの影響を最小限に抑えることが可能です。
アクセスログを詳細に記録・分析することで、通常とは異なる不審な挙動を早期に検知し、サイバー攻撃や内部不正の兆候を素早く発見できます。また、誰が・いつ・どのデータにアクセスしたかが明確な証跡として残るため、インシデント発生時の原因究明が容易になるほか、コンプライアンス監査への対応力も強化されます。
IDaaSなどの認証基盤と連携しシングルサインオン(SSO)を実現することで、ユーザーは複数のクラウドサービスや業務システムに一度のログインで安全かつ効率的にアクセスできます。これにより認証の手間が減り、業務の利便性が向上し、クラウド活用やDX推進にもつながります。
04 ゼロトラストを導入する場合の注意点

ゼロトラストは高いセキュリティ効果が期待できる一方で、導入にあたっては以下のような課題もあります。
- 初期費用の発生
- 導入計画に必要な期間と体制
- 既存システムとの互換性
- 運用負荷の増加
ゼロトラストは複数の技術を組み合わせるため、導入する製品やサービスの選定が初期費用に大きく影響します。自社のセキュリティ要件と既存システムとの互換性を慎重に見極め、過不足のない構成を検討することが重要です。また、設計や設定には専門知識が求められるため、外部ベンダーの支援コストも考慮した予算計画が不可欠です。
導入プロジェクトは中長期にわたることが多く、設計から展開・検証まで、プロジェクトの規模や体制によって期間は異なります。情報システム部門だけでなく、他部門との連携や外部パートナーとの協力体制も重要です。
また、既存のオンプレミス環境やレガシーシステムとの互換性が課題になることがあります。場合によっては、システム改修や追加投資が必要になるため、事前の調査と計画が欠かせません。
加えて、ゼロトラストではアクセス制御やログ管理が高度化するため、運用負荷が増す傾向があります。これに対応するには、自動化ツールの導入やマネージドサービスの活用、関係者への教育・トレーニングを計画的に進めることが重要です。
05 VPNからゼロトラストへの移行ステップ

ゼロトラストへの移行は、一度にすべてを切り替えるのではなく、段階的に進めることが成功の鍵です。以下の5つのステップを踏むことで、リスクを抑えながらスムーズな導入が可能になります。
現状のセキュリティインフラを分析する
まずは、自社のセキュリティ環境を正確に把握することが重要です。VPNの利用状況、アクセス権限の管理方法、インシデント履歴などを調査し、どこに課題があるかを明確にします。
必要なツールと技術を選定する
次に、自社の要件に合ったゼロトラスト関連技術を選びます。ZTNA、IDaaS、SASEなどの選択肢があり、クラウド型かオンプレミス型か、既存システムとの互換性、コストなどを総合的に検討する必要があります。
優先度の高い領域から導入する
すべてのシステムを一度に切り替えるのは現実的ではありません。まずはテレワーク環境や外部アクセスが多い領域など、リスクの高い部分からゼロトラストを適用し、段階的に範囲を広げていきましょう。
監視体制を整え、継続的に改善する
導入後は、アクセスログの分析や異常検知の精度向上など、継続的な監視と改善が不可欠です。セキュリティポリシーの見直しやKPIの設定も、運用の質を高める上で重要です。
社内教育を実施する
ゼロトラストは従来のVPNとは運用方法が異なるため、社員への教育が欠かせません。多要素認証や新しいアクセスルールを理解してもらうために、オンライン研修やワークショップを活用し、社内全体のセキュリティ意識を高めましょう。
06 ゼロトラストとVPNの今後の関係性

ゼロトラストは、従来のVPNが抱えるセキュリティ上の課題を補完・解決する新しいアプローチとして注目されています。VPNは一度認証されると社内ネットワーク全体へのアクセスが可能となる構成が一般的であり、万が一侵入された場合、被害が広範囲に及ぶリスクがあります。また、機器の脆弱性や通信速度の低下、クラウドサービスとの相性の悪さなども課題として挙げられます。
一方、ゼロトラストは「常に検証する」という原則に基づき、ユーザーやデバイスの状態を都度評価し、必要最小限のアクセス権のみを付与します。これにより、外部からの攻撃だけでなく、内部不正やラテラルムーブメント(横方向の不正移動)のリスクも抑えることができます。
ただし、すべての環境を一度にゼロトラストへ移行するのは現実的ではありません。重要な業務システムや外部アクセスが多い領域からゼロトラストを導入し、既存のレガシー環境にはVPNを併用するのが実用的です。
このような段階的な移行により、セキュリティの強化と業務の安定性を両立させながら、将来的にはゼロトラストを基盤としたセキュリティ環境への完全移行を目指すことができます。
07 まとめ

ゼロトラストとVPNの併用は、現実的かつ柔軟なセキュリティ戦略として、企業のセキュリティ強化の選択肢となっています。特に、クラウド活用やリモートワークが常態化する中で、従来のVPNだけでは対応しきれない課題が顕在化しており、ゼロトラストの導入は企業の持続的な成長とセキュリティ強化に向けた重要な選択肢となっています。
NTTドコモソリューションズでは、ゼロトラスト型セキュリティの導入・運用に関する豊富な実績を活かし、あらかじめ設計・テンプレート化されたサービスを提供しています。複雑な初期設計の負担を軽減しながら、短期間での導入を可能にしています。
また、セキュリティオペレーションセンター(SOC)による監視・運用支援や、Microsoft 365(※)との連携による不正アクセス対策など、実用的な機能も備えており、日々の運用負荷を軽減しながら、セキュリティレベルの向上を図ることが可能です。
セキュリティ課題の解決に向けて、ゼロトラストの導入を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。
※Microsoft 365は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国々における登録商標または商標です。