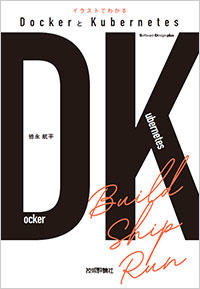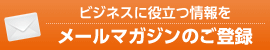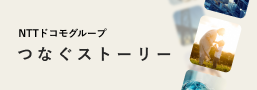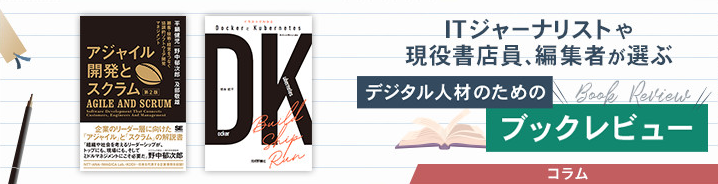
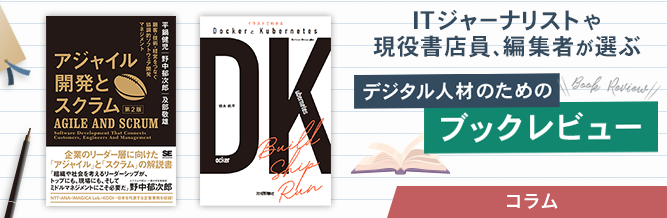
今月の書籍
レビュワー:新野 淳一
- 『アジャイル開発とスクラム 第2版 顧客・技術・経営をつなぐ協調的ソフトウェア開発マネジメント』
- 『イラストでわかるDockerとKubernetes』
この分野の解説書籍として最も信頼できる一冊。
あらゆる層のビジネスマンにとって読む価値がある
現代の企業においては、ITを活用できるかどうかが成否を大きく左右することが強く意識されるようになった。そのなかでビジネスとITとの架け橋たる主要なアプローチとして理解しておきたいのがアジャイル開発と、その代表的な手法であるスクラムだ。
そもそも、スクラムの基礎となった野中郁次郎氏と竹内弘高氏による1986年の論文「The New New Product Development Game」は日本企業のベストプラクティスについて研究したものであり、スクラムを知ることはビジネスにおけるベストプラクティスのエッセンス的手法を知ることと言ってよいだろう。
本書の著者の一人としてその野中郁次郎氏が名前を連ねており、本書が技術者向けの実践的な解説にとどまらず、企業における知識創造、リーダーシップ、組織運営、そして経営においてアジャイル開発やスクラムがどういった意味を持つか、野中氏自身による解説はあらゆる層のビジネスマンにとって読む価値があるといっても過言ではない。
と同時にアジャイル開発とスクラムはクラウドやDevOps、テスト駆動開発、ペアプログラミングなどITの最新動向を巻き込んだ進化をしてきた。本書はそうしたITの、特に開発現場における最新動向と具体的実践についての解説も抜かりなく、企業による事例も豊富に取り上げている。日本語で平易に書かれたアジャイル開発とスクラム解説本としてもっとも信頼できる一冊と言えよう。
『アジャイル開発とスクラム 第2版 顧客・技術・経営をつなぐ協調的ソフトウェア開発マネジメント』
著者:平鍋 健児、野中 郁次郎、及部 敬雄
出版社:翔泳社
豊富な図解を駆使して、新技術の基礎を分かりやすく解説。
短時間で的確に学べる
現在、仮想化がITインフラにとって当然の機能として用いられているように、近い将来、ITのインフラのほとんどはDockerとKubernetesが当然のように用いられると見られている。そのため、ソフトウェアの開発に携わる方であれば、たとえ現時点で仕事に関係なくともDockerとKubernetesについて理解しておきたいと考える方は多いだろう。
本書はそうした、DockerとKubernetesをこれから理解したい方にとって適切な解説書だ。
本書の優れた点は3つある。1つ目は、タイトルにあるようにイラストによる解説があることだ。実際にコマンドラインからDockerやKubernetesを操作することで使い方を学ぶことはできるが、その内側で何が起きているかまでをそこから知ることは難しい。内側の仕組みや階層構造がどのようになっているのかがイラストで示されることで、内部の理解を深めることが容易になる。
2つ目は、DockerやKubernetesについてどこまで詳しく知るべきなのか、指針が得られる点にある。IT技術の多くに当てはまるが、詳しく調べていくときりがない。特にDockerとKubernetesは複雑な階層構造を内部に抱えている。それらによるメリットと構造、そして基本的な使い方やコマンドなど、著者により初学者向けに適切に切り分けられていると言える。
そしてこれらの情報が正味130ページ程度の、おそらく目を通すだけなら1~2時間で済む情報量としてまとまっている見通しの良さが3つ目の優れた点として指摘できる。その上で、コマンドを試しながら手を動かしてじっくりと使い方を学ぶためのガイドとしても有用だ。
DockerとKubernetesは、やや落ち着いてきたとはいえ技術の変遷の流れの速い部分に位置する技術。その基礎を短時間でしっかり学べる本書の価値は高く評価できる。
今月のレビュワー

新野淳一 (にいの・じゅんいち)
ITジャーナリスト/Publickeyブロガー。一般社団法人クラウド利用促進機構(CUPA)総合アドバイザー。日本デジタルライターズ協会代表理事。大学でUNIXを学び、株式会社アスキーに入社。データベースのテクニカルサポート、月刊アスキーNT編集部副編集長などを経て1998年フリーランスライターに。2000年、株式会社アットマーク・アイティ設立に参画。2009年にブログメディアPublickeyを開始。2011年「アルファブロガーアワード2010」受賞。
2021/05/31