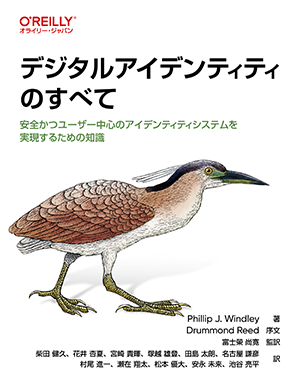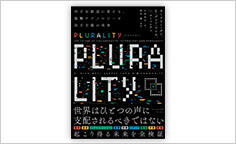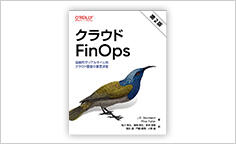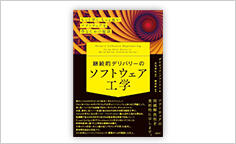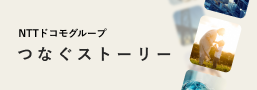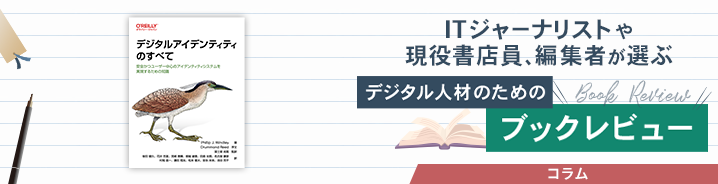
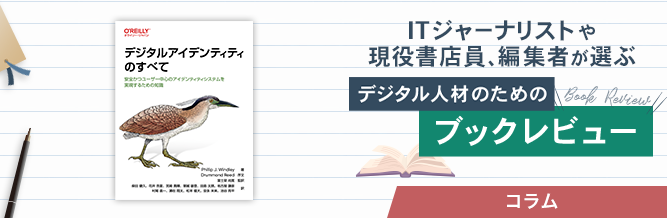
今月の書籍
レビュワー:高橋 征義
- 『デジタルアイデンティティのすべて ―安全かつユーザー中心のアイデンティティシステムを実現するための知識』
現代的なアイデンティティシステムと、将来あるべきそれを体系的に学ぶ
本書は「アイデンティティシステム」の設計に必要な知識を伝える書籍である。本書で参照される「アイデンティティ」と「アイデンティティシステム」の定義は以下の通りである。
「アイデンティティとは、特定の人や物を認識し、記憶し、反応する方法である。アイデンティティシステムは、主体、識別子、属性、生データ、コンテキストの情報資産を取得し、関連付け、適用、推察し、管理する」
少し分かりにくいかもしれないが、つまり、人やモノに対して「この人はAさんである」「Aさんは過去にN回アクセスしている」「AさんはBは変更できるがCは変更できず、Dは閲覧もできない」「このモノはすでに登録済みのXであり、Xに関連する情報はYの権限を持っていれば検索可能である」といったことをできるようにする基盤となるのが、アイデンティティとアイデンティティシステムである。
この記事を読まれている方であれば、日々何かしらのアイデンティティシステムに触れているだろう。スマートフォンを利用するときにも、メールやチャット・メッセージングサービスを読み書きする際にも、あるいは本サイトにアクセスする際にも、そこには「アイデンティティ」があり、それは誰かが設計したものである。そしてアイデンティティはシステムやサービスそのものの根幹に関わる要素であるため、システムのアーキテクチャ設計にも深く関わっている。
アイデンティティシステムについての書籍はすでに多数刊行されているが、特定の技術に焦点を当てた書籍や、セキュリティ面に特化した書籍が多い印象がある。単一で限られた情報を扱うシステムでは技術的な側面を中心に考えればよかったからかもしれない。しかしデジタルサービスが広く普及した現在では、ユーザー体験やプライバシー、法令といった非技術的側面も無視できない。さらに技術的にもシステムやサービスにまたがりアイデンティティとその属性を相互に活用し合うことが試みられるなど、適切な設計と実装の難易度は高まっている。
そういった需要に応えるべく、本書の扱う領域は広範にわたる。名前と識別子、PKI(公開鍵基盤)、証明書、暗号、ディレクトリ、認証、アクセス制御、クレデンシャル、フェデレーション、アイデンティティウォレット、ガバナンスや監視資本主義まで、「デジタルアイデンティティのすべて」という日本語版タイトルも大げさではないほど、網羅的な内容になっている。また個々のアイデンティティシステムをまたがったアイデンティティメタシステムを前提とする第4章など、抽象度も高い。
アイデンティティの理解をおろそかにした設計は、思わぬ不具合や運用上のリスクにつながりかねない。現代的なシステムを持続的に運用していく上で、本書の知見は有益な指針となるだろう。また自己主権型IDや分散型ID、Verifiable Credentialsといった将来のための技術についてのまとまった解説も貴重である。
デジタルアイデンティティに興味のある方はもちろん、一般的なサービスやシステムを設計・運用している方にも本書を勧めたい。
『デジタルアイデンティティのすべて ―安全かつユーザー中心のアイデンティティシステムを実現するための知識』
著者:Phillip J. Windley
監訳:富士榮尚寛
翻訳:柴田健久、花井杏夏、宮崎貴暉、塚越雄登、田島太朗、名古屋謙彦、村尾進一、瀬在翔太、松本優大、安永未来、池谷亮平
出版社:オライリー・ジャパン
今月のレビュワー

高橋 征義(たかはし・まさよし)
札幌出身。Web制作会社にてプログラマとして勤務する傍ら、2004年にRubyの開発者と利用者を支援する団体、日本Rubyの会を設立、現在まで代表を務める。2010年にITエンジニア向けの技術系電子書籍の制作と販売を行う株式会社達人出版会を設立、現在まで代表取締役。著書に『たのしいRuby』(共著)など。好きな作家は新井素子。
2025/10/15