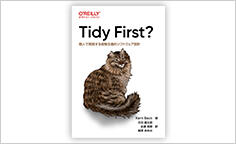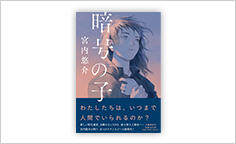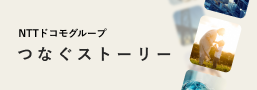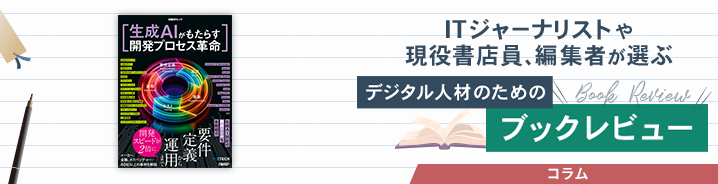

今月の書籍
レビュワー:新野 淳一
- 『生成AIがもたらす開発プロセス革命』
先進の業界動向を知って、今後の開発の方向性を決定する一助となる一冊
人間が言葉で指示するとプログラムが自動的に生成される、という技術はすでに未来のものではなくなっている。GitHub CopilotやDevinといった生成AIを活用したコーディングアシスタントやコーディングエージェントが次々に登場し、システム開発の現場で使われ始めているのだ。
本書は、そうした生成AIを活用したシステム開発をいちはやく取り入れた現場での事例、サービスの動向、そして生成AIによるシステム開発の展望などをまとめたものである。
なぜ本書の内容が重要なのかと言えば、本書のタイトルにあるようにシステム開発における生成AIの活用は、プログラミングの効率化にとどまらず、これまで行ってきた開発の工程(プロセス)そのものを変革する可能性が高いことが分かってきたからだ。
当初、システム開発における生成AIの活用は、書きかけのコードを補完したり、コメントを元にコードを生成したりしてくれるものであり、人間のプログラマがコードを書くスピードをさらに速く、効率的にするものとして注目された。
しかし本書では、例えばサイバーエージェントは多くの工数がかかるテスト工程を生成AIによって自動化する取り組みや、企画書や仕様書を基に生成AIが自動的に実装しテストを行うことによる効率化を紹介している。あるいは博報堂DYホールディングスの最高AI責任者の肩書きを持つ森 正弥氏は、ハルシネーションの影響を受けるコード生成よりも、システムの質を高めるために生成AIによるチェックなどを活用する方が効率的に寄与するのではないかとの見方を示した。
このように本書は先進的なユーザーがコーディング以外でも積極的に生成AIを活用することで、より競争力の高いシステム開発を進めようとしているさまざまな事例を紹介している。こうした中から生成AIを用いた新たな開発プロセスを各社が模索している様子がうかがえる。
後半ではサービスを提供するベンダー側の動向や、生成AIによってシステム開発のハードルを下げ、ユーザー企業における内製が活発化すること、そしてシステム開発を本業とする大手システムインテグレータによる生成AIの活用なども紹介されており、生成AIが業界構造の変化を引き起こしつつあることを俯瞰する視点も得られる。
いま多くのIT系企業で、生成AIツールの導入が検討されているだろう。本書はそうした際の参考に、あるいは導入を進める上での上司への説得材料などに使えるはずだ。
今月のレビュワー

新野 淳一(にいの・じゅんいち)
ITジャーナリスト/Publickeyブロガー。一般社団法人クラウド利用促進機構(CUPA)総合アドバイザー。日本デジタルライターズ協会代表理事。大学でUNIXを学び、株式会社アスキーに入社。データベースのテクニカルサポート、月刊アスキーNT編集部副編集長などを経て1998年フリーランスライターに。2000年、株式会社アットマーク・アイティ設立に参画。2009年にブログメディアPublickeyを開始。2011年「アルファブロガーアワード2010」受賞。
2025/05/21