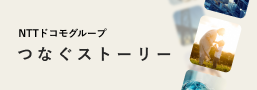プロを目指すなら、めげないことも一つの才能
― 高校を卒業した頃には、もう音楽の道でプロになるという意識があったのでしょうか?
そうですね。高校2年の時に、師匠である中川イサトさん(以下、イサトさん)のギター教室に通い始めたんです。イサトさんは『赤い風船』の元ギタリストで、関西フォークの草分け的存在。イサトさんが出された教則本も完璧にマスターして門を叩きました。ところが、イサトさんはすでに、全く新しい奏法を取り入れていたんです。以前はブンチャ、ブンチャ、とリズムを刻むラグタイムギターのような弾き方だったのが、ギターのチューニングをブンブン変えて、バーンと弦を叩くような斬新な奏法で、今までとは違う次元の、いわゆるニューエイジミュージックとかヒーリングミュージックの走りともいえる音楽でした。イサトさんの音楽は、インストゥルメンタルとの出会いでもありました。アコースティックのギター演奏だけで、こんなにかっこいいことができるのかと、のめり込みました。
― 押尾さんの多彩なギターサウンドの原点ですね。
イサトさんと出会ったことが人生の節目となりました。師匠でありアイドルでもあります。その後、東京の音楽専門学校に通うようになったのですが、東京に行くならということで、イサトさんが岡崎倫典さんを紹介してくれました。倫典さんは当時からギターインストゥルメンタルの楽曲をたくさん作られていて、イサトさんと同じくパイオニア的な存在でした。東京に行った頃は、周りからも「ギターうまいね」と言われるようになり、ギターを弾くのが楽しくて、楽しくて。でも倫典さんからは「モノを作る人になれ」と言われていました。というのも僕は人の曲のコピーばかり演奏していて、オリジナル曲がありませんでした。でも楽しかったし、それでいいじゃないかと思っていました。
そんな折りに、ひょんなことからバンドを組むことになり「バンドで成功したい!」と思うようになって、作曲をする必要に迫られたわけです。ボーカルが歌詞を書いて僕が曲を作る。すると、あろうことかその作業がおもしろくて。倫典さんの言っていた「モノを作る人になれ」とはこういうことかと、ようやく理解できました。倫典さんは、新しいものを生み出すという感覚、そして既存の曲に似ていたとしても、コピーではない自分のオリジナルを作り出すことの大切さを、僕に実感してほしかったのだろうと思います。次々とデモテープを作り、レコード会社に送りまくった時期でした。
― バンドデビューを目指していたとは、ちょっと意外です。

でも、実はその時にやっていたのはギターではなくベースです(笑)。他にベースをやる人がいなかったからですが、その時はギターかベースかというこだわりは特になく、バンドをやることに夢中でした。20歳から27歳まで、ずっとそんなことを続けていました。鳴かず飛ばず、でしたけど。ライブのチケットが売れなくて自分たちで買い取るような、赤字バンドでした。
30歳に近づくと周囲のバンド仲間からも、辞めたり解散したりという話が聞こえ始めました。そういうことが重なると、ふつうは迷ってへこむんですよ、バンドマンも。ところが僕はちっとも不安に思わなかった。根拠のない自信というか、音楽で食べていきたいという情熱だけは人一倍強かったのでしょう。
― 音楽の道しか考えられなかったのですね。
就職するなら、その職業で骨を埋めたいタイプなんです。就職して音楽を続けるとなると、どちらも中途半端になってしまう。だから30歳になっても、もうちょっと音楽で頑張りたいと思っていた。いい年になっても、へこたれず不安にもならなかったことが、一つの才能かもしれませんね。
「わかるやつだけわかればいい」では、人がついてこない
― 現在の押尾さんの演奏スタイルは「本当にギター1本?」と耳を疑うくらい、アップテンポからバラードまで曲調は幅広く、まるで複数の楽器で演奏しているかのような変化に富んだ音色に驚かされます。このスタイルはどのようにして築き上げられたのでしょうか?
バンドが解散してから、原点であるアコースティックギタリストとして、他のミュージシャンのライブやレコーディングに参加するなど、仕事の声がかかるようになりました。カントリーロック調にしたいロックバンドや、タンゴのバンド、アイリッシュバンドなど、アコースティックギターはわりと需要があったんです。
そうした経験を積む中で、ミュージシャンとしての姿勢をいろいろと考える機会も生まれました。ミュージシャンの中には「わかるやつだけわかればいい、俺たちはやりたい音楽をやる」という硬派なタイプもいます。しかし、お客さんが誰もついてこなければチケットも売れません。やはりお客さんあっての世界ですから、それは違うんじゃないかと思ったんです。独自のスタイルを貫きつつ、お客さんが求めるものに応えられるギタリストになりたいと僕は思うんです。
― お客さんの目線で考えることも必要ということですね。
サポートギタリストとしての活動の合間に、ソロギターのライブ活動もマイペースで始めていました。いろいろなバンドが出演するイベントに出ると、バンドは音圧があってサウンドに迫力があるし、女の子からキャーキャー言われている。盛り上がっていいな、と客席を見ていると、お目当てのバンドが終わったら、お客さんがぞろぞろと退場していくんですよ。「これはまずい!次が出番なのに!」と慌てました。普通に出て行って「押尾コータローです、聴いてください。ポロローン」なんてアコースティックギターを弾き始めても、地味すぎて間違いなく全員が帰ってしまう。「わかるやつだけ」なんて言っていられないわけです(笑)。どうしたら聴いてもらえるか必死で考えて知恵をしぼりました。