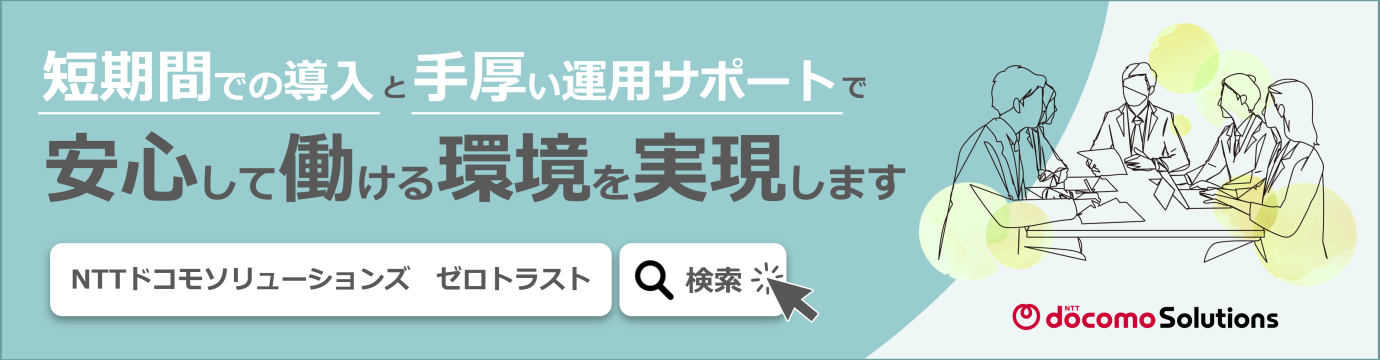- そもそもエンドポイントセキュリティとは何か
- エンドポイントセキュリティが必要とされる理由を知りたい
- エンドポイントセキュリティを理解するために必要なキーワードを整理したい
昨今テレワークの普及など、企業のセキュリティ環境が大きく変化してきました。
また、サイバー攻撃の高度化や内部不正の増加で、セキュリティ対策の難易度はますます上がっています。
この状況で、セキュリティ対策のキーワードとして「エンドポイントセキュリティ」が注目されてきています。
本記事では、エンドポイントセキュリティの意味、必要とされる理由、理解するために必要なキーワードを紹介します。
エンドポイントセキュリティとは
-
エンドポイントセキュリティの「エンドポイント」は、「末端」、「終点」を意味する言葉です。セキュリティ用語ではネットワーク末端のPC、スマートフォンなどの端末を意味します。
エンドポイントセキュリティとは、エンドポイント自体やエンドポイントに存在する情報を、攻撃から守るセキュリティ対策のことです。
企業の規模を問わず、今やどの企業もサイバー攻撃を受けるリスクがあります。また、社外からの攻撃だけでなく、内部不正も大きな脅威になってきました。
このような状況下で、多くの企業ではサイバーセキュリティの最前線にエンドポイントセキュリティを配備しており、企業ネットワークを保護する最初の防御層としているのです。

エンドポイントセキュリティとアンチウイルスソフトとの比較
-
従来、PCなどにインストールするソフトは、アンチウイルスソフトが中心でした。これは、ウイルス感染やマルウェアのインストールを防止するものです。
それには、ウイルス感染やマルウェアを社外との境界で食い止めることや、感染した瞬間に感染を検知して駆除・隔離することが有効とされてきました。
しかし、アンチウイルスソフトには限界があります。
ウイルスの検知には、それぞれのウイルスの特徴を把握してパターンファイルを用意する必要があります。
そのパターンファイルの構築には時間がかかるため、最新のパターンファイルが適用されるまでの間に侵入される可能性があります(ゼロデイ攻撃)。
これに対し、エンドポイントセキュリティでは端末を守ることに主眼が置かれています。
ウイルスやマルウェアに侵入される前提で、ウイルスの検知や検知後の封じ込め・復旧・暗号化などによって、ウイルスやマルウェアの被害を抑えます。
ファイアウォールなど侵入を防ぐ「入口対策」に対して、エンドポイントセキュリティは「出口対策」とも言われています。
アンチウイルスソフトとエンドポイントセキュリティの両方を導入することで、企業はよりセキュリティを強化できるのです。

エンドポイントセキュリティが必要とされる理由
-
昨今、エンドポイントがターゲットにされることが増えてきており、エンドポイントセキュリティの必要性が増大しています。
ここでは、エンドポイントセキュリティが必要とされる理由を以下の順に紹介します。
- 環境変化に伴うエンドポイントの増加
- サイバー攻撃の高度化
- 内部不正のリスク防止
環境変化に伴うエンドポイントの増加
エンドポイントセキュリティが必要とされる理由の1つ目は、テレワークの普及による環境変化です。
昨今、新型コロナウイルス感染症対策などにより、テレワークの普及が急速に進んでいます。
東京都産業労働局の調査によると、2021年4月時点で、従業員300人以上の企業においてテレワーク普及率は79.3%にまで達しました。
テレワークの普及によって、企業の環境は大きく変化しました。
例えば、PCの持ち出しやモバイル端末から社内ネットワークにアクセスすることが増えました。
また、私物の端末で業務を行う、BYODでテレワークを実施する事例も増えてきました。
これらの要因により、エンドポイントが増加しています。このことは、攻撃対象になりうる端末が増えて、セキュリティリスクが増大している理由ともなっているのです。
また、無線LANやクラウドサービスの普及によって、社外から社内ネットワークへのアクセスが当たり前になっています。
以上のことから、社内と社外の境界がなくなり、境界型セキュリティだけを用いたセキュリティ対策は限界を迎えているのが現状です。
そのため、エンドポイントにおいてもセキュリティ対策を強化することが求められているのです。
サイバー攻撃の高度化
エンドポイントセキュリティが必要とされる理由の2つ目は、サイバー攻撃の高度化です。
サイバー攻撃の手口や種類は、高度化・巧妙化を続けています。マルウェアが検知を回避する能力も向上しています。
そのため、アンチウイルスソフトや、セキュリティパッチだけではエンドポイントへの攻撃を防ぎきれない事象も起こってきました。
1つの端末がマルウェアに感染しただけで、社内ネットワークを通じて他のエンドポイント群にも感染する恐れがあります。
そのため、マルウェアの感染を予防するだけではなく、エンドポイントに攻撃が加えられた時にどう対処するかも重要になってきたのです。
内部不正のリスク防止
エンドポイントセキュリティが必要とされる理由の3つ目は、内部不正のリスク防止です。
近年、セキュリティ対策においては外部からの攻撃だけでなく内部不正への対策も重要になってきました。
内部不正によって機密情報や個人情報の持ち出し・漏えいが発生すると、企業経営に大きな影響を与えます。
実際、情報処理推進機構(以下、IPA)の情報セキュリティ10大脅威 2021では、内部不正が組織部門の6位にランクインしました。
エンドポイントセキュリティを強化することにより、内部不正のリスクを防止して情報漏えいを防ぐことが、企業経営を守ることにもなるのです。

エンドポイントセキュリティを理解するためのキーワード
-
エンドポイントセキュリティを強化するには、PCやスマートフォンのロック、アクセス管理に加えて、理解したいキーワードがあります。
ここでは、エンドポイントセキュリティを理解するためのキーワードを以下の順に紹介します。
- EPP(アンチウイルスソフト)
- NGEPP・NGAV(マルウェア検知ソフト)
- EDR(サイバー攻撃対策ソフト)
- DLP(情報漏えい対策)
EPP(アンチウイルスソフト)
エンドポイントセキュリティを理解するためのキーワードの1つ目は、EPP(アンチウイルスソフト)です。
EPP(Endpoint Protection Platform)は、既知のマルウェアを検知し、攻撃を阻止・修復します。
エンドポイントにダウンロードするファイルをスキャンして、既知のマルウェアのパターンからマルウェアを検知します。
ただし、未知のマルウェアは検知できないことには注意が必要です。最近では、クラウドサービスによりライブラリが自動更新されるものが多くなっています。
NGEPP・NGAV(マルウェア検知ソフト)
エンドポイントセキュリティを理解するためのキーワードの2つ目は、NGEPPとNGAV(マルウェア検知ソフト)です。
NGEPP(Next Generation Endpoint Protection Platform)とNGAV(Next Generation Anti-Virus)は、いずれも「振る舞い検知」によりマルウェアを検知します。
「振る舞い検知」とは、通常のプログラムとは異なる、マルウェア特有の構造や動作をもとに、不審なプログラムを検知することです。
この特性により、未知のマルウェアにも対処できることが特徴です。
EDR(サイバー攻撃対策ソフト)
エンドポイントセキュリティを理解するためのキーワードの3つ目は、EDR(サイバー攻撃対策ソフト)です。
EDR(Endpoint Detection and Response)は、侵入したマルウェアの検知・拡散防止・除去を行います。
いくらセキュリティを強化しても、マルウェアの侵入をゼロにすることは事実上不可能です。
EDRを用いることでマルウェアが侵入してもその被害を軽減できるため、EPPやNGEPPと、EDRとを組み合わせて使うと、よりセキュリティを強化できます。
DLP(情報漏えい対策)
エンドポイントセキュリティを理解するためのキーワードの4つ目は、DLP(情報漏えい対策)です。
DLP(Data Loss Prevention)は、エンドポイントやネットワーク上のデータを常時監視します。
エンドポイントやネットワーク上のデータに不審な動作が確認できた時には、アラートを出したり、不審な動きを阻止したりします。
DLPにより、社外からのサイバー攻撃だけでなく、社内からの情報漏えい・持ち出し・誤動作なども防止できます。

まとめ
-
本記事では、エンドポイントセキュリティの意味、必要とされる理由、理解するために必要なキーワードを紹介しました。
セキュリティ対策は日々進歩していますが、同時にサイバー攻撃も高度化しています。
それに伴い、今後エンドポイントセキュリティの重要性はますます高まると予想されます。