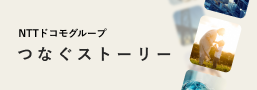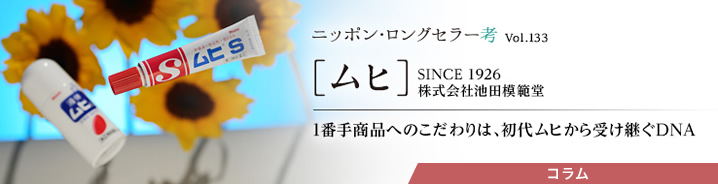

時代の先を読み、2度の転身

ワセリン基剤の軟膏から、夏でも溶けにくいクリーム基剤とすることで使いやすくなり、大ヒットした昭和初期の「ムヒ」
連日の真夏日や熱帯夜が珍しくなくなった日本の夏。暑さもさることながら、人々を悩ませるのが虫刺され。2014年夏、約70年ぶりにデング熱の国内感染が見つかり大騒ぎになったが、どこにでもいるヤブ蚊がウイルスを媒介するのだから、今年も油断はできない。予防策として虫よけ剤を使用することはもちろん、いち早く止めたいかゆみの強い味方が、虫刺され・かゆみ止め薬「ムヒ」。この「ムヒ」を製造・販売しているのが富山県の企業、株式会社池田模範堂だ。富山といえば置き薬で有名だが、同社も家庭配置薬の販売からスタート。池田嘉市郎が1909(明治42)年に創業した、100年カンパニーである。

昭和20年代、海水浴場の監視台に掲示された「ムヒ」の広告
大正中期、ちまたでは外傷・肌荒れに効く軟膏(こう)が評判になっていた。2代目の池田嘉吉も薬の製造を思い立つが、それと同じでは能がない。頭を悩ませた結果、使用頻度の高い「虫刺され・かゆみ止め」を薬効の主点とすることとした。1926(大正15)年に発売した「ムヒ」はブリキ缶入りのワセリン軟膏。これを持って静岡へ行商に行くと、当時、東海道一帯では「カユガリ病」という奇病が流行していたこともあって、「ムヒ」はたちまち大評判となった。 その後、1927(昭和2)年に容器を当時としては珍しいチューブ型とし、1931(昭和6)年には新処方の白いクリーム状の「ムヒ」を発売して爆発的なヒットとなる。

昭和20年代後半、人気商品「ムヒ」にはニセモノが続出。薬局薬店に向けに注意を喚起したDM
戦後、流通構造が変化し、薬局薬店での販売が伸長する中、「あの『ムヒ』をうちでも」と、全国から取引依頼が殺到した。これほど「ムヒ」が有名なのは、同社が当初より広告宣伝に関して人一倍積極的に取り組んできたからだ。配置薬のオマケはもちろん、ほうろう看板や折り込みチラシ、海水浴場での広告など、徹底的に「ムヒ」を宣伝。それが、配置販売から薬局販売に転換する際に功を奏した。
嘉吉には豪快なエピソードが残されている。流通の転換を見て、「これからはマスメディアの時代だ」と確信した嘉吉は、日本電報通信社(現・電通)の門をたたく。白米や現金で支払うことを条件に、自ら広告スペースの獲得に乗り出したのだ。背に現金入りのリュックサック、足にはゲートル……、夜汽車に揺られて富山と東京を往復する嘉吉。そんな熱意が通じ、「ムヒ」は東京の大企業と肩を並べて広告を打つことが可能となった。終戦からわずか2年後のことである。
池田模範堂は創業から約40年の間に、卸売業から製造業へ、配置販売から薬局販売へ、2度の転身を遂げた。それはまさしく嘉吉の先見性の高さを裏付けるものといえるだろう。