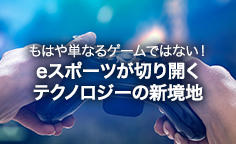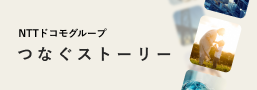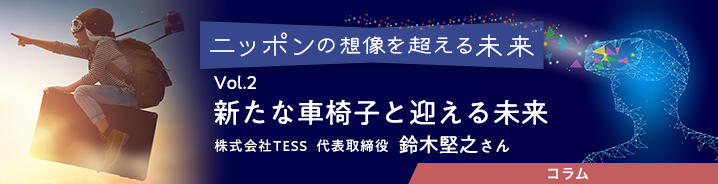
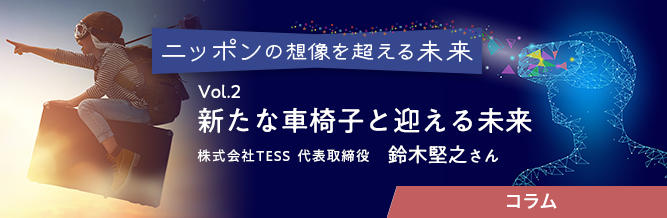
100年後。想像を超える車椅子がもたらす〝楽しみ〟とは。
下校中の親子連れの一コマ。
(プロローグ)
親:今日は、お友達と〝VR宝探し〟をする約束をしているの?
子ども:うん、僕のスケジュールは、昨日、クラウドの予定表に書いておいたけど、もう見たんだね。転校生の子とも遊ぶ約束をしているんだ。
親:ああ、ゲームがすごく上手っていうお友達ね。
子ども:そうそう。今日はVRで渋谷の街の中でヒントを集めて宝探しするんだ。転校生の子は足が不自由で自分用の車いすを持っているんだけど、この前も一番でクリアしてたんだよね。
親:すごいね。昔は車いすっていうと体の不自由な人が移動するための道具でしかなかったよ。通信でつなげてゲームをしたり、皆で一緒にサイクリングに行ったりできる道具になるなんて、誰も想像していなかったな。今じゃ、自転車みたいな乗り物で、一家に一台はあるもの、色々なエレベーターもそのまま乗れるようになっていて。
子ども:へえ。そうなんだ。じゃ、遊びに行ってくるね!今日は負けないよ!
想像を超える未来へと挑む車椅子の現在へ
▼
麻痺があっても自力で動かせる!既成概念を覆した足こぎ車いす

「車いす」と聞くと何をイメージするだろうか?
介護者に押してもらう一般的なタイプや電動タイプの他にも、パラリンピックでもおなじみ、競技用の独自なデザインなど、日常生活の中でもさまざまな場面での車いすを見る機会が多くなってきた。
ここに、もうひとつご紹介したいものがある。福祉用具のイメージを変えた〝自らこぐ〟ペダル付の足こぎ車いす「COGY(コギー)」だ。優れたデザインは、2016年度「BBC NEWS 世界の最も美しい自転車トップ10」に選出され、「グッドデザイン金賞(経済産業大臣賞)」など数々のデザイン賞を受賞していることからもわかる。
今回は、この「COGY」を取り扱う、株式会社TESSの鈴木堅之さんに、COGYの特長や、将来の「車いす」と「人」との関係などについてお話を伺った。

麻痺(まひ)などの歩行障がいがあっても、自力でペダルを踏んで移動ができる――ヒトに備わった原始的な脊髄反射を活用した足こぎ車いすが、国内外で関心を集めている。
歩けない人が自力でペダルを踏んで進む車いすとはどういうことか?
COGYの公式サイトには、歩行障がいのある方たちが初めてCOGYに乗った時の様子が動画で公開されている。事故による下半身麻痺、先天性の全身麻痺、脳梗塞の後遺症など、歩けない事情も年齢もさまざまな男女が、普段乗っている車いすからCOGYに乗り換えた瞬間は、まだぎこちない。ところが、少し練習してコツをつかむと、自分の足でテンポよくペダルを踏み込み、スイスイと移動できるようになるのだ。本人や介助者の表情から、“自分で足を動かす”ことの感動と喜びが伝わってくる。

この車いすの構造は非常にシンプルだ。電動でもなければ、最先端のIT技術を搭載しているわけでもない。座面とペダルの距離と角度に秘密がある。
ヒトには生まれつき「片方の足を動かしたあとは、もう片方が動く」という原始的な歩行反射の機能が備わっている。新生児の上半身を抱きかかえて足を床につけると、左右の足を交互に動かし、歩くような動作をするのをご存知だろうか。足を動かした刺激が脊髄に伝わり、原始的歩行中枢から「交互に足を動かす」という反射的な司令が出るためだ。COGYの座面やペダルは、この反射運動を引き出すことでペダルがこげるように設計されている。
シンプルだが、いたるところに入念な工夫をしていると鈴木さんは話す。「座ってみると、ちょっと窮屈に感じるかもしれませんが、この姿勢、この角度が反射運動を引き出すポイントなんです。ペダルは非常に軽く、足を置いた重みだけで踏み込むかたちになるので、わずかでもペダルが動けば、それをきっかけに両足で〝こぐ〟ことができるんです。」
自転車文化が根付いているヨーロッパや台湾では「障がいがある人や高齢者が、安心して乗れる自転車」としてCOGYをとらえる向きもある。リカンベント(寝そべった姿勢で乗る)自転車や競技用車いすのようなスポーティな外観と鮮やかなカラーリング、そして自分の足でこいで走行する。COGYは福祉用具のイメージを覆した。