
働き方改革の実現に向けて最も効果的なアプローチと考えられている「テレワーク」。すでに多くの企業がその導入により、業務効率向上や残業時間の削減に成功しています。その一方で、ICT環境・ツールを活用しきれず、生産性が低下してしまった企業も少なくありません。そうならないためには、リスクや課題を把握し対策を練って実施することが欠かせません。ここでは、テレワークに伴って発生しうるICT環境・ツールに関する課題と、それらにどのように向き合って対応すべきかについてご紹介します。
テレワークに関するICT環境・ツールの課題

調査規模1,100名、調査期間2021年4月12日~13日で、「第5回働く人の意識に関する調査(※1)」を日本生産性本部が実施しています。
※1 公益財団法人日本生産性本部 「第5回働く人の意識に関する調査」
https://www.jpc-net.jp/research/assets/pdf/5th_workers_report.pdf
この調査によると、テレワークの課題として、「Web会議などのテレワーク用ツールの使い勝手改善」が25.1%と、テレワーク用のツールに対する不満があがっています。また、テレワークを実現するために欠かせないICT環境に関する課題として、「Wi-Fiなど、通信環境の整備」が42.7%、「職場に行かないと閲覧できない資料・データのネット上での共有化」が29.9%、「情報セキュリティ対策」が27%、「押印の廃止や決裁手続きのデジタル化」が19.9%、「営業・取引先との連絡・意思疎通をネットでできるような環境整備」が15.2%となっています。
「その他」の1.4%を含め11個中6個なので、半数以上がテレワークを実現するために必要なICT環境に関わる課題となっています。「特に課題は感じていない」の16%と比較しても、相当の割合を占めていることが分かります。
テレワークに必須のICT環境・ツール

厚生労働省の「テレワークではじめる働き方改革(2016年)(※2)」によると、テレワーク導入を実現するためには、「マネジメント」と「コミュニケーション」と「セキュリティの確保」に関するICT環境・ツールを導入・構築する必要があります。
※2 厚生労働省 「テレワークではじめる働き方改革(厚生労働省 2016年)」
http://www.tw-sodan.jp/dl_pdf/14.pdf
まず「マネジメント」に関するICT環境としては、勤怠管理、プレゼンス管理(在席管理)、 業務管理(進捗状況確認)などの管理ツールが該当します。テレワークには、在宅勤務、モバイルワーク、サテライトオフィス勤務の3つの形態がありますが、勤務状況を直接目視できなくてもマネジメントするために必須のツールとなっています。
また、「コミュニケーション」に関するICT環境としては、文字、音声、映像などによるコミュニケーション方法の確保 、情報を共有するコミュニケーション基盤の構築などのコミュニケーションツールが該当します。具体的には、Eメール、チャット、WEB会議システム、情報共有ツール(データ共有)、情報共有 ツール(SNS)などが挙げられます。たとえば、WEB会議システムであれば、「letaria(レタリア)(※3)」が挙げられます。
※3 NTTドコモソリューションズ 「日本の会議を考え抜いたWEB会議システム」
https://www.nttcom.co.jp/dscb/letaria/
最後に、「セキュリティの確保」に関するICT環境ですが、利用するデバイスやシステム方式などICT環境におけるセキュリティの確保 、情報を社外に持ち出さずに業務を遂行できる環境の構築などのICT技術が挙げられます。具体的なICT環境・ツールとしては、端末へのログイン認証、HDD暗号化、ウイルス対策ソフト、セキュアブラウザ/コンテナ、覗き見防止フィルタ、情報漏えい対策付きのUSBメモリなどが挙げられます。各ICT環境・ツールの詳細については、「テレワーク関連ツール一覧(※4)」をご参照ください。
※4 一般社団法人 日本テレワーク協会 「テレワーク関連ツール一覧」
https://japan-telework.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/Tools-V6.0s-20210531.pdf
「第5回働く人の意識に関する調査(※1)」のテレワークに関するICT技術の課題を「マネジメント」「コミュニケーション」「セキュリティの確保」の3つに振り分けるとどのようになるでしょうか。
27%の「情報セキュリティ対策」は「セキュリティの確保」とはっきりしています。また、29.9%の「職場に行かないと閲覧できない資料・データのネット上での共有化」や15.2%の「営業・取引先との連絡・意思疎通をネットでできるような環境整備」は、「コミュニケーション」に振り分けられそうです。
しかし、よく考えてみると「セキュリティの確保」が制約条件にもなるため、はっきりと振り分けられないことが分かります。さらに42.7%の「Wi-Fiなど、通信環境の整備」に至っては、通信環境なくしてテレワークは成り立たないので、必須のICT技術となっています。このように、テレワークを実現するために欠かせない「マネジメント」「コミュニケーション」「セキュリティの確保」に関するICT環境の構築を現実の課題として捉えると、密接不可分の関係であることが分かります。
DX推進とテレワークに関するICT環境・ツールの推進

DX戦略、DX推進という言葉がちまたで流行しています。経済産業省が公表する「DX推進ガイドライン(※5)」のDXの定義によれば、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義されています。
※5 経済産業省 「DX推進ガイドライン」
https://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181212004/20181212004-1.pdf
また「The Countries Facing The Greatest Skill Shortages(※6)」によると、高速に進むグローバル化と技術刷新が労働市場を形作っていますが、スキル不足の面での企業への影響は国によって開きがあり、日本の企業に至っては最も深刻で、89%の日本企業の雇用者がスキル不足に陥っていると回答しています。最も影響が少ないと回答した中国の雇用者は13%で、76%もの開きがあります。
※6 statista 「The Countries Facing The Greatest Skill Shortages」
https://www.statista.com/chart/4690/the-countries-facing-the-greatest-skill-shortages/
日本企業のスキル不足を踏まえつつ上記のDXの定義を換言するならば、うまく活用すればビジネスインパクトを与えられるデータとデジタル技術があるにもかかわらず活用しきれていない企業が多いため、(他の企業と比較し)それを活用できるようになればそれだけライバル企業より優位に立てる、ということなのかもしれません。
2019年8月23日出版の「DX実行戦略 デジタルで稼ぐ組織をつくる」(日本経済新聞出版)という著書によれば、DX推進を成功させていくためには、デジタル技術に対するニーズや課題に対し個別に対応していくのではなく、デジタル技術戦略を統合的に描ききる、グランドデザインが重要だと説いています。
「マネジメント」「コミュニケーション」「セキュリティの確保」に関するICT環境の導入・構築を、現実の課題として捉えると、お互いが切り離せずに関わり合い影響し合っていることからも示唆されるように、デジタル技術の一部であるテレワークに関するICT環境の構築についても、DX推進と同様のことが言えるかもしれません。
そう考えると、各々のニーズ・課題を個別に対応・解決するのではなく、統合したグランドデザインがあり、その中にマッピングされた一部の要素として解決・対応をすることが望ましいでしょう。
ツールの網羅性と「Web会議などのテレワーク用ツールの使い勝手改善」①

製造元によって製品・ツールに関する設計思想も異なります。設計思想が違う製品を寄せ集めて組み合わせると、設計思想の違いからユーザビリティがチグハグで使い勝手が悪くなったり、肝要な機能の抜け漏れがあったり、またその逆で、同じ機能がオーバーラップし無駄な投資が発生するといった問題が起こりえます。
設計思想は統一されていればいるほど、上記のような問題を回避しやすいため、いろんな製造元から製品・ツールをかき集め組み合わせるよりも、網羅性の高い製品・ツールを選定するのが無難と言えるかもしれません。そうすることで、テレワークの課題、「Web会議などのテレワーク用ツールの使い勝手改善」も促進すると予想されます。
ツールの設計思想と「Web会議などのテレワーク用ツールの使い勝手改善」②
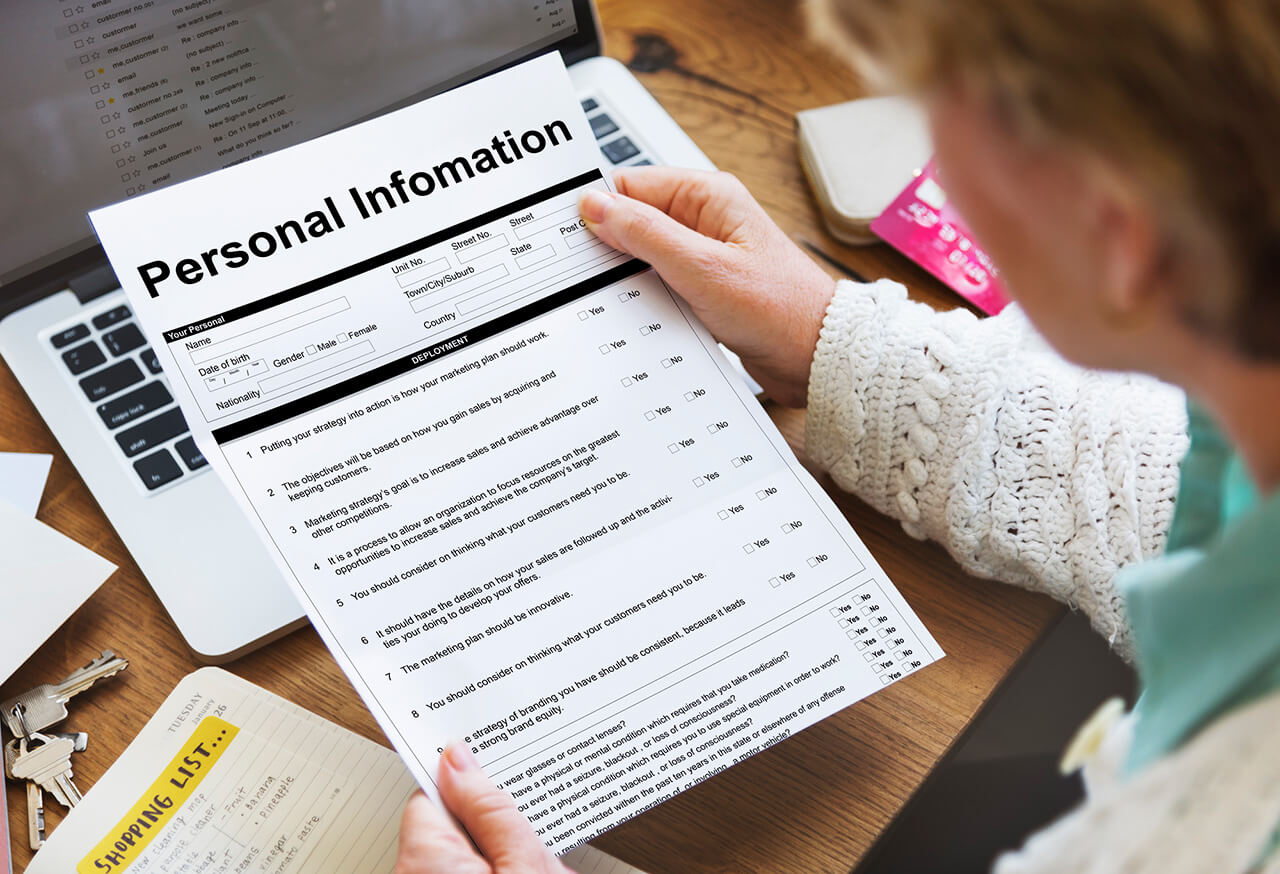
当然ですが、国や地域によって思想・志向も異なります。ここで(一財)日本情報経済社会推進協会が公表した「個人情報保護関連の海外の法制度の概要(※7)」を引用します。
日本の事業者や組織にとってのリスクは、国や地域によって異なる規律を守らなければ違法であるとされて罰則を課される可能性があることです。日本の「個人情報保護法」の遵守だけでは、このリスクを避けることができません。まず、国や地域によってどのような制度があるのかを知ること、個人情報の取扱いや越境移転がある場合に何に気を付けるべきかを知ること、が重要です。ただしその際に規律だけの解釈に頼ると判断を誤る可能性があります。その背後にある社会的要求や思想、制度の成り立ちや構造を知ることで、規律への対応の勘所が見えてきます。
※7(一財)日本情報経済社会推進協会 「個人情報保護関連の海外の法制度の概要」
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/05/12/documents/10.pdf
国や地域によって社会的要求や思想、制度の成り立ちや構造の多様性が伺える例として、ある新薬が治療に効果があるかどうか評価したいケースというのが挙げられるかもしれません。日本の場合、治療に有効な薬が市場に出ないリスクを許容し、ともすれば有害な薬が広まるリスクを低減させるため、新薬認可の基準を厳格化させていることが少なくありません。
まとめ

テレワークに関するICT技術の製品・ツール・サービスの網羅性という観点では、GAFAM(Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft)のサービスは強いかもしれませんが、すべてアメリカの企業です。ある程度以上の品質とサービスの網羅性が担保されているのであれば、アメリカ製と比較し日本製のサービスの方が日本企業との親和性が高いため、テレワークの課題、「Web会議などのテレワーク用ツールの使い勝手改善」も促進すると予想されます。
よくある質問
- テレワークに関するICT環境の課題とは?
-
Web会議やリモートデスクトップなどのインフラ整備に加え、勤怠管理、在籍管理、業務管理などのマネジメントツール、そして社内のコミュニケーション活性化のためのICTツールの整備が求められてきています。
- 国内発のICTツールの可能性は?
-
GAFAMの製品が網羅性という点において先行していますが、必ずしも日本のビジネスと親和性が高いとは限りません。マネジメント、コミュニケーション、Web会議システムなど、日本の商習慣に根差したツールも登場しています。国内サーバによるセキュリティの高さもメリットとなります。

