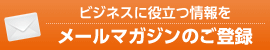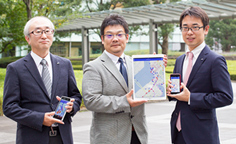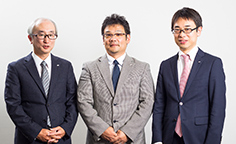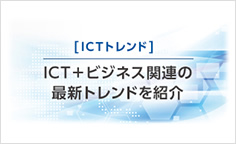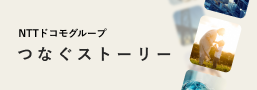マネージドサービスがクラウドの利便性をさらに向上
マネージドサービスがクラウドサービスとともに普及していった理由をもう少し詳しく見てみます。「所有」から「利用」へという「共通哲学」があることは先に述べましたが、もともと親和性が高いものといえるでしょう。
特にパブリッククラウドは、専門のIT管理者がいない中小企業やスタートアップでも気軽に導入できるのが魅力です。規模が小さい企業にとっては、運用保守を肩代わりしてくれる「マネージドサービス」があるからこそ、クラウドサービスを活用しやすくなっているといってもよいでしょう。
また規模が大きい企業であっても、少ない投資で新規事業を立ち上げることが可能ですし、事業の拡大に応じて、スケールアップ・スケールアウトなど柔軟に対応できます。
パブリッククラウドの初期設定は、利用者企業にとっては必ずしも「最適」ではないかもしれません。そのような場合も、マネージドサービスを活用することによって、利用者のニーズに細かく応える運用が可能になります。
プライベートクラウドやオンプレミスでもマネージドサービスの利用が拡大
マネージドサービスの魅力を考えれば、パブリッククラウドだけでなく、プライベートクラウド、あるいはオンプレミスにも、保守・運用のアウトソーシングをしたいと考える企業が出てくるのは当然の流れです。
オンプレミスとクラウドサービスを組み合わせて利用しているケース、あるいは複数のクラウドサービスを併用しているケースなど、複雑化した運用業務を一元的にアウトソーシングする事例も増えています。
特にマルチクラウド(複数のクラウド)、オンプレミスとの併用によるハイブリッド環境を利用する場合、複数の運用ツールを使いこなすことはIT管理者にとって大きな負担になります。増大する運用ツールの管理負担軽減にも、マネージドサービスが適しているといえるでしょう。
コスト抑制に寄与するアウトソーシング、品質も向上
システム管理者や経営層にとって、マネージドサービスはどのようなメリットやリスクがあるのでしょうか。
IT管理者にとって大きなメリットの一つは、フルタイムの監視体制を低コストに導入できることにあります。24時間の死活監視やトラブル時の対応などをアウトソーシングし、ダウンタイムを最小限にとどめることができれば、管理者の負担を大いに軽減できます。
もちろん運用保守のノウハウを蓄積した専門家にアウトソーシングすることで、安定したシステム維持が可能になり、サービスレベルや生産性の向上が期待できます。現代のビジネスシーンでは、システムダウンが損害や機会損失に直結することを考えれば、経営面からも大きなメリットです。
またクラウドは変化の激しいビジネス環境において、柔軟にリソースを調達することが可能です。それに伴い、必要となる人的リソースについても、マネージドサービスを利用することで、プロフェッショナルサービスを必要な量だけ調達できます。これにより、人件費など固定費を削減できます。
図3:マネージドサービスの利点
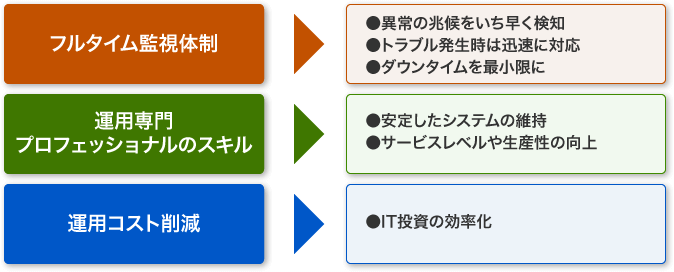
ITの予算のうち、運用保守に占める比率は決して低くありません。トラブルへの対応や、ソフトウェアの更新作業など、突発的に生じるコストは見落としがちです。導入にあたり、費用の固定費化を是とするか、リスクとコストのバランスをどのように判断するかなど、運用管理を見つめ直す必要があります。
企業のIT化はどこまでも進んでいて、複雑化の一途をたどっています。組織内の各セクションから寄せられる要望は絶えることがありません。IT管理者を運用保守という実務から解放し、本来業務に専念させることによって生まれるメリットにも目を向ける必要があるでしょう。
IT管理者は、問題が発生するたびに現地作業に駆り出され、原因究明が難しいアラートの対処に悩まされてきました。外部専門家の力を借りることで、蓄積したノウハウにより問題の切り分けが可能となり、負担も小さくなります。
社内ニーズに応えつつも、社内の前向きな業務に集中できる環境を提供することが、どの程度コストカットに影響するかをトータルに考えることが求められています。