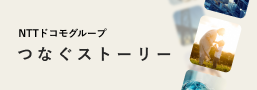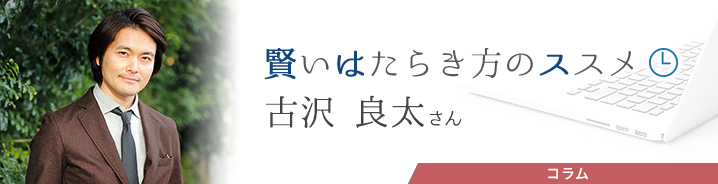
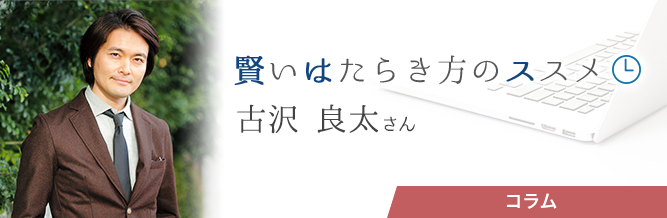
映画『ALWAYS 三丁目の夕日』シリーズや、テレビドラマ『リーガル・ハイ』シリーズなど数多くのヒット作を生み出している脚本家の古沢良太さん。2018年4月期の月9『コンフィデンスマンJP』は翌年5月には映画化となり、「この脚本家の作品なら見てみよう」と、いま名前で人を呼べる数少ないクリエイターの1人だ。手がける物語のジャンルも幅が広く見る者を飽きさせないが、自身は脚本家という仕事を天職とは思っていないという。先輩たちの仕事ぶりや現場の共同作業から影響を受けたという、自身の技術やアイデアをその場に合わせて発揮する柔軟なはたらき方は、協業がキーワードとなっている今のビジネスパーソンにとっても参考となるだろう。
知識やアイデアのストックがあるなら、失敗を恐れずにアウトプットしてみる
―古沢さんは、映画やドラマなど数々の人気作品で脚本を手がけておられますが、『ALWAYS 三丁目の夕日』のような人間ドラマから、最新作『コンフィデンスマンJP』のような奇想天外なエンタテインメントまで、同じ脚本家の作品とは思えないほどの幅の広さに驚かされます。多彩な題材で執筆される古沢さんですが、脚本家を目指したきっかけをお聞かせいただけますか。
古沢:もともと僕はテレビっ子で昔からテレビドラマをよく見ていたんです。一方で、絵を描くのも好きで漫画を描いたりもしていました。中学生のときに藤子不二雄先生の自伝的作品『まんが道』を読んで、漫画家を目指す青春に夢と憧れを抱き、独学で漫画の描き方を勉強しました。尊敬する手塚治虫先生が「漫画家になりたければ漫画を読むより、いい映画をたくさん見るべき」とおっしゃっていたので、いわゆる名作といわれる映画をたくさん見るようになりました。
中学生が精一杯、背伸びしていたわけですが、黒澤明監督の作品はまだビデオ化されておらずレンタルビデオ屋で借りることができませんでした。それで図書館で脚本集を読み始めたらのめり込み、向田邦子さんや倉本聰さん、山田太一さんなどの脚本を読むうちに、脚本家という仕事に興味を持つようになりました。大学生の時に養成講座に通って「何でもいいから1本書いてみなさい」と言われて書いたのが最初の脚本です。
―必然ともいえる自然な流れで脚本家を目指すようになったのですね。
古沢:そうでもないんです。書いた作品を先生に褒められたことが自信にはなりましたが、1本書き上げるのがすごく大変で、こんな作業を日常的に続けていく仕事なんて絶対に無理だと思ったんです。現実を知って脚本家の仕事に夢を持てなくなり、その後が続きませんでした。
「やっぱり自分は絵を描くほうが好きだ」などと気持ちが定まらず、定職にも就かずに20代を過ごしていましたが、さすがに20代後半になると「何とかしなければ」という気持ちが出てきて、自分の中にためてきた「物語のアイデア」をいったん全部出しきってしまいたいと思うようになりました。アイデアを形にしないまま脚本家を諦めるより、全てを出し切り気持ちをすっきりさせてから就職なりしようと考えたんです。それで、テレビ局の脚本コンクールに応募したら、なんと大賞をいただくことができました。自分の気持ちにけじめをつけるつもりで応募したのですが、脚本家としての第一歩を踏み出すことになったわけです。
「理想の実現」よりも、「制約の中で全力を尽くす」のがプロの仕事
―脚本家としての潜在的な素質が開花して、順調なデビューをされましたね。

古沢:受賞後、すぐにテレビ局から連続ドラマのオファーをいただいたのですが、デビュー直後は当然ながらうまく書けなかったし「この仕事はどうせこれっきりになるだろうな」と思いながら書いていました。本気で脚本家を目指している人たちと違って何の下積みもなく現場に入ってしまったので、右も左も分からないし、プロデューサーが厳しい方だったこともあり、思うように書けなくて嫌になってしまい「すみません、書けないのでこの仕事から外してください」と言って、実際に外してもらったんです。
それから2週間ぐらい経った頃、プロデューサーから電話がかかってきて「しばらく休んで気持ちも落ち着いただろうから、現場に戻ってきなさい」と呼び戻していただきました。僕が不在の間は江頭美智留さんなど脚本家の大先輩たちが書いてくださっていて、その脚本を読んだら「ああ、こうすればいいのか」と少しずつ要領が分かってきました。
―先輩方の脚本から、どのようなことを学ばれたのですか?
古沢:中学生の頃から背伸びして名作映画ばかり見てきたせいで、知らず知らずのうちに理想が高くなっていて、自分の書くものが本当に次元の低い、くだらない脚本に思えたんですよ。もっとああしなきゃ、こうしなきゃと届きもしない高すぎる理想を追い求めて「どうしてもうまく書けない」とがんじがらめになっていたんでしょうね。先輩方の脚本は、ちゃんと届く範囲で作品として成り立っていたんです。
連続ドラマはスケジュールや予算など、制限のある中で現実と折り合いをつけて制作していきますが、「やれる範囲で全力を尽くせばいいんだ」と気がついて、プロの仕事とはこういうものなのか、と感銘を受けました。要領をつかんだといっても、新人がそう簡単にうまく書けるわけもなく、最初の仕事は今までで一番苦しかったですね。脚本家としてやっていく決意もあやふやだった僕が、素人からプロになるためには避けられなかった修業期間だったと思います。
―プロとして脚本を書くには、魅力的な物語の創作はもちろん、さまざまな事情や制約に折り合いをつけ、現実的な視点で仕事を進める意識が必要なのですね。ビジネスの現場にも共通する課題だと思います。
古沢:物語を生み出すのも苦労の連続です。おもしろい話なんて、そうそう思いつかないですよ(笑)。脚本に取りかかる前に全体の構成をつくってプロデューサーに確認してもらうんですが、全く何も思いつかなくて、締め切りの日になっても1行も書けないということがありました。その時、プロデューサーに「当然、思いつかないこともあるだろう。それでもプロはでっち上げるんだよ」と言われて、また一つプロとしての仕事を学びました。
何も思いつかなくても、とりあえず何かを書いてみる。自分で「つまらない内容だな」と思いながらも書き進めていくと、「ここをちょっと変えてみたらおもしろくなるかな」ということを思いついて、少しずつ修正を繰り返していくと「何とか許せるかな」と思えるレベルには持っていけるんです。いまいち良くないと思えるアイデアでも、諦めずに細部を少しずつ改良していくことで、何とか合格点をもらえるぐらいにはできる。最初から素晴らしいアイデアなんて、なかなか出てきませんよね。