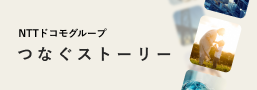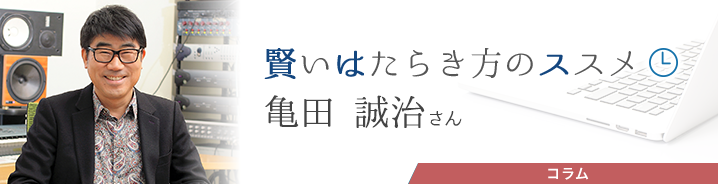
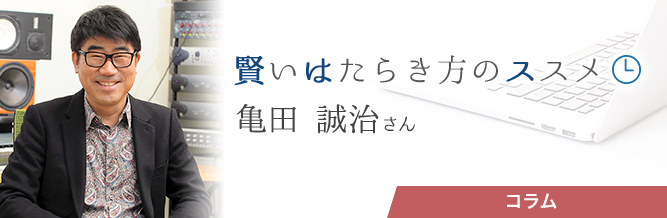
数々のヒット曲を生み出してきたJ-POP界のヒットメーカー亀田誠治さん。椎名林檎、平井堅、GLAY、いきものがかりなど人気アーティストのプロデュースやアレンジを手がけ、多くのミュージシャンから“師匠”と崇められている存在だ。新しいテクノロジーやサービスの登場により音楽業界は大きく変化してきたが、ごく自然に肯定的に受け止め、変わらぬ情熱で音楽制作に取り組み続ける。下積み時代の経験と、そこで得た技術を生かし、「いい音楽を作る」というゆるぎない仕事観と変化に適応するはたらき方は、ビジネスパーソンにとっても至極、参考になるに違いない。
表舞台にはない「堅実な仕事」が、確かな実力につながった
―30年以上の長きにわたり、プロデューサーやベーシストとして音楽業界の第一線でご活躍されていますが、この世界に入ったきっかけをお聞かせいただけますか。

亀田:小学生の頃から音楽が大好きで、将来は音楽に関わる仕事がしたいと思っていました。バンド、バックミュージシャン、制作担当、ミキシングエンジニア‐‐職種は問わず、とにかく何でもいいから音楽に関わりたかったんです。教育熱心な家庭で育ち進学校に進みましたが、大学時代にはバンドを組んだり、自宅録音をしたり、オーディションやコンテストに自作デモテープを送るようになりました。
そのデモテープがコンテストでグランプリや最優秀作曲賞、最優秀編曲賞を受賞するようになって、「この調子でこのままデビューできる!」と思っていたら、デビューしていくのはボーカルだったり、容姿端麗なドラマーだったりと、厳しい現実をつきつけられました。「まあ、亀ちゃんも勉強がてらスタジオに遊びに来たら?」と、もののついでに言われたりして。作曲も僕、作詞も僕、アレンジも僕、演奏も僕、それでも僕はアーティストとしてカウントしてもらえないのだと、24歳ぐらいで自覚したわけです。ずいぶん悔しい思いを味わいました。
でも、そこで僕はくさらずに、いろんな現場に出向いて“プロの仕事場”を見学することにしたんです。するとミュージシャンやボーカルを裏で支える音楽の仕組み、例えばディレクター、エンジニアの仕事ぶりがとにかくおもしろかった。そして「ここで起きていること全部に関わりたい」と思うようになりました。
―具体的には、何をしたのですか。
亀田:まず、受賞という形で認められていたデモテープ作りに集中しました。それをコツコツと2年ほど続けていたら、僕の楽曲がアーティストのシングルやアルバム収録曲として採用されるようになってきたんです。すると次はアレンジ(編曲)を頼まれるようになりました。同じ現場で一緒に作業をしていると、だんだんとディレクターに意見も言えるようになり、「このサビはコーラスが入ったほうがいいですよ。僕、試しに作ってきました」などとアイデアを出したりするうちに、「じゃ、次のアルバムは亀ちゃんが全部やってみてよ」という話になり、それが音楽プロデュースの道につながっていきました。
「自分から白旗を上げる必要はない」、困難な局面をプラスと捉える
―演奏よりも作曲、編曲の依頼が先だったのですね。

亀田:ほぼ同時でした。作曲、編曲を任されるようになると「亀ちゃんをチームに入れると、なんかいい感じだね」と言っていただくようになり、安定して声がかかるようになりました。どうも僕は楽観的なところがあって、その場のムードを明るくしているらしいんです。アマチュア時代の知人がその噂を聞きつけ、シンガーソングライターの崎谷健次郎さんのツアーにベーシストとして誘ってくれたことで、プレイヤーとしてのキャリアもスタートしました。20代半ばまでアマチュアの無名でしたが、26歳で作曲家、編曲家、プレーヤーの扉が一度に開いたわけです。
僕より先に華々しくデビューしていった仲間と比べたら、扉が開かない期間は長かったんですが、いったん扉が開いたら、CoCoというアイドルグループの編曲でいきなりチャートの上位に食い込みました。一流の制作マンやミュージシャンと毎日向き合うような状況に、飛び級で上がってしまった感覚です。
―飛び級で環境が急変して、ご苦労はありませんでしたか。
亀田 :僕はわりと、どんなことでも面白がってやれるタイプなんです。アマチュアの時からプロになっても、人に使われることが楽しくて(笑)。指示されたら想像以上のアウトプットで返してやろうという気持ちでやっていたので、楽しんでやっていました。
もちろん、常に楽観的でいられたわけではありません。崎谷健次郎さんのツアーメンバーに抜擢された時は、他のメンバーが大先輩や超一流のミュージシャンだったので、自分のプレーが下手過ぎて、毎日落ち込んでいました。それで「僕には荷が重い。無理だ」と思って、崎谷さんに辞めたいと言いに行こうとしたのです。そしたら逆に、「ちょうど今、ベースが最高だねってバンドのメンバーみんなで話していたんだよ」と言われたんです。
この経験から皆さんにお伝えしたいのは「自分から白旗を上げる必要はない」ということ。自己評価が低かったとしても、他人はそう捉えていないこともあります。それ以降、僕は自分からプロジェクトを降りたことがありません。それに、しんどいことはたまにありますけど、嫌な仕事は一つもないんです。例えば、音楽畑ではないクライアントの方と話していると、音楽的ではない発言が出てくることもありますが、それを的外れだとは思わずに「そういう視点があるのか」と興味深く聞いています。どんな状況も好奇心を持って臨むと、自分にとってプラスになるんですよね。
椎名林檎さんとの出会いもそうでした。椎名さんの楽曲は個性が強く歌詞も文学的で、デビュー前には「どうやって活かしたらいいかわからない」と言われていたんですが、「亀ちゃんだったら一緒に作品づくりができそうだから、会ってみない?」と彼女を紹介されました。椎名さんは初めからおもしろくて「マライア・キャリーが好き、サウンド・オブ・ミュージックも好き、ザ・ピーナッツも好き」と、洋楽も邦楽も関係なく、自分の感性で良いと思ったものは全部受け入れるところが、僕と波長が合うなと思ったんです。僕も彼女もマーケットを意識するよりも、自分のクリエイティブの軸や、やりたいことを大事にするタイプ。白旗を上げることなど考えもせず、この子となら何かできると思って椎名さんと作品作りを始めました。
―そして、プロデューサーの扉が開いたわけですね。
亀田 :やっていることはアマチュア時代と同じだと思います。アーティストとミュージシャンを信じて、全人生を使って今までにないものを生み出してゆく。椎名さんも同じ価値観で、ジャンルの枠を超えて「カッコいい」と思ったものを圧倒的な個性で表現してくれました。そうして生まれた作品によって、音楽プロデューサーとして認められるようになったんです。
―それ以来、本当に数多くのアーティストをジャンルに関わらず手がけていらっしゃいます。
亀田 :僕はジャンルにこだわりません。椎名林檎のプロデュースもするけど、アイドルや若いバンドのプロデュースもします。自分の中にある基準としては、アーティストや楽曲が心に響いて、世の中に届けたいと思うかどうか。それだけです。
ジャンル分けをして垣根を作ってしまうと、誰かを傷つけることもあるし、自分自身が損をすることもある。僕は多様性を大事にしたいと思っていて、音楽に対しても、そういった姿勢で取り組んでいます。