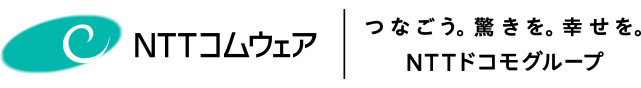矢来能楽堂様
舞台の動きに合わせて、詞章や解説をタブレットに配信。ICT活用で伝統芸能のファン層拡大を目指し、トライアルを実施
東京・矢来能楽堂様では、タブレット端末を用いて、舞台の動きに合わせて詞章(せりふ)や解説を配信するガイドサービス開始に向けたトライアルを実施しました。日本古来の伝統芸能である能楽をわかりやすく説明するこのサービスは、英語や中国語など複数言語に対応しており、訪日外国人観光客のさらなる増加が見込まれる中、能楽鑑賞の敷居を下げ、ファン層の拡大につながると期待されています。
舞台の動きに合わせて画面がスクロール
端末操作に煩わされずに能楽鑑賞を堪能
配信側の操作に合わせてタブレット画面が自動で切り替わるため、端末操作に煩わされることがありません。画面上の詞章や解説を見ながら鑑賞することで、演目への理解がより深まります。
30台の同時接続によるトライアルを実施
2015年9月に矢来能楽堂様で実施したトライアルでは、30台のタブレット端末を同時接続。参加者からは「鑑賞の邪魔にならず見やすくて便利」「わかりやすい説明に理解が深まった」といった感想が寄せられました。

- 導入効果1
- 画面の自動同期で能楽鑑賞の醍醐味を堪能
矢来能楽堂様では本トライアルサービスを用いて、より分かりやすく、かつ手軽に利用できるガイドサービスの実現を目指していました。本システムでは能楽関係者が舞台の動きに合わせて操作するマスター端末と鑑賞者の各端末の画面を同期させる仕組みとなっており、舞台が始まると鑑賞者のタブレットの操作は制限され、ページが自動で切り替わるようになるなど、端末操作に煩わされることなく舞台を堪能できます。
- 導入効果2
- 専用アプリ不要で、より手軽な配信が可能
本システムでは、HTML5に対応した標準のWebブラウザで動作しており、サービス利用に専用のアプリケーションを必要としません。そのため、例えば屋外で催される薪能など、大勢の観客が想定される公演において個人所有のタブレットやスマートフォンへのサービス提供が可能です。矢来能楽堂様も今後のそうした活用に大きな期待を寄せています。
- 導入効果3
- コンパクトな機材で、どこでも配信が実現
本システムに必要な機材は、配信・閲覧用のタブレット端末のほか、小型のWi-Fiアクセスポイントやサーバーと、コンパクトな機材で配線も不要、持ち運びも容易と、歴史ある能楽堂の設備に手を加えることなく、ガイドサービスがどこでも手軽に実現できます。

お客さまプロフィール
| 名称: | 矢来能楽堂 |
|---|---|
| 所在地: | 東京都新宿区矢来町60 |
| 営業開始日: | 1952年(昭和27年)現在の能舞台・建物が建てられる |
| 施設概要: | 1908年、観世清之が神田西小川町に舞台を設けたが、関東大震災で焼失。 1930年現在地に移って舞台を復興。しかし空襲で消失する。戦後の物資不足の中、二世 観世喜之によって1952年、現在の舞台が建てられた。 以来、観世九皐会(現 公益社団法人観世九皐会)の活動拠点となる。現在ではさまざまな演能活動にも利用されている。国の登録有形文化財である。 |
| 公式サイト: | http://yarai-nohgakudo.com/ |
この事例をPDF版で読む

導入事例一覧