
矢来能楽堂様
お客さまの声
- 観世 静子氏
- 有限会社 KNOW-NOH
代表取締役
鑑賞の妨げにならない最適なシステムを導入できました
能独特の調子や発声、能の囃子など存分に堪能してもらいたいとの考えから、一般的な音声ガイダンスではなく、タブレット端末を用いたガイドサービスの導入を決めました。普段から手元に資料を置いて鑑賞する観客も多く、タブレットであれば同様な鑑賞スタイルが実現することから、実際に利用したお客さまからの評価も上々で、「これからもどんどんやってほしい」などの感想を得ており、大きな手応えを感じています。今後の本格導入に向けてガイドサービスを提供できる演目を充実させたいですね。
トライアルを実施した矢来能楽堂は歴史が古く、国の有形文化財に登録されるなど、大規模なシステム導入は困難でしたが、配信機材は小型のWi-Fiアクセスポイントとサーバーで実現できるため、機材をタブレットと一緒にスーツケースに入れて持ち運ぶことも可能です。
若者だけでなく中高年も含め、能楽に触れたことのない日本人はまだまだ多く、タブレット端末を活用したこうした取り組みを通じて、より多くの方々に能楽を知ってもらいたい。NTTコムウェアには、使いやすく、革新的なシステムやサービス提供で、能楽のさらなる普及やファン層拡大に貢献することに期待しています。
- 椙杜 友美氏
- 株式会社 檜書店 取締役
台本のデジタル化は能楽のさらなる普及に不可欠
従来、能楽を見に来る人は、能楽を習っていたり、長年見続けている人が多く、事前に台本を読んでいたり、手元に資料を用意して公演に臨んでいました。しかし近年は一般の方が鑑賞する機会が増えており、さらには鑑賞を希望する訪日外国人観光客も増えていることから、新たな情報提供手段の整備が急務でした。そうしてさまざまなシステムを検討する中で、字幕のスクロールを手軽に制御でき、標準的なWebブラウザさえあれば専用端末やアプリケーションを用意しなくて済む運用のしやすさから、本システムを矢来能楽堂様に導入することを提案しました。
今後はNTTコムウェアの協力を得て、台本のデジタル化を効率よく進めていき、能楽の普及に貢献できればと考えています。
お客さまプロフィール
| 名称: | 矢来能楽堂 |
|---|---|
| 所在地: | 東京都新宿区矢来町60 |
| 営業開始日: | 1952年(昭和27年)現在の能舞台・建物が建てられる |
| 施設概要: | 1908年、観世清之が神田西小川町に舞台を設けたが、関東大震災で焼失。 1930年現在地に移って舞台を復興。しかし空襲で消失する。戦後の物資不足の中、二世 観世喜之によって1952年、現在の舞台が建てられた。 以来、観世九皐会(現 公益社団法人観世九皐会)の活動拠点となる。現在ではさまざまな演能活動にも利用されている。国の登録有形文化財である。 |
| 公式サイト: | http://yarai-nohgakudo.com/ |
-
*
製品およびサービスの内容は、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
-
*
その他、記載されている社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。
-
*
所属部署、役職等については、取材当時のものです。
この事例をPDF版で読む

導入事例一覧
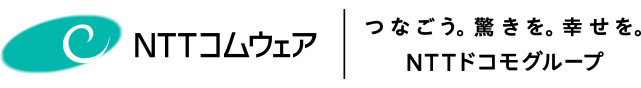

担当者の声
使い心地の良いシステムを、
お客さまと共に開発しました
開発に際して特に重視したのが、導入するシステムが能の鑑賞の妨げにならないこと。そのため、タブレットに搭載されているカメラやスピーカーなどのデバイス機能を無効にしたほか、画面も黒地に白文字のデザインにしたり、反射防止シートを貼り画面の光量を制限したりと、さまざまな工夫を施しました。加えて、鑑賞者が、端末の操作や画面の切り替えに煩わされずに済むよう、舞台の動きに合わせて詞章が最適なタイミングで自動的に切り替わるよう、スクロールの表示テストを多数回繰り返し実施。お客さまからの協力も得て、見やすくて分かりやすい、使い心地の良いガイドシステムを実現することができました。
本システムは能楽などの舞台鑑賞のガイダンスだけでなく、観光バスや習いごとなどでのガイドサービスへの応用が可能であり、今後は檜書店様と同様なさまざまなコンテンツホルダとの協業を通じて、多様な用途に役立ててもらうことを考えています。
品質生産性技術本部
研究開発部