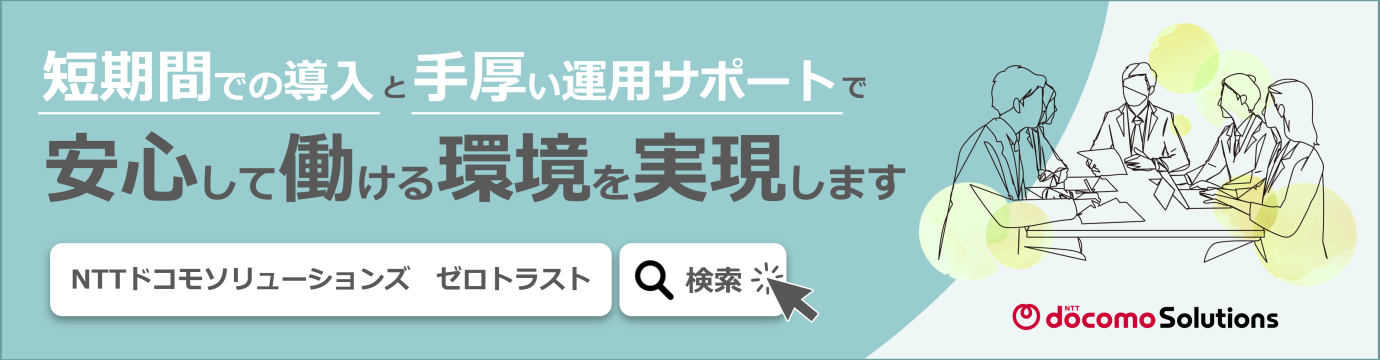2018年7月に公布された「働き方改革関連法」。順次施行されてきましたが、近年の新型コロナウイルスの影響でさらに注目されています。
政府が推奨する働き方改革のひとつにテレワークがあります。すでに多くの企業が検討し、導入しているのではないでしょうか?
テレワークによる働き方改革が進められていくなかで、これまでにもたくさんのメリットが挙げられていますが、それに伴いデメリットがあるのも現状です。
この記事ではテレワークにおける、主なデメリットの説明とその解決法のポイントを解説したうえで、対策としておすすめのITツールを紹介します。
テレワークとは何か?

テレワークとは、ICT(情報通信技術)を活用し、時間や場所の制約を受けずに仕事ができる柔軟な働き方という定義がされています。
主な形態として、「在宅勤務」・「モバイルワーク」・「施設利用型勤務」の3つが挙げられています。(※1)
- 在宅勤務
-
自宅にいながら会社にいるのと同じ業務をする働き方です。
- モバイルワーク
-
「モバイル:可動性」のある働き方。車や電車での移動中や、カフェや取引先などで業務を行うことです。
- 施設利用型勤務
-
勤務している会社とは別に、離れた場所に設置されたオフィスで業務を行う働き方。別名サテライトオフィス勤務とも呼ばれています。
※1 総務省 「テレワークの意義・効果」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/18028_01.html
このように国が推奨するテレワークは、会社に出勤しなくても業務を行うという大きな目的があり、さらには通勤時間の短縮や、コストの削減、仕事の効率をあげるといったメリットがあります。
テレワークのデメリットと解決策のポイント

テレワークが推進されていく中で起きた新型コロナウイルスの流行。その後のニューノーマルも見据え、早急にテレワークの導入を考えている企業も多いかと思います。しかし、準備不足のままテレワークを導入して失敗した企業もあることから(※2)、事前にデメリットを確認し対策をたてることをお勧めします。テレワーク導入による主なデメリットを以下に挙げます。
※2 総務省 「テレワークの動向と生産性に関する調査研究に関する報告書」
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/h22_06_houkoku.pdf
- 情報漏えいリスクや端末のウイルス感染への危惧
- 従業員の勤怠管理の難しさ
- コミュニケーション不足
- 電話応対の難しさ
- 従業員の評価基準の不明瞭さ
(1) 情報漏えいリスクや端末のウイルス感染への危惧
テレワークを導入することによって考えられるデメリットの中で、最も不安視されるのは情報漏えいによる事故です。
先述したように、テレワークとは会社の外にいても、同じ業務を可能にする新しい柔軟な働き方です。会社の大事な情報を外に移動させるので、機密情報の漏えいはもっとも避けたいところです。テレワークを導入している企業で、会社から持ち出したパソコンやUSBメモリの紛失や盗難が実際に起きています。それに伴い、端末がウイルス感染してしまうというリスクもあります。さらには、カフェなどの公共の場でセキュリティが万全ではないWi-Fiスポットから安全ではないネットワークに接続し、情報を抜き取られ、悪用されてしまうといったケースもあります。
解決策のポイントは、従業員のそれぞれの端末の取り扱いルールを見直し(例えば、公共のWi-Fiを利用しない等)、明確にすること。ネットワークシステムやアクセス管理などのセキュリティ対策の徹底、さらに紙の書類の紛失対策などになります。
詳しくは総務省のセキュリティガイドラインを参照することをおすすめします。(※3)
※3 総務省 「セキュリティガイドライン 第5版」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000752925.pdf
(2) 従業員の勤怠管理の難しさ
テレワーク導入により、仕事の生産性の向上や、採用力強化というメリットがある一方で、今までは見える範囲で業務をしていた従業員の姿が見えないので、勤務実態が把握できなくなるというデメリットが起こります。サボりやオーバーワークといった従業員個人で差が出てしまうのも現実です。
解決策のポイントは従業員の労働時間の管理システムの導入になります。
労働時間管理に関する厚生労働省のガイドラインの参照もおすすめします。(※4)
※4 厚生労働省 「使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf
(3) コミュニケーション不足
企業側、従業員側ともに発生するデメリットとして、コミュニケーション不足があげられます。
対面業務から遠隔業務になると、そもそもコミュニケーションが取りにくい環境への変化となります。報告のみの作業が増え、雑談などの単純な会話が減ってしまいます。
テレワークにおけるコミュニケーションはテキストやメール、SNSが主となるため、個人の文章力や読解力の差で情報伝達内容の認識に差異や時差が生じてしまいます。他にも、1人で業務をする時間が多くなるため、社員の孤立に加え、上司や同僚との信頼関係の構築が困難になるというデメリットもあります。
解決策のポイントは「コミュニケーションを取る」という積極性です。社員の意識改革やコミュニケーションの共通認識を明確にすることや、WEB会議などのコミュニケーションツールを上手く活用していくことです。
(4) 電話応対の難しさ

今まで会社内で行ってきた業務である電話応対は、テレワークにより複雑になってしまうというデメリットです。対策を怠ると担当者不在やコールバックの遅延が生じます。問い合わせの電話に迅速に対応できなくなるなどし、顧客の信頼を失うことになりかねません。
対策のポイントは転送サービスやアプリの利用、電話代行サービスです。どんなにテレワークやモバイル化が進んでも、電話や対面といった業務が全てなくなるわけではありません。顧客のニーズに合った応対ができる環境にしておくことが大事です。
(5) 従業員の評価基準の不明瞭さ
先にあげた、従業員の勤怠管理の難しさとコミュニケーション不足というデメリットでさらに難しくなるのが、マネジメント層による人事評価です。結果だけでは判断できない職種や業務が少なからずあります。作業プロセスが見えにくい中、さらにコミュニケーション不足も加わると、従業員に対する的確な評価が困難になるというデメリットです。
解決策のポイントは社内での評価項目や評価基準のルールを明確にし、きちんと共有することでしょう。他にも「人事評価システム」などのITツールの活用もおすすめします。
テレワークによるデメリットを解消するITツールの紹介

前述の主なデメリットはきちんとした対策をすることによって、ほとんどが解消できます。その中でも特に大事と思われるコミュニケーション対策・セキュリティ対策・人事評価システムに対応できるおすすめITツールを紹介します。
(1) チャットツール
テレワークでは、従来のオフィスワークのように「ちょっとわからないことがあるから隣の人と会話を……」ということが難しくなります。
しかし毎回それらをメールで送っていると、リアルタイムなコミュニケーションがとれず、業務が円滑に進みません。そのため、チャットツールの導入は重要です。
セキュリティが高く、使い勝手の良いものを選びましょう。
弊社では、NTT西日本社の「elgana」を利用しています。
NTT西日本「ビジネスチャットelgana」
https://elgana.jp
(2) WEB会議ツール
また、会議についても専用のツールが必要となります。
例えば、弊社の開発したWEB会議ツール「letaria」では、会議稼働を削減するための機能や、オンライン会議でのコミュニケーションを活性化するための機能が備わっています。
NTTドコモソリューションズ 「letaria(レタリア)」
https://www.nttcom.co.jp/dscb/letaria/
(3) ゼロトラストセキュリティサービス
テレワークにおいては、オフィスワーク以上にセキュリティに気を遣う必要があります。カフェ等での後ろ見、職場外でのPCの紛失、Wifi経由でのマルウェアの侵入などのリスクが考えられるためです。
どこでいつウイルスに感染するかわからない、そんな環境に適した対策が「ゼロトラスト型セキュリティサービス」です。
ゼロトラスト型セキュリティサービスであれば、ウイルスに侵入された場合を想定し、該当端末の切り離し、情報持ち出し時の再確認などの対策がなされています。弊社でもゼロトラスト型セキュリティサービスを展開しております。ぜひ参考にしてください。
NTTドコモソリューションズ「ゼロトラスト型セキュリティサービス」
https://www.nttcom.co.jp/dscb/zerotrust/index.html
(4) 電話システム
テレワークでは、お客様から職場への電話をダイレクトで受け取ることができません。
この問題を解決するには、電話の転送サービスが必要となります。
弊社で展開している「SmartCloudPhone」では、職場へのお電話を担当者のスマートフォンへと自動転送し、提携した担当者が自宅から電話を受けることができます。
NTTドコモソリューションズ 「クラウドPBX SmartCloud Phone」
https://www.nttcom.co.jp/smartcloudphone/
(5) 勤怠管理システム
テレワークでは、従業員の勤怠状況を目視で確認することができません。
そこでPCログを持って勤怠を管理できるシステムの導入が重要です
弊社で採用している「Follow」では、月の稼働予定を作成し、毎日実績を投入する形で、直感操作での稼働管理を実現します。また、PCログと勤務開始・終了時間との乖離を確認することもできます。
NTTドコモソリューションズ 「勤怠管理ソリューションFollow」
https://www.nttcom.co.jp/follow_s/
まとめ

働き方改革の大きな目玉のひとつであるテレワークにはたくさんのメリットがありますが、その一方でデメリットがあるのも見落とすことはできません。
デメリットを事前に把握し、その対策を講じることでスムーズにテレワークを導入できます。そしてテレワークを進めていく中で起こる問題にも、迅速かつ柔軟に対応することが可能になると考えます。
アフターコロナを見据え、テレワークへの移行を成功させるためにも、ITツールなども利用したデメリットへの対策をしっかりとした環境を作ることをおすすめします。
よくある質問
- テレワークの定義とは何か?
-
テレワークとは、ICT(情報通信技術)を活用し、時間や場所の制約を受けずに仕事ができる柔軟な働き方という定義がされています。主な形態として、「在宅勤務」・「モバイルワーク」・「施設利用型勤務」の3つが挙げられています。
- テレワークの主なデメリットとは?
-
(1)情報漏えいリスクや端末のウイルス感染への危惧
(2)従業員の勤怠管理の難しさ
(3)コミュニケーション不足
(4)電話応対の難しさ
(5)従業員の評価基準の不明瞭さ
- テレワークによるデメリットを解消するためには?
-
Web会議やビジネスチャットなどのICTツールに加え、コミュニケーション、マネジメント、電話応対など、様々な分野でITCツールを活用することでメンバーが離れて働くことのデメリット解消が期待できます。