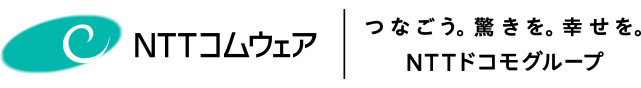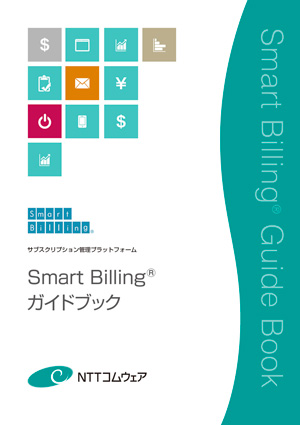表計算ソフトはシンプルながら多くの用途に対応できるため、大量データを扱う業務管理にも利用されているケースがあります。
しかし、共同作業が難しくデータ品質の担保ができない、関数・マクロの保守作業が属人化しがち、といった表計算ソフトの限界が叫ばれるようになりました。
表面的にはお手軽かつ安上がりのように見えても、思わぬところで業務効率化の妨げになっているのです。
では、表計算ソフトの他にどのような選択肢があるのでしょうか。
- 表計算ソフトによる大量データ管理の品質担保は困難
- 表計算ソフトを前提とした業務プロセスはガバナンス、コンプライアンス面のリスクが指摘される
- 新規事業立ち上げのときこそ、SaaSを活用して基本的なプロセスを取り入れる
- SaaS導入によって、サブスクビジネスに最適なバックオフィス業務を実現
表計算ソフトによる大量データ管理の品質担保は困難
管理業務において、表計算ソフトを利用している企業は多く見受けられます。
たいていのPCへ標準装備されており、直感的に利用できる上、関数やマクロを活用すれば高度な用途にも対応可能です。
しかし、見かけ上のコストは抑えられても、事業が拡大するにつれ、見えないコストが発生するようになり、結果として非効率になってしまうという課題があります。

例えば、表計算ソフトで商品・顧客・契約・請求・回収の情報を統合して管理するとしましょう。
商品価格や料金体系を改定する場合、過去の契約や請求データへ影響を与えないように商品情報の追加や変更を行う必要があるため、保守の難易度が上がります。
また、表計算ソフトでは手動でのデータ更新を可能な限り廃するため、関数やマクロを組んで情報を整理するケースが多いことから、こうした作業が得意な担当者へと属人的に作業が割り当てられてしまうことがあります。
その場合、他の担当者では関数やマクロをメンテナンスすることができず、担当者が異動した後ツールが陳腐化するという問題がしばしば見られます。
上記のような表計算ソフトを利用した管理業務や保守作業は、事業が拡大するにつれ継続していくことが非現実的になっていきます。数千件、数万件の契約を表計算ソフトで管理する場合、ファイルの容量が肥大化し、開くのにさえ時間がかかってしまいます。
さらに、管理項目が増えるほど複数のセルやシートにまたがったデータの整合性をとる難易度は高くなり、正当性を担保することが困難になります。
このように、はじめは簡単に扱えた表計算ソフトも、規模が大きくなるにつれ、誰も検証ができない、複雑怪奇なツールになってしまうリスクがあるのです。
表計算ソフトを前提とした業務プロセスはガバナンス、コンプライアンス面のリスクが指摘される
表計算ソフトで毎月の請求・回収業務を管理する場合、逐一手作業が伴うため、恒常的に労務コストが発生してしまいます。
どの顧客へいくら請求し、いくら入金があったかを表計算ソフトで記録していくためには、常に営業部門と経理部門の間で最新の情報を共有しておく必要があります。そうした点で、表計算ソフトは共同作業に向いていません。
表計算ソフトを前提とした業務では、「ムリ・ムダ・ムラ」が発生する傾向があり、業務効率化の妨げとなります。
膨大な件数を手作業で処理するために過剰な残業を担当者に課すのは、「ムリ」を強いていると言われても仕方のないことでしょう。
また、最新版を共有するため、メールでファイルをやり取りする場合がありますが、他のメンバーが更新するのを待っている間は待ち時間が発生するため、作業負荷の「ムラ」が発生します。
さらに、各人がバラバラにファイルを更新すれば、どれが最新版なのかの区別がつかなくなり、誤って内容が巻き戻ってしまう可能性があります。まさに作業の「ムダ」です。
データ入力者や承認者の役割を定義し、誰がデータを閲覧・更新できるかを定め、その証跡を残すことは、ガバナンスやコンプライアンスを考える上で重要です。
しかしながら、表計算ソフトではこの認証・認可の仕組みを実装する難易度が高く、情報漏洩や不正会計などのリスクが避けられません
新規事業立ち上げのときこそ、SaaSを活用して基本的なプロセスを取り入れる
「事業規模を拡大できるか分からないし……最初は表計算ソフトで済ませよう」
新規に事業を始める上で、そのように考える企業もあるかもしれません。 しかし、表計算ソフトで多くのデータを扱う場合のリスクを考慮すると、その考え方が本当に正しいのかどうか、再検討する余地があります。

事業の規模が拡大してきてからSaaS(Software as a Service)やPKGを導入する場合、表計算ソフトに最適化させた業務プロセスの見直しやデータ移行を実施する必要が出てくるため、新システムへの切り替えにコストと時間を要します。
さらに、請求のタイミングや請求書のレイアウトが変わる等、エンドユーザーへの影響も考慮する必要があります。
将来的に規模が拡大するかどうか分からない時こそ、初めからSaaSを導入・活用するのがスマートな選択だと言えます。
SaaSはオンプレミスのシステム構築と比べると短期間での利用も可能であり、導入にかかる初期費用も抑えられるのがメリットです。
表計算ソフトを作りこむよりも、初めから基本的な業務プロセスが定義されたSaaSを利用する方が、新規ビジネスの立ち上げもスムーズに進むと言えるでしょう。
オンプレミスとSaasの導入比較については、こちらの記事をご覧ください。

こんなに違うの?オンプレミス、SaaS導入比較
業務システムについて、SaaS(Software as a Service)という利用形態が普及したことから、多くの企業が直面するのが「オンプレミスでシステムを構築した…
SaaS導入によって、サブスクビジネスに最適なバックオフィス業務を実現
NTTドコモソリューションズでは、NTTグループがエンドユーザーに提供する様々な業種・業態の料金系システムを、長年担当してきました。
ここで培われたバックオフィスへの深い理解を元に、サブスクリプションに最適な請求管理SaaS「Smart Billing」を開発、提供しています。
サブスクリプション管理においてSaaSの活用を検討されているお客様へ、円滑なサービス導入と万全なサービス運用のご支援をさせて頂きます。