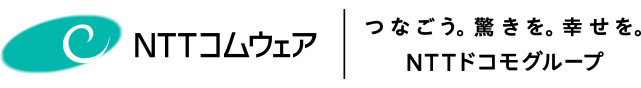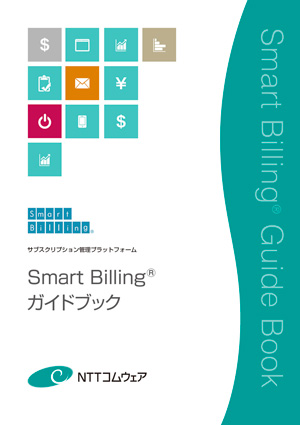継続的な収益が見込めること、収益の見通しが立てやすいことなどの特質から、企業の間で関心が高まっているサブスクリプション(以下「サブスク」)ビジネス。
しかし、実際には良いこと尽くめとは限りません。
新規事業として始めるにあたり、どのようなリスクが想定されるのでしょうか?
また、そのリスクを克服して収益を生み出し、事業として成長させていくためには、どのような取り組みが必要なのでしょうか?
サービススタート後、短期での黒字化は期待できない
従来的な売り切り型の販売モデルの場合、売れれば一括で売上が立つため、製造や仕入れにかかる原価を短期間で回収できます。
さらにそこで得られた収益を、次の製品の製造や仕入れの費用に回すことが可能です。
ところが、長期利用を前提に月々の利用料を押し延べて設定するサブスクでは、サービス開始当初の売上が売り切り型を大きく下回るため、製造や仕入れにかかる原価を短期間で回収することはできません。

そのため、サービス開始当初から爆発的に利用が伸びるようなケースでもないかぎり、初期投資コスト(製造原価、販売費など)に対して、短期的に売上が低迷し赤字が続くことになります。
つまり、投資額の回収期間が長期化するのです。
そのようなリスクがある一方で、長期的に見て利用する顧客が増加すればするほど、単純な販売モデルに比べ売上が伸びるため、挑戦する価値は十分にあると言えます。
リスク克服に向けた事業計画の立案
投資額の回収期間長期化というリスクを克服して事業を軌道に乗せるためには、イニシャルコストを企業の原資(資本金や現金など)で賄うか、もしくはイニシャルコストを抑えた事業計画を立案する必要があります。
まず方法として考えられるのは、仕入や調達の際にかかるイニシャルコストをランニングコストへ転嫁することです。
物品についてはリースやレンタルを活用するというのも1つの手ですし、一連の管理業務プロセスに必要なシステム導入をSaaSなどのクラウドサービス利用により賄うという選択肢もあります。

オンプレミスでシステムを構築する場合、開発のための外注費やハードの調達費用などで膨大なイニシャルコストがかかる上、仮に収益が期待できずビジネスそのものを撤収する事態に陥った場合、大きな損失が発生してしまいます。
そのようなケースであっても、クラウドサービスであれば途中解約も可能となるため、最小限の痛手に収めることができます。
コスト面も含めたオンプレミスとSaasの導入比較については、こちらの記事をご覧ください。

こんなに違うの?オンプレミス、SaaS導入比較
業務システムについて、SaaS(Software as a Service)という利用形態が普及したことから、多くの企業が直面するのが「オンプレミスでシステムを構築した…
次に、収益を早期に拡大させるための事業計画立案では、サービス内容やターゲット設定、価格設定などの戦略を明確化していく必要があります。
例えば、既存事業の販売モデルで取り扱っている商品をサブスクで提供する場合、ターゲットが重なり合ってしまえばカニバライゼーション(シェアの奪い合い)が発生し、サブスクの収益拡大を望めないだけでなく、既存事業の売上減少にも繋がってしまいます。
事実、サービス開始後にそのような問題へ直面し、短期での撤退を余儀なくされたケースは少なくありません。
サブスクへの参入は、企業にとって既存事業にも影響を及ぼす一大事だと言えるでしょう。
改善サイクルを意識した業務・分析プロセスの策定
サブスクへの参入により、ビジネスモデルが変革され、収益構造が一変することは、組織全体にも影響を及ぼします。
また、収益を拡大していく上で、顧客との長期的な関係構築と継続的なLTVの向上が根幹となるため、顧客とのあらゆるタッチポイントを意識してサービスの改善に取り組んでいく必要があります。
具体的には、マーケティング、セールス、カスタマーサクセスだけでなく、エンジニアも巻き込むなど、組織横断的な取り組みが求められるでしょう。
それだけに、サービス立案の時点で改善のサイクルが回せるよう業務・分析プロセスを設計することが肝要です。
以上の要素を勘案し、次の手順でサブスクのビジネスを検討していきましょう。
- フェーズ1. ビジネスモデルの策定
顧客にどのような価値をどういった経路で提供するのか、サービス内容と販売チャネル/物流チャネルなどの商流を決定します。
B2Cであれば想定される顧客の年代や性別、職業、居住地、趣味趣向、B2Bであれば企業規模、業種・業界、事業内容など、ターゲット設定を行います。
そのターゲットがどのようなカスタマージャーニーを辿るのかなどを含め顧客接点の構築も行います。
- フェーズ2. サービス設計
サービス料金や契約内容、保証範囲を定義し、規約・約款を制定します。
価格設定と料金体系設定は、サブスク成功の肝ともいうべき部分です。
顧客にとってのお得感、競合の料金設定、継続的な収益確保が可能かどうかなどのポイントをもとに検討します。
- フェーズ3. 業務プロセス設計
顧客からの申し込みが入ってから最終的にサービスを届けるまでの一連のサービス提供フローと、利用料を請求してから回収し会計処理を行うまでの料金業務フローを設計します。
各プロセスにおける役割分担、顧客から取得し管理する申込情報や契約情報、請求情報の定義を行うほか、サービスの決済手段についても検討が必要です。
- フェーズ4. 分析プロセスの設計
ビジネスが成長して結果を出しているか、収益拡大に向けた具体的な施策で目標が達成されているか、などを測定・分析するためのKPIを設定します。
そのKPIをどう算出するのか、そのためにどのようなデータが必要なのかを、事業戦略と業務の両面から設定することも不可欠です。
立ち上げ段階でこの部分をおろそかにすると、後々大きな失敗の原因になりかねません。
サブスクへの参入にはリスクも伴いますが、その回避・軽減に向けて事前に戦略と戦術を練っていけば対処することができます。
ビジネスを軌道に乗せることができれば、継続的な収益を企業にもたらすチャンスとなるため、挑戦するには十分な価値があると言えるでしょう。
リスクを軽減し、継続的な収益をもたらすためのプラットフォームの導入
NTTドコモソリューションズが提供する「Smart Billing」は、サブスクリプションビジネスの管理業務をトータルサポートするクラウドサービスです。
NTTグループの様々な業種・業態の料金系システムにおいて構築・保守・運用を担ってきた実績と経験をもとに、お客様の円滑なサービス導入と万全なサービス運用を支援いたします。