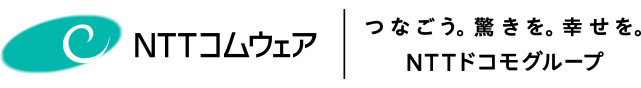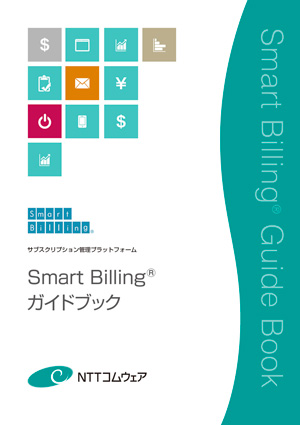製品やサービスなどを一定期間利用して、消費者が月々の料金を支払うサブスクリプション(以下、サブスク)ビジネス。
ソフトウェアや動画・音楽配信などのデジタル領域から家電、衣服やバッグ、食料品まで、さまざまなビジネスが生まれています。
サブスクでは、ずばりデータの活用が成功のカギを握っています。
また、従来の売り切り型サービスで重視される顧客単価と販売数に加え、サービス利用の継続率が重視されます。
そこで、データ活用やサービス利用継続率の観点からサブスクで収益を上げるヒントを探ります。
サブスクで収益を拡大するには
既存事業からの転換や、新規事業としてサブスクに興味や関心をお持ちの方からすれば、大きな関心ごとは以下の二つだと思われます。
1. 「そもそも、サブスクをやるメリットは何なのか」
2. 「サブスクでどのように収益を拡大するのか」
1番目のサブスクのメリットは、マーケティングに活用可能なデータを収集できることです。

顧客によるサービスの申し込みから利用、支払い、果ては解約までをシステムで管理することにより、サービスの取引に関するマクロデータや顧客に紐づくパーソナルデータが蓄積され、ビジネスの戦略へ活用することが可能になります。
2番目の収益拡大方法は、データ活用により顧客の求めるサービスをタイムリーに提供すると共に継続してサービスを改善することです。
顧客の満足度が高まるほど解約が減り、サービスを長期間利用してもらえることから、継続的な収益をもたらしてくれるのです。
サブスクを通じてデータドリブンな経営に生まれ変わる
それでは、サブスクで得られたデータを有効活用するためには、どうすればよいでしょうか。
システム上で得られたデータを分析し、顧客へのアプローチを変えたり、サービスの改善に繋げるデータ起点の手法を「データドリブン」と呼びます。
さらにこうした手法を用いたマーケティングを「データドリブンマーケティング」と呼ぶこともあります。
具体的には、サービスの契約から利用料金の請求・回収、解約といった一連のプロセスを「見える化」することで、顧客の利用状況や趣味趣向を把握し、レコメンドによるクロスセルやアップセルに繋げることができます。
また、利用頻度が落ちてきた顧客に対してダウンセルや一時的な休止などの提案を行うことで、解約の防止に繋げることも可能になります。
さらに、収益の向上に結びつく施策を適切に講じていくためには、KPI(主要業績指標)により検証することが肝要です。
例えば、立ち上げたばかりのサービスであれば新規契約者数が重要ですが、サービス開始から期間が経過し契約者数が増加した段階では収益に大きく影響を与えるのは解約率であり、解約率の低減が重要になります。
収集したデータを元に算出したKPIを活用し、マーケティングや販売における各施策の効果測定を行うことで、次に打つべき手の糸口が見えてくるのです。
サブスクではこんなデータ活用が有効
具体的な事例で、サブスクでのデータ活用例をみていきます。
食品宅配サービス「Oisix」※1は、徹底したデータ分析で解約率の低減を実現しているビジネスの好例です。
解約には、表には出てこないさまざまな理由や傾向がありますが、同社はそれらをアクセスログや購買データの分析によって見いだしたといわれています。

同社の定期配送は、発送前にLINEやメールで通知があり、配送のキャンセルや商品の組み合わせを変更することができます。※2
このような顧客に寄り添ったサービスも、解約防止に寄与する一連の取り組みの1つといえるでしょう
その他サブスクサービスの最新動向情報は、こちらの記事をご覧ください。

※2 有機野菜などの安全食品宅配 Oisix(おいしっくす)
『Netflix』※3などの動画配信サービスが成功した背景にも、こうしたデータ活用があります。
現在視聴している時間や場所、映画のカテゴリー、再生回数、視聴をやめたタイミングなどのデータを解析することにより、好みや関心を把握し、レコメンド表示や新たなコンテンツ制作に活用しているといわれています。
このように、サブスクとデータ活用は切っても切り離せない関係であり、ビジネスを成功させるうえで不可欠な取り組みです。
サブスクビジネスで得られるさまざまな情報を基に、顧客のサービス利用状況を分析することは収益向上につながります。
サブスクとデータ活用の重要性について、理解が深められたとしたら幸いです。
一連のプロセスの見える化やデータ分析ができる、サブスクリプションプラットフォーム「Smart Billing」の資料はこちらからダウンロードできます。